In vivo CAR-Tが持続的かつ強力にがんを攻撃するには、「CAR構造」そのものが鍵を握ります。特に、共刺激分子やシグナル伝達ドメインの設計は、治療効果と副作用のバランスに直結します。本記事では、CARの構成要素に焦点をあて、基礎から最新の改良型までを解説します。
目次
1. CARの基本構造とは?
CAR(キメラ抗原受容体)は、T細胞ががん細胞を認識・攻撃するために人工的に設計された受容体です。主に以下の構成要素から成り立っています:
- 抗原認識部(scFv): 抗体由来の領域で、がん抗原に特異的に結合
- ヒンジ領域: 柔軟性を与え、細胞間の距離調整に関与
- 膜貫通領域: 細胞膜を貫き、CARを細胞表面に安定的に配置
- 細胞内シグナル領域: 活性化と持続的反応を決定づける中核
中でも「細胞内シグナル領域」の設計が、CAR-Tの寿命・効果・副作用に強く関係しています。
2. 共刺激分子の役割とその進化
T細胞が完全に活性化するには、抗原認識だけでなく「共刺激」が必要です。CAR-Tにおいては、この共刺激信号を人工的に組み込むことで、T細胞の生存・増殖・サイトカイン分泌を調節できます。
代表的な共刺激分子:
- CD28: 迅速で強力な活性化を促進。ただし、疲弊や毒性のリスクも。
- 4-1BB(CD137): 活性は緩やかだが、長期生存やメモリーT細胞誘導に有利。
- OX40やICOS: 補助的な役割。第3世代CARに組み合わせとして用いられる。
世代別CAR-T構造の分類:
- 第1世代: CD3ζのみ。活性は不十分。
- 第2世代: CD28 または 4-1BB のいずれかを追加。
- 第3世代: 複数の共刺激分子を組み合わせ、より安定的な活性化。
3. シグナル伝達設計の工夫と課題
シグナル伝達設計は、「強すぎず、弱すぎない」反応を誘導するために重要です。
活性化の持続と疲弊のバランス:
CD28型は短期的な反応に向いていますが、T細胞が早期に疲弊することもあります。一方、4-1BB型は長期活性が持続しやすく、慢性疾患やin vivo型に好まれます。
新技術:チューナブルCAR(tCAR)
シグナル伝達の強さや持続時間を外部因子で制御できるよう設計された「調整型CAR」も登場しています。薬剤で活性レベルを調整する構造も開発されつつあり、毒性低減が期待されています。
融合ドメインの工夫:
CAR内部に制御モジュール(例:iCAR、SWIFF-CARなど)を導入することで、非がん組織での活性抑制や、逆にがん環境でのみ活性化する設計も進められています。
4. in vivo型での応用と次回予告
in vivo型CAR-Tでは、T細胞への遺伝子導入と同時に、望ましい反応性を示すCAR構造を体内で発現させる必要があります。そのため、以下のようなポイントが重要です:
- 共刺激分子の選定と安全性(CD28型 vs. 4-1BB型)
- 薬剤や環境因子によるオン/オフ制御可能性
- 体内での発現レベルの制御(プロモーター選択、tCAR構造)
これらの最適化により、より「精密医療」的なCAR-Tの構築が可能になります。
次回(第5回)は、「臨床試験の最前線と注目されるin vivo CAR-T開発企業」について詳しく解説します。いよいよ、基礎から応用、そして実用化へと進展する現場に迫ります。
🔗 関連記事・シリーズリンク
- 治療薬トレンド2025年:何が注目されているのか?
- 【第1回】少女エミリーが示した奇跡:CAR-Tとは何か?
- 【第2回】技術の核心:ナノ粒子・ベクター・mRNA
- 【第3回】標的抗原の選定
- 初心者向け入門シリーズ 記事一覧




この記事はMorningglorysciences編集部によって制作されました。


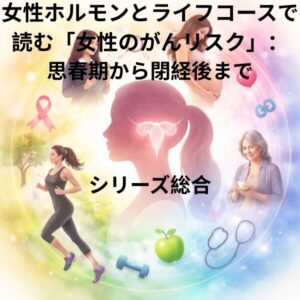
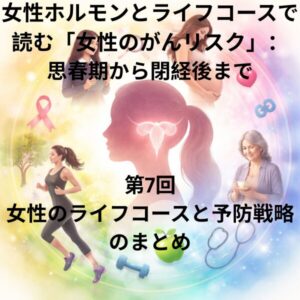
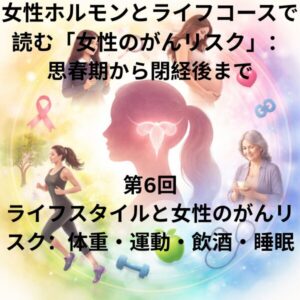
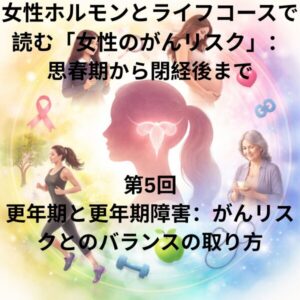
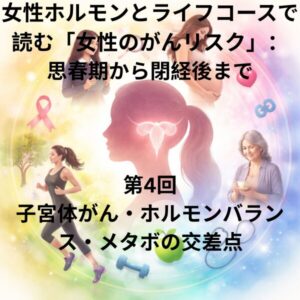
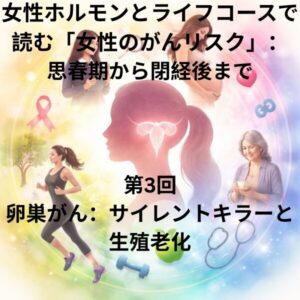
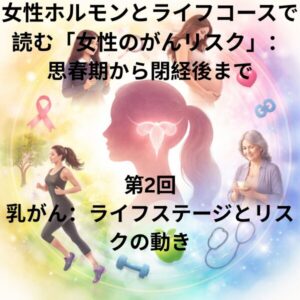
コメント