Fierce Biotechがまとめる「Layoff Tracker 2025」から、2025年前半に米国バイオテック企業で発生したレイオフ(人員削減)情報を読み解き、その背景と今後の展望について分析します。
1. 2025年前半に報告された主なレイオフ企業一覧
以下は、2025年にレイオフを発表した主なバイオ企業の一部です:
- Absci(AI創薬・タンパク質工学)
- Synthetic Biologics(感染症)
- Beam Therapeutics(ベースエディティング)
- Aeglea BioTherapeutics(希少疾患)
- Revelation Biosciences(呼吸器ウイルス)
- TScan Therapeutics(がん免疫療法)
- ImmunoGen(ADC、AbbVieによる買収直後)
- Cyteir Therapeutics(DNA修復標的)
- Akili(デジタル医療)
- Novavax(ワクチン)
これらの企業は、それぞれ異なる治療領域やプラットフォーム技術を持ちながら、共通して人員削減に踏み切っています。
2. レイオフの規模とその意味
報道により把握できた範囲では、レイオフ率は以下のようにバラつきがあります:
- ImmunoGen(AbbVieによる買収後):全社員の50%以上削減
- Absci:従業員の半数近くを削減
- Akili:80%以上のレイオフおよびNASDAQ上場廃止
- Beam:開発パイプライン整理に伴う20〜30%削減
20〜80%という大規模な削減が多く見られます。これは単なる組織のスリム化ではなく、「経営方針の転換」または「事業継続の危機」と直結しています。
3. レイオフが集中している分野と傾向
データを分析すると、以下のような分野で人員削減が集中しています:
- がん免疫療法(Immunotherapy):競争過多・臨床試験中止が相次ぐ
- 細胞・遺伝子治療(CGT):開発コスト高騰と規制対応困難
- 感染症ワクチン:COVID-19特需後の急速な冷え込み
- AI創薬・プラットフォーム技術:期待値は高いが商業化に時間がかかる
これらはどれも2020年以降に資金流入が著しかった分野であり、過去数年間で資金調達後に拡大した組織が、投資回収の目処が立たず見直しを余儀なくされている状況です。
4. 要因分析:なぜ今、レイオフが相次ぐのか?
背景には複数の要因が複雑に絡んでいます:
- 金利上昇とVC投資の冷え込み:2021年までのバブル的な資金流入が落ち着き、厳選投資の傾向へ。
- 市場環境の変化:IPO市場の低迷、M&A減少、バイオETFの停滞。
- 技術の商業化困難:期待されていた技術が臨床で成果を出せず、再編や撤退が加速。
- 買収による人員整理:ImmunoGenのように大手による買収に伴う重複人員の整理。
5. ポジティブな兆しも:選別と集中のフェーズへ
すべてがネガティブではありません。以下のような変化はむしろ健全化の兆候とも言えます:
- 赤字のまま上場維持していた企業の整理 → 実質的な淘汰
- 注力領域の再定義 → 成功確度の高いパイプラインに集中
- AI創薬の精緻化 → 技術と実用のギャップ解消へ
Layoffは社会的インパクトが大きいですが、業界構造をリセットし、次のフェーズに備えるための「必要な痛み」として位置づける見方も増えています。
6. 今後の展望と日本への示唆
米国のこの動きは、以下のような視点を日本のバイオ企業にも提供します:
- 過剰投資のリスク:バズワード的なテーマへの過度な集中は危険
- 出口戦略の設計:IPO依存ではなくM&Aも視野に入れた資本戦略
- 少人数・高精度のチーム設計:急成長よりも実行可能性を重視
日本ではレイオフのインパクトが大きいため、慎重な対応が必要ですが、世界の流れから目を背けずに戦略を立て直すことが求められます。
まとめ:再編期のバイオ業界に何を学ぶか
2025年のレイオフラッシュは、単なる景気後退のサインではなく、バイオテック業界の「構造的な成熟期入り」を示していると考えられます。
研究成果と事業性の両立、技術と社会実装の距離感、そして人材と資本の最適配置。これらを問い直すことで、日本のバイオ業界も次の10年に備えることができるはずです。
引き続き、Morningglorysciencesではグローバル動向を正確にキャッチし、読者とともに思考を深めていきたいと考えています。

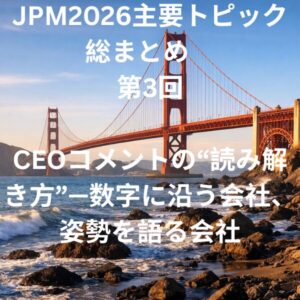
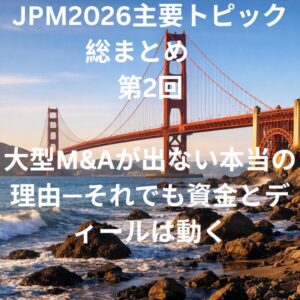

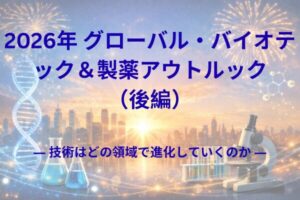

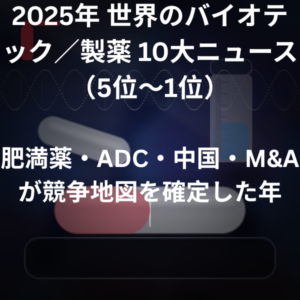
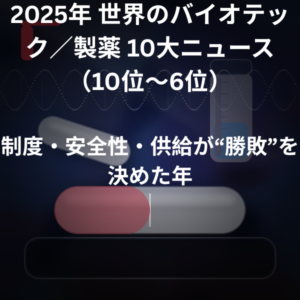

コメント