前回の第1回では、「なぜ今、ADC争奪戦が起きているのか?」という問いから出発し、 がん治療全体の中でのADCの位置づけ、Enhertu登場以降のインパクト、そして製薬・バイオ・投資家それぞれの動きを俯瞰しました。 本第2回では、一歩踏み込んで「ADCというモダリティそのものの設計」に焦点を当てます。
同じ「ADC」と呼ばれていても、その中身は大きく異なります。 第一世代のADCは、抗体・リンカー・ペイロードの組み合わせがまだ手探りで、 有効性や安全性の面で多くの試行錯誤がありました。 そこから改良を重ねた第二世代、さらにEnhertuのようなTopo-I系ペイロードとバイスタンダー効果を持つ「ポストEnhertu世代」、 さらにはサイトスペシフィックコンジュゲーションなどを特徴とする「第三世代」へと議論されることも増えています。
この記事では、ADCの構造(抗体・ペイロード・リンカー)を改めて整理したうえで、 第一〜第三世代の特徴と違いを整理し、「どの設計要素が臨床成績とディールバリューに効いてくるのか」を、 入門者にも分かる形で丁寧に解説します。 製薬企業・VC・コンサルの方にとっては、ADCのプロジェクト説明資料や学会発表を読む際の「読み方の軸」を持つことが、本稿のゴールです。
ADCの基本構造を整理する:抗体・ペイロード・リンカー、そして DAR
抗体:標的を認識する「案内役」
ADCの第一の構成要素は抗体です。 抗体は、がん細胞表面の特定の抗原(例:HER2、TROP2、CD30 など)を認識し、ADCを標的細胞へと運ぶ「案内役」の役割を果たします。
ADCの設計において重要なのは、「どの抗原を選ぶか」と「その抗原に対する抗体の特性」です。 理想的な標的抗原の条件としては、たとえば以下のようなポイントがよく挙げられます。
- がん細胞で高発現し、正常組織では低発現または限定的な発現に留まる
- 細胞表面に存在し、抗体結合後に内在化(internalization)される
- 腫瘍の進行や増殖に機能的な役割を持ち、腫瘍細胞にとって「捨てにくい」標的である
また抗体そのものの特性も重要です。 IgG1 か IgG2 か、Fcエンジニアリングを行うかどうか、ADCC/CDC 活性をどの程度残すか、といった設計は、 ADCとしての薬理作用のバランスにも影響を与えます。
ペイロード:強力な「実行部隊」
第二の構成要素はペイロード(薬物)です。 ADCのペイロードには、ナノモルレベルで強力な細胞毒性を持つ低分子薬が用いられます。 代表的なクラスとしては、
- 微小管阻害薬(maytansinoid、auristatin 系)
- DNA損傷薬(Calicheamicin、PBD、duocarmycin 系など)
- トポイソメラーゼ I 阻害薬(camptothecin系など)
ペイロードの選択は、有効性と毒性プロファイルの両方を規定します。 たとえば微小管阻害薬は伝統的な抗がん薬として長く使われてきたクラスで、安全性プロファイルもある程度蓄積されていますが、 神経障害や骨髄抑制などの懸念があります。 Topo-I系ペイロードはDNA複製へのダメージを通じて強力な殺細胞効果を持つ一方で、 間質性肺疾患(ILD)や消化器毒性など、別種のリスクを伴うことがあります。
リンカー:どこで・どのように毒を放つかを決める「スイッチ」
第三の構成要素がリンカーです。 リンカーは抗体とペイロードをつなぐ化学的な橋であり、どのタイミングでペイロードが切り離されるかを決める「スイッチ」の役割を果たします。
リンカーには大きく分けて、
- 切断可能(cleavable)リンカー:酸性環境、特定酵素、還元環境など、腫瘍・細胞内特有の条件で切れる設計
- 非切断(non-cleavable)リンカー:抗体が分解された後にペイロードが遊離する設計
があり、それぞれに長所・短所があります。 切断可能リンカーは、適切に設計されればバイスタンダー効果を生み出しやすく、 腫瘍内ヘテロジェネイティを乗り越えやすくなります。 一方で、循環中や正常組織で過度に切断されるとオフターゲット毒性のリスクが上がります。 非切断リンカーは、より「オンターゲット」の挙動が期待されますが、 抗原発現が不均一な腫瘍では効果が限定される可能性があります。
DAR(Drug-to-Antibody Ratio):何分子の毒をぶら下げるか
ADC特有のパラメータとしてDAR(Drug-to-Antibody Ratio)があります。 これは、「抗体1分子あたり何分子のペイロードが結合しているか」を示す指標です。
DARが高ければ、理論上は一度標的細胞に届いたときの「一撃の強さ」は大きくなりますが、
- 薬物動態(PK)が悪化しやすい
- 非特異的な取り込みやオフターゲット毒性が増えやすい
といった問題も出てきます。 逆に DAR を低く抑えると安全性は高まりやすいものの、十分な抗腫瘍効果を得るには高用量投与が必要になることもあります。 多くのADC開発は、この「DAR・リンカー安定性・ペイロード強度」のバランスの最適化との戦いと言えます。
第一世代から第三世代へ:ADC「世代論」を整理する
第一世代:コンセプト実証と「安全性の壁」
いわゆる第一世代ADCは、 「抗体+強力な毒」というコンセプトの実証に重きが置かれた時代の産物です。 標的やペイロード、リンカーの選択は現在から見ると粗削りな部分も多く、 有効性は示せたものの、毒性や製造上の課題から市場でのポテンシャルを十分に発揮できなかったケースも少なくありません。
第一世代ADCの特徴としては、
- ランダムコンジュゲーションによるヘテロな DAR 分布
- リンカーの安定性が十分でなく、循環中でのペイロード漏出リスクが高い
- 標的・ペイロードの組合せがまだ最適化されていない
といった点が挙げられます。 これらの経験は、以降の世代で「どこを改善すべきか」という学びとして蓄積されました。
第二世代:リンカーとペイロードの改良による「実用化」フェーズ
第二世代ADCは、第一世代で得られた教訓を踏まえ、「より安定したリンカー」と「より扱いやすいペイロード」を組み合わせることで、 実用的な安全性・有効性のバランスを目指した時代と言えます。
この世代のADCでは、
- 切断可能/非切断リンカーの最適化
- 微小管阻害薬など、毒性プロファイルがある程度理解されたペイロードの活用
- 標的抗原の選択・適応設定の最適化
が進み、「特定の患者集団に対しては明確なベネフィットを示す」製品が現れました。 しかし、適応が比較的限られていたり、腫瘍内ヘテロジェネイティを完全に克服するには至らないなどの課題も残りました。
第三世代:ポストEnhertu世代とサイトスペシフィック ADC
近年、「第三世代 ADC」と呼ばれることが多いのは、
- Topo-I系ペイロードとバイスタンダー効果
- サイトスペシフィックコンジュゲーション(特定のアミノ酸/挿入部位にのみペイロードを結合させる技術)
- 新しい標的(Claudin18.2、B7-H3など)や tumor-agnostic 的な設計
を組み合わせた、「制御された高火力」を志向するADCたちです。 Enhertuに代表されるような設計は、
- DARを比較的高く保ちながらも、リンカー・ペイロードの性質によって PK や安全性をコントロールする
- バイスタンダー効果を利用して HER2-low のような新たな患者層を取り込む
- 複数腫瘍種への展開を見据えたターゲット戦略を取る
といった方向性を示しており、従来の第二世代とは質的に異なるオプション価値を持っています。
また、サイトスペシフィックコンジュゲーション技術は、 従来のランダムコンジュゲーションに比べて製品の均一性・再現性を高め、DAR制御をより精緻に行うことを可能にします。 これにより、安全性・有効性だけでなく、製造面でのスケーラビリティや品質保証の面でも優位性を持つADCが生まれつつあります。
設計要素ごとに見る:ターゲット、抗体、リンカー、ペイロード、コンジュゲーション
ターゲット選択:生物学と市場の両面から考える
ADC開発においてターゲット選択は最初の重要な意思決定です。 ここには、生物学的な観点とビジネス的な観点の両方が絡みます。
生物学的には、
- 腫瘍と正常組織での発現差
- 内在化の速度とメカニズム
- 抗原のターンオーバー
が重要です。 ビジネス的には、
- 対象となる腫瘍種と患者数
- 既存・競合薬とのポジショニング(ファーストインクラス vs ベストインクラス)
- バイオマーカー検査の普及状況や実装可能性
などが検討されます。 「生物学的には面白いが、検査体制が整わず市場に結びつきにくいターゲット」や、 その逆も存在するため、研究開発と事業戦略のチームが早期から連携することが不可欠です。
抗体の設計:Fcエンジニアリングとアイソタイプ選択
抗体そのものの設計にも多くの選択肢があります。
- アイソタイプ(IgG1 / IgG2 / IgG4 など)
- Fc領域の変異により ADCC/CDC 活性を強めるか・弱めるか
- 半減期延長や免疫活性の微調整を行うかどうか
たとえば、抗体単体でも十分な抗腫瘍効果が期待できる場合は、ADCC/CDC 活性を残す設計が有効なことがあります。 一方、主役はあくまでペイロードであり、免疫活性は最小限にしたい場合には、Fc機能を減弱させた方がよいこともあります。
リンカー設計:切断トリガーと安定性のバランス
リンカー設計のポイントは、「どこまで循環中で安定させ、どのタイミングで確実に切らせるか」のバランスです。
- pH感受性リンカー:エンドソームなどの酸性環境で切断
- 酵素感受性リンカー:カテプシンなど特定酵素の作用で切断
- 還元環境感受性リンカー:細胞内の還元環境で切断
これらの設計は、腫瘍微小環境や細胞内環境に関する理解が深まるほど、より精密になっていきます。 最近のADCの成否を見ていると、リンカーの設計が有効性だけでなく毒性プロファイルにも大きく影響していることが分かります。
ペイロードの選択:強さと「扱いやすさ」
ペイロードは強ければ強いほど良い、というわけではありません。 もちろん高いポテンシーは重要ですが、同時に
- 合成・製造のしやすさ
- 代謝や排泄のされ方
- オフターゲット毒性のパターン
なども考慮する必要があります。 たとえば PBD など極めて強力なDNA損傷ペイロードは、小さな漏出でも重篤な毒性を引き起こすリスクがある一方で、 Topo-I系ペイロードは、バイスタンダー効果を活かしつつも、用量調整やモニタリングによってある程度コントロール可能という見方もあります。
コンジュゲーション技術:ランダムか、サイトスペシフィックか
最後に、抗体とペイロードをどのように結合するか、というコンジュゲーション技術があります。 従来は、抗体中のリジン残基やシステイン残基に対してランダムに結合させる方式が一般的でした。 この方式では比較的技術的ハードルが低い一方で、 「DARや結合位置にばらつきのある ADC の混合物」として製品が形成されます。
これに対し、近年のサイトスペシフィックコンジュゲーションでは、
- 特定部位へのアミノ酸改変やタグ挿入
- 酵素的なコンジュゲーション反応
などを用いて、「決まった位置に、決まった数だけペイロードを結合させる」ことを目指します。 このアプローチにより、製品の均一性、PKの再現性、毒性プロファイルの予測可能性が高まり、 規制当局やパートナー企業にとっても評価しやすい ADC となります。
Enhertu世代の意味:Topo-I ADCが示した「プラットフォーム」の姿
Enhertu型 ADC の設計思想:高DAR×バイスタンダー効果
EnhertuのようなTopo-I系 ADC は、
- 比較的高めの DAR
- 酵素感受性リンカー
- 膜透過性のあるペイロードによるバイスタンダー効果
を組み合わせることで、HER2-high だけでなく HER2-low のような、従来は標的治療の期待が薄かった患者層にもベネフィットをもたらしました。 ここで重要なのは、「標的抗原の発現レベルだけで患者を線引きしない」方向性を示した点です。
この設計思想は、他の標的(TROP2 など)にも応用されつつあり、 「Topo-I ADC プラットフォーム」として複数のパイプラインを展開する企業も増えています。 ターゲットを変えつつも、ペイロードとリンカー、コンジュゲーション技術の組み合わせはある程度共通化することで、 開発・製造の効率化とリスク分散を図るアプローチです。
世代論としての位置づけ:第二世代と第三世代の橋渡し
Enhertu型ADCは、「第二世代」と「第三世代」のちょうど間に位置するような存在として語られることもあります。 リンカーやペイロードは明らかに従来型とは異なる一方で、 コンジュゲーション方式は必ずしも完全なサイトスペシフィックではないなど、 技術的にはグラデーションのある世界です。
世代ラベルに厳密な定義はありませんが、実務的には、
- 第二世代:より安全で扱いやすいリンカー・ペイロードの組み合わせで、特定患者集団を確実に狙うADC
- Enhertu世代:Topo-I系ペイロードとバイスタンダー効果によって、患者層と適応の幅を一段広げたADC
- 第三世代:サイトスペシフィックコンジュゲーションなどにより、さらなる均一性・制御性を追求するADC
といったイメージで捉えておくと、各社のパイプラインの位置づけを理解しやすくなります。
非専門家が「ADCの技術説明」を読むときのチェックポイント
チェックポイント1:ターゲットと患者集団
製薬・VC・コンサルの視点でADC案件を見る際、 まず確認したいのは「どのターゲットで、どの患者集団を狙っているのか」です。
- 標的抗原は何か? その腫瘍種での発現頻度は?
- 既存治療と比べて、どのライン(一次/二次/三次)での使用を想定しているか?
- バイオマーカー検査の普及状況や、将来の検査インフラ整備の見込みは?
ここが現実的でなければ、どれだけADCの設計が巧みでも、ビジネスとして成立しにくくなります。
チェックポイント2:ペイロードとリンカーから見える「性格」
次に、ペイロードとリンカーの組み合わせです。
- ペイロードのクラスは何か(微小管阻害、DNA損傷、Topo-I など)?
- バイスタンダー効果を持つ設計か、それともよりオンターゲット寄りか?
- リンカーはどのようなトリガーで切断される設計か?
これらの情報から、そのADCが「どれだけ広く・どれだけ強く」攻撃しようとしているのかの性格付けをある程度推測できます。 また、想定される毒性プロファイルも、ある程度のイメージを持つことができます。
チェックポイント3:コンジュゲーションと製造の現実性
最後に、コンジュゲーション方式と製造戦略です。
- ランダムコンジュゲーションか、サイトスペシフィックか?
- どのようなスケールで製造が可能か? CDMOとのアレンジはどうなっているか?
- 品質管理(CMC)の観点から、規制当局との対話に必要なデータを準備できそうか?
技術的に魅力的なADCであっても、製造や品質保証の面で無理があれば、 実際の臨床開発・商業化で大きな壁にぶつかります。 ADC案件を見る際には、技術説明の裏にある製造・サプライチェーンの現実性にも目を向けることが重要です。
私の考察
ADCの設計を第一〜第三世代というラベルで整理してみると、一見きれいに進化しているように見えます。 しかし実務の現場では、世代という区分よりも、 「どの要素を、どの程度コントロールできているか」が本質だと感じます。 ターゲット選択、抗体の性質、リンカーの安定性、ペイロードの強さ、コンジュゲーションの均一性—— これらの要素のうち、どれをどこまで意図的に設計できているかが、そのADCの「世代」を決めているように見えます。
Enhertu世代のTopo-I ADCは、その意味で一つの転換点でした。 バイスタンダー効果を前提にした設計により、HER2-low のような新しい患者層を開拓し、 同時に規制当局・医師・ペイヤーの「ADCに対する理解」を一段引き上げました。 これは、個々の製品の成功だけではなく、ADCというモダリティ全体の「プラットフォーム化」を促した出来事でもあります。
一方で、第三世代ADCとして語られるサイトスペシフィックコンジュゲーションや新規ペイロードは、 まだ発展途上の部分も多く、必ずしも全てが Enhertu 以上の成果を出しているわけではありません。 重要なのは、世代ラベルを鵜呑みにするのではなく、 「このADCは、ターゲット・リンカー・ペイロード・コンジュゲーションのどの軸で、従来より一歩先に踏み込んでいるのか」を個別に見ていくことだと思います。
次回の第3回では、こうした技術的な進化がなぜビッグファーマの特許補填戦略(パテントクリフ対応)と直結しているのかを掘り下げていきます。 単に「新しい技術だから」ではなく、「なぜ次の10年の収益エンジンとしてADCが選ばれているのか」を、 ポートフォリオとディール戦略の観点から整理していきたいと思います。
本記事は、Morningglorysciencesチームによって編集されています。
関連記事 / Related Articles
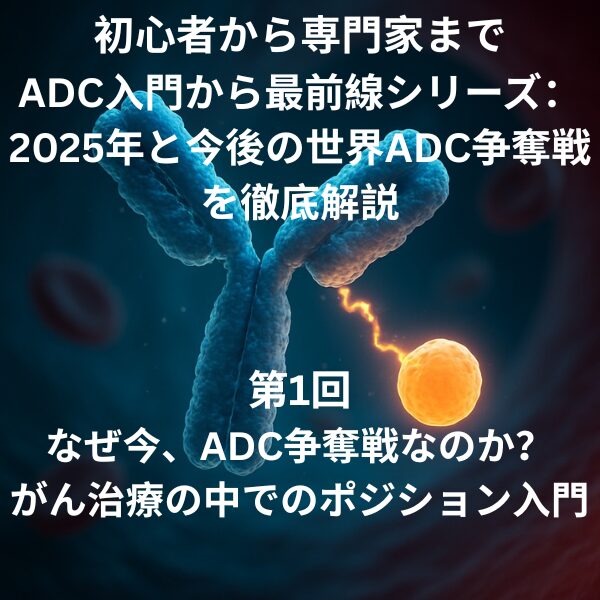



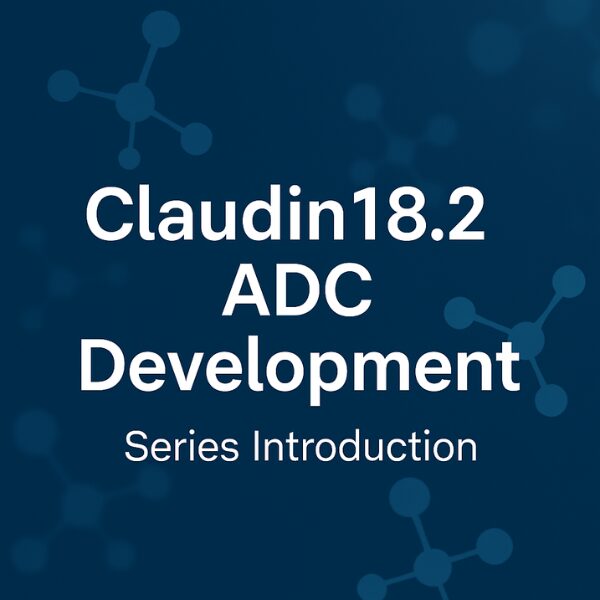












コメント