イントロダクション:老化の「中身」にズームインする
第1回では、「がんはなぜ加齢とともに増えるのか?」という問いに対して、歴史的な変遷と、老化とがんのホールマーク(特徴)が大きく重なっていることを概観しました。時間の経過=変異の蓄積、という単純な図式から一歩進み、「老化そのものが細胞や組織のコンテクストを変化させ、その上でがんが立ち上がる」というイメージを共有しました。
第2回のテーマは、その「コンテクスト」の中身を、分子・遺伝子レベルでもう少し丁寧に見ていくことです。具体的には、
- DNA損傷とゲノム不安定性
- テロメアと細胞分裂限界
- エピゲノムと3Dゲノム構造
- ミトコンドリア・代謝・タンパク質品質管理
- 細胞老化(senescence)と SASP
といった要素が、老化とがんにどう関わるのかを、できるだけ数式や難解な専門用語を使わずに説明します。研究レベルでは膨大な詳細がありますが、ここではあくまで「何が起きているのか」「それががんとどうつながるのか」を理解するための“道標”をつくることが目的です。
専門家の方にとっては、知っているはずの概念をあらためて俯瞰し直す機会として、非専門家の方にとっては、「老化」や「がん」のニュースや論文を読むときの背景知識として活用していただければと思います。
DNA損傷とゲノム不安定性 ― 「老化」と「がん」の共通土台
老化とがんのどちらにとっても、最も分かりやすい共通項は「DNAの傷」と「ゲノム不安定性」です。ここでは、日常的に起きているDNA 損傷のイメージと、なぜ老化でそれが問題化しやすくなるのか、そしてがんではどう利用されるのかを整理します。
DNAは毎日どれくらい傷ついているのか
私たちの DNA は、常にさまざまなストレスにさらされています。紫外線、喫煙や大気汚染などの化学物質、代謝の副産物として生じる活性酸素(ROS)、さらには自然放射線など、細胞の外にも中にも「DNAを傷つける要因」は無数に存在します。
よく引用される概算として、「1日のうちに1細胞あたり数万回規模のDNA損傷が起こる」と言われます。もちろんその大部分は、細胞内の修復機構によって素早く、そしてかなりの精度で修復されます。しかし、修復が完全ではない場合や、修復の過程自体にミスが混じる場合もあります。
若いころの細胞では、こうした損傷と修復のバランスが比較的うまく保たれており、致命的な変化が残る頻度は低めにコントロールされています。ところが、加齢とともに修復機構そのものが疲弊したり、一部の経路が機能不全になったりすると、損傷の「後始末」が徐々に追いつかなくなり、結果として DNA の変異が蓄積しやすくなります。これが老化に伴う「ゲノム不安定性」の一側面です。
老化で何が変わるのか:修復の“質”と“量”の低下
DNA 修復には、塩基除去修復、ミスマッチ修復、相同組換え修復、非相同末端結合など、複数の異なる経路があります。どの経路が働くかは、損傷の種類や細胞周期のタイミングに応じて決まります。老化細胞では、
- 修復に必要な酵素群の発現レベル低下
- エネルギー代謝の低下に伴う修復能力の低下
- エピゲノム変化により修復因子がターゲット部位にたどり着きにくくなる
といった変化が重なり、「修復のスピード」と「修復の精度」両方が少しずつ落ちていきます。これによって、細胞の DNA には、小さな変異から大きな再編成まで、さまざまな異常が蓄積していきます。
がん細胞はゲノム不安定性を“武器”にする
一方、がんの側から見ると、このゲノム不安定性は“毒にも薬にもなる”要素です。極端にゲノムが不安定だと、細胞はそもそも生き延びることができません。しかし「ギリギリ許容される程度」の不安定性は、がん細胞にとっては多様性と進化の源になります。
例えば、抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬が投与されたとき、ゲノム不安定な腫瘍では、多様なクローンが存在するため、その中に「たまたま薬に強い」「たまたま免疫から逃れやすい」クローンが含まれる確率が高まります。こうしたクローンが選択されて増えていくことで、治療抵抗性が出現します。
つまり、老化にともなう DNA 修復能力の低下とゲノム不安定性は、がんの「種」を増やすだけでなく、「治療に対するしぶとさ」を獲得する土台にもなり得る、ということです。
テロメアと細胞分裂限界 ― 安全装置と抜け道
もうひとつ、老化とがんを語る際によく登場するキーワードが「テロメア」です。テロメアはしばしば「染色体のキャップ」や「靴ひもの先端(金具)」にたとえられます。ここでは、テロメアがなぜ老化の尺度として語られ、がんでどのように悪用されるのかを整理します。
テロメアはなぜ短くなるのか
DNA 複製の仕組み上、細胞が分裂するたびに、染色体のいちばん端の部分は完全には複製できません。その結果、テロメアは分裂のたびに少しずつ短くなっていきます。一定レベルまで短くなると、細胞は「これ以上の分裂は危険だ」と判断し、増殖を止めたり、アポトーシスを誘導したりします。
この仕組みは、一種の「細胞分裂回数カウンター」として機能しており、組織の過剰な増殖やがん化を防ぐための安全装置でもあります。加齢とともにテロメアが短くなることは、細胞や組織の再生能力が低下していくメカニズムの一部を説明します。
テロメラーゼと“複製不死化”
がん細胞は、この安全装置を乗り越えるために、テロメアを再び伸ばす仕組みを利用します。代表的なのが「テロメラーゼ」という酵素です。テロメラーゼは、テロメア配列を付け足すことで、短くなったテロメアを延長する能力を持っています。
通常の体細胞ではテロメラーゼの活性は低いか、ほとんど認められませんが、多くのがん細胞ではテロメラーゼが再活性化されています。その結果、がん細胞はテロメア短縮による分裂限界を超えて、事実上“複製不死”の状態になります。これは「がんのホールマーク」の一つである「複製不死化(replicative immortality)」に相当します。
老化・がん・テロメアをどう捉えるか
テロメアの短縮は、老化とがんの両方で重要です。ただし、短くなりすぎれば細胞は死ぬか老化し、がん化どころではありません。逆に、テロメラーゼが活性化しすぎると、細胞はほぼ無限に分裂できるようになり、がんリスクが高まります。
このバランスの上に成り立っているのが現実の生体です。老化の過程でテロメアが短くなることは、ある意味では「がんになる前にブレーキを踏む」ための仕組みですが、がん細胞がテロメラーゼを再活性化した時点で、そのブレーキは強力な選抜圧へと変わり、「最も抜け道をうまく見つけたクローンだけが生き残る」という状況になります。
エピゲノム変化と3Dゲノム ― スイッチの入り方が変わる
DNAの「文字列」自体は変わらなくても、「どの遺伝子がいつ・どれくらい働くか」は、エピゲノムによって大きく変わります。さらに近年では、染色体が細胞核の中でどのような立体構造(3Dゲノム)をとっているかも、遺伝子発現に大きく関与していることが分かってきました。
エピゲノムとは何か ― DNAの“楽譜の書き込み”
エピゲノムとは、DNA メチル化やヒストン修飾、クロマチンの凝縮・解凝縮状態など、「DNA配列の上に書き込まれた制御情報」の総称です。よく使われる比喩として、
- DNA配列=楽譜の音符
- エピゲノム=演奏指示(テンポ・強弱・どの楽器で弾くか)
というイメージがあります。同じ楽譜でも、演奏指示が違えば全く異なる音楽になります。同じ DNA 配列を持つ細胞でも、エピゲノムが違えば全く別の細胞タイプや機能を持ち得るわけです。
加齢に伴うエピゲノムの“ずれ”
加齢とともに、エピゲノムパターンは少しずつ「ずれ」ていきます。例えば、
- 本来メチル化されて静かであるべき領域のメチル化が減ってしまう
- 逆に、本来開いていてほしい遺伝子のプロモーターが異常にメチル化される
- クロマチンの高次構造が変化し、遠く離れたエンハンサーとプロモーターの関係が乱れる
といった現象です。これにより、本来は抑えられているはずのレトロトランスポゾンが活性化されたり、炎症関連遺伝子が過剰に発現したり、逆に DNA 修復や抗酸化に関わる遺伝子が十分に働かなくなったりします。
3Dゲノムとがん ― 立体構造の乱れがスイッチを狂わせる
染色体は、細胞核の中でランダムに詰め込まれているわけではありません。実際には、
- 活発に遺伝子が発現している「Aコンパートメント」
- 比較的静かな「Bコンパートメント」
- TAD(topologically associating domain)と呼ばれる領域内での高頻度な相互作用
など、秩序だった3D構造をとっています。この3D構造が、エンハンサーとプロモーターを近づけたり遠ざけたりすることで、遺伝子発現の精密な制御を支えています。
がんでは、この3Dゲノム構造が乱れ、
- 本来つながるべきでないエンハンサーがオンコジーンの上流につながる
- 逆に腫瘍抑制遺伝子が「静かな」コンパートメントに押し込められる
といった現象が起こります。老化によって3D構造が少しずつ崩れていくことは、こうしたがん特有の3Dゲノム異常が生じやすくなる土台と考えることができます。
ミトコンドリア・代謝・タンパク質品質 ― エネルギーと“メンテナンス”の問題
老化とがんを考えるとき、「エネルギーをつくる工場」と「タンパク質のメンテナンス」の問題も避けて通れません。ここではミトコンドリアと代謝、そしてタンパク質品質管理(プロテオスタシス)の観点から、老化とがんのつながりを見ていきます。
ミトコンドリア機能不全と活性酸素
ミトコンドリアは、ATP を産生するエネルギー工場であると同時に、細胞内で最も活性酸素が生じやすい場所です。加齢とともに、ミトコンドリア DNA の損傷や、ミトコンドリアの数・形態・品質を管理する仕組み(ミトファジーなど)が低下し、機能不全のミトコンドリアが増えていきます。
その結果、エネルギー産生効率は下がりつつ、活性酸素の漏出が増えるという、細胞にとっては厳しい状況になります。活性酸素は DNA やタンパク質、脂質を傷つけ、さらに老化とがんの両方を加速させる要因になります。
代謝のシフトとがん ― Warburg効果からその先へ
がん細胞は、「Warburg効果」と呼ばれる現象、すなわち酸素が十分にある状況でも解糖系を強く利用するという特徴を示すことが多いとされます。これはエネルギー産生効率だけを見れば不利なはずですが、増殖に必要な生合成原料を大量に確保するという点では有利に働きます。
老化細胞でも、ミトコンドリア機能の低下や栄養シグナルの乱れにより、代謝経路の使い方が変わっていきます。インスリン・IGF-1 経路、mTOR、AMPK、NAD+代謝などのネットワークは、老化とがんの両方に深く関与しており、これらを制御する薬剤や食事・運動介入は「老化制御」だけでなく「がん予防・治療」にも関わる可能性があります。
タンパク質品質管理(プロテオスタシス)の破綻
細胞内では、日々合成されるタンパク質のうち、折りたたみに失敗したものや傷ついたものを見つけ出し、修復したり分解したりする仕組み(プロテオスタシス)が働いています。これにはシャペロンタンパク質やユビキチン・プロテアソーム系、オートファジーなどが関わっています。
加齢とともにこれらの系が弱まり、「異常タンパク質が溜まりやすい」「細胞ストレスに対処しにくい」状態になっていきます。神経変性疾患などではこのプロテオスタシス破綻がよく知られていますが、がんの世界でも、プロテアソーム阻害薬(多発性骨髄腫など)やシャペロン阻害薬のように、タンパク質品質管理の系を標的とする治療が実際に使われています。
老化によるプロテオスタシス破綻は、がん細胞にとっては「弱点」である一方で、ストレス耐性の高いクローンを選び出す圧力にもなり得ます。どの程度のストレスが、どの方向に働くかは、細胞の種類や環境によって大きく異なります。
細胞老化(senescence)と SASP ― 防御機構から“土壌”へ
第1回でも触れましたが、細胞老化(senescence)は、老化とがんをつなぐ上で非常に象徴的なプロセスです。ここではもう少し丁寧に、その二面性とメカニズムを見ます。
細胞老化は「がん抑制」の第一線
細胞が深刻な DNA 損傷やテロメア短縮を認識すると、p53 や p16 などの分子を介して細胞周期を停止し、不可逆的な増殖停止状態(senescence)に入ります。この状態の細胞は、増殖こそしませんが、代謝的には活発で、周囲にさまざまな因子を分泌します。
このプロセスは、短期的には非常に重要ながん抑制機構です。「危険かもしれない細胞」が増殖を続けて腫瘍になる前に、増殖の回路を完全に止めてしまうことで、組織全体の安全を守っているわけです。
SASPと炎症性老化(inflammaging)
しかし、senescent な細胞が長期的に組織に滞留すると、話は変わってきます。これらの細胞が分泌する SASP(senescence-associated secretory phenotype)は、炎症性サイトカイン、ケモカイン、増殖因子、マトリックス分解酵素など、多岐にわたります。これらは周囲の細胞の性質を変え、免疫細胞を呼び寄せ、細胞外マトリックスを組み替え、血管の状態を変えます。
結果として、組織は慢性的な軽度炎症状態(inflammaging)に傾きます。この環境は、前がん病変の増殖を助けたり、上皮間葉転換(EMT)を促進したり、免疫回避を助長したりする可能性があります。一方で、SASP によって免疫細胞が呼び寄せられ、senescent な細胞が除去されるという面もあり、そのバランスは非常に微妙です。
セノリティクスと「老化標的がん治療」の可能性
近年、senescent な細胞だけを選択的に除去する「セノリティクス(senolytics)」と呼ばれる薬剤群が研究されています。これらはマウスの実験レベルでは健康寿命の延長や一部がん治療との併用効果が示されており、今後ヒトでの臨床応用がどこまで進むかが注目されています。
老化した細胞をどこまで、どのタイミングで、どの組織で除去すべきかはまだ議論の余地がありますが、「老化そのものを標的にしてがんの予後を改善する」という発想は、まさに「老化 × がん」領域ならではの新しい治療コンセプトと言えます。このテーマは、入門編の最終回や疾患編であらためて取り上げる予定です。
「老化の分子地図」とがんドライバー変異の関係
ここまで見てきたように、老化は DNA 損傷、テロメア、エピゲノム、ミトコンドリア、代謝、プロテオスタシス、細胞老化など、多層的な変化の集合体です。これらをまとめて「老化の分子地図」と呼ぶならば、その地図の上に「がんドライバー変異」がどのように位置づけられるかを考えてみることが重要です。
同じ変異でも“土壌”が違えば挙動が変わる
がんゲノム研究が進んだ結果、特定のがん種で頻出するドライバー変異(例:KRAS、EGFR、PIK3CA、TP53 など)はかなりの程度カタログ化されました。しかし、同じ変異を持っていても、患者ごとに腫瘍の進行速度や薬剤感受性が大きく違うことは日常診療の中でもよく見られる現象です。
この違いの一部は、「どのような老化プロファイルの組織に、その変異が生じたか」によって説明できるかもしれません。例えば、
- すでに強い慢性炎症と線維化が進行している肝臓に TP53 変異が入る場合
- 比較的若く、まだ再生能力が保たれている肝臓に同じ変異が入る場合
では、同じ TP53 変異でも、その後の選択圧やクローン展開のパターンが変わることが十分に考えられます。
老化シグネチャーとがんシグネチャーの重なり合い
トランスクリプトーム解析やエピゲノム解析を用いると、「老化した組織で共通して上がる遺伝子群」「特定のがんで共通して上がる遺伝子群」といった「シグネチャー」を定量的に扱うことができます。最近の研究では、組織ごとの老化シグネチャーとがんシグネチャーがどのように重なっているかが解析されつつあり、
- ある組織では、老化がそのままがんシグネチャーを強める
- 別の組織では、老化がむしろ増殖シグナルを抑える方向に働く
といった臓器特異的な違いが見えてきています。こうした視点は、「この患者の、この臓器に、この変異が入ったときの危険度」をより精密に評価するための重要な手がかりになります。
まとめ:分子レベルの老化を“静的な劣化”ではなく“動的な背景”として見る
第2回では、老化とがんをつなぐ分子・遺伝子レベルの要素を、主に次の観点から整理しました。
- DNA損傷とゲノム不安定性:老化で修復能力が落ちることで、変異の「素材」としての多様性が増え、がんや耐性クローンの土台となる。
- テロメアと細胞分裂限界:本来はがん抑制的な安全装置だが、がん細胞はテロメラーゼなどで抜け道をつくり、複製不死化を獲得する。
- エピゲノム・3Dゲノム:加齢に伴うエピゲノムの“ゆらぎ”と立体構造の乱れが、がん関連遺伝子のオンオフを狂わせる土壌になる。
- ミトコンドリア・代謝・プロテオスタシス:エネルギー産生の低下とストレスの増加、タンパク質品質管理の破綻が、老化とがんの両方を複雑に形づくる。
- 細胞老化と SASP:短期的にはがん抑制的な防御機構である一方、長期的には炎症性老化と腫瘍促進的な微小環境を生み出し得る。
- 「老化の分子地図」とドライバー変異:同じ変異でも、どのような老化背景の上で生じるかによって、腫瘍の性質や進行が変わりうる。
重要なのは、これらの分子レベルの変化を「一方的な劣化」としてではなく、「がんという現象が起こる背景としての動的な環境」として理解することです。老化は、がんのリスクをただ単純に増やすのではなく、「どのようながんが、どのような速度と性質で現れてくるか」という“質”をも左右します。
次回(第3回)では、この分子レベルの変化が「免疫」と「腫瘍微小環境(TME)」にどう影響し、結果としてがんの発生と進展にどのように関わるのかを掘り下げていきます。老化とがんを理解するうえで、免疫老化と炎症性老化(inflammaging)は欠かせないテーマですので、ぜひ続けて読んでいただければと思います。
私の考察
分子・遺伝子レベルの老化とがんの関係を眺めてみると、「老化=がんのリスク要因」という単純な図式の裏に、非常に精巧で動的なバランスがあることが浮かび上がります。DNA 損傷、テロメア、エピゲノム、ミトコンドリア、代謝、細胞老化――それぞれが単独で働いているわけではなく、互いに影響し合いながら、最終的に「がんが起こりやすいのか起こりにくいのか」「どのようながんが立ち上がりやすいのか」という現実のアウトカムを形づくっています。
個人的に印象深いのは、「老化の分子機構の多くが、本来は防御や適応のために存在している」という点です。DNA 修復、細胞老化、テロメアによる分裂制限、代謝の適応変化――どれも短期的には生体を守るための仕組みですが、繰り返しストレスがかかり、長期にわたって使い続けられる中で、少しずつ“副作用”が蓄積し、最終的にはがんの土壌にもなり得ます。この「防御と代償が裏返るポイント」をどう見極めるかが、老化とがんの交差点を理解する鍵だと感じています。
また、「同じがん遺伝子変異が入っても、老化背景によって腫瘍のふるまいが変わる」という視点は、今後の個別化医療・予防戦略にとって重要な意味を持つと思います。がんゲノムだけを見て治療を決めるのではなく、「そのゲノムがどのような老化プロファイルの上に乗っているのか」を一緒に評価できるようになれば、より精度の高いリスク評価や治療選択が可能になるかもしれません。
本シリーズでは、こうした分子レベルの知識を、免疫、生活習慣、性差・生殖老化、老化時計・AI 解析などと組み合わせながら、「老化とがん」を多層的に理解する土台をつくっていきたいと考えています。専門領域の異なる方々が、それぞれの立場からこのテーマに関わるときに、共有できる“共通言語”のようなものを提供できれば幸いです。
本記事は、Morningglorysciencesチームによって編集されています。
関連記事 / Related Articles
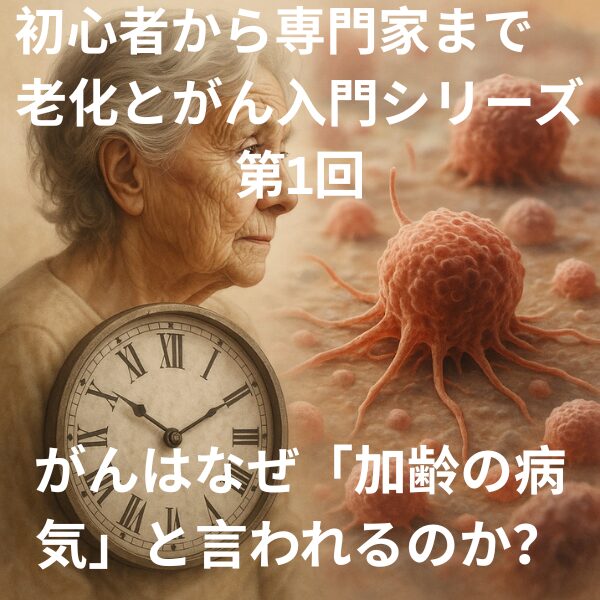

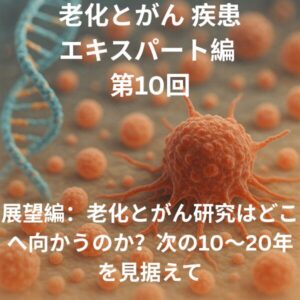
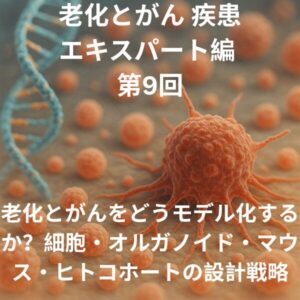

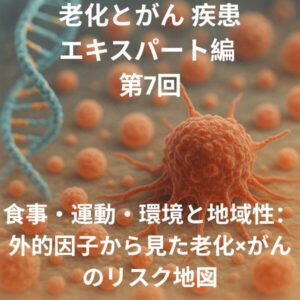


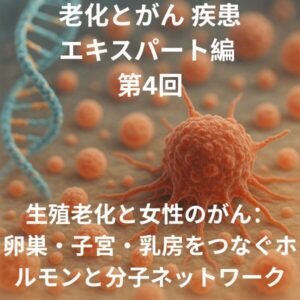

コメント