2025年前後のオンコロジー領域では、抗体薬物複合体(ADC)を軸とした「次の10年」をめぐる争奪戦が一気に加速しています。本シリーズでは、その中でも特に動きが激しいビッグファーマの最新データとディールを俯瞰し、「いま何が起きているのか」を臨床開発・事業戦略の両面から整理していきます。
本記事・第1回では、Enhertu/Datrowayの成功を足場に、「自社ADCプラットフォーム+放射性医薬+細胞治療」までを一体で構築しようとしているAstraZeneca(AZ)の戦略を取り上げます。ADCの仕組みや設計の基礎といった入門的な内容は、別途公開予定の「初心者から専門家まで|ADC入門から最前線シリーズ:2025年と今後の世界ADC争奪戦を徹底解説」で体系的に解説する予定です。
本シリーズの位置づけと読み方
「ここ最近数ヶ月のADC臨床試験・大型ディール総覧シリーズ」は、ESMO・WCLCなど主要学会や直近のM&A/ライセンス契約をもとに、「いま最新のADC開発・事業戦略がどこまで来ているか」を俯瞰するニュース解説編です。個々のADCの構造やリンカー・ペイロード、標的分子の基礎生物学については、入門シリーズ側の記事と相互に行き来して読める設計にしていきます。
対象読者としては、研究者・製薬企業のR&D/事業開発担当・CVCや投資ファンド・コンサルティングファームなど、日々の実務で「具体的な社名・プロジェクト名・試験名」を扱う方を想定しています。一方で、ADCそのものに興味を持ち始めた医療従事者・学生・一般の方でも全体像が追えるよう、必要な専門用語にはできるだけ簡潔に補足を入れます。
2025年秋、なぜ今AstraZenecaの戦略が注目されるのか
AstraZenecaは、Daiichi Sankyoとの共同開発品であるHER2標的ADC「Enhertu」とTROP2標的ADC「Datroway」によって、一気にADCのトップランナーの一角に躍り出ました。両剤は乳がんを中心に適応拡大とラインシフトを重ね、売上面でもブロックバスターになりつつあります。
しかし、AstraZeneca自身はすでに「Enhertuの次」を見据えています。Enhertu/Datrowayという“外部協業”ADCに続き、自社リンカー・自社Topoisomerase Iペイロードを用いた社内ADCポートフォリオ、放射性医薬(radioconjugates)、バイスペシフィック抗体、T細胞エンゲイジャー、そして細胞治療(CAR-T/in vivo cell therapy)までを、一つのオンコロジー戦略として束ねている点が特徴です。
この「モダリティ横断型」の設計思想は、単に個別アセットの寄せ集めではなく、「抗体+ペイロード+標的+診断・バイオマーカー」を組み合わせるプラットフォームを全体として最適化する発想に近いものです。ADC単体ではなく、「化学療法を置き換えうる一連の治療体系」としてのポジションを狙っている、と見ることができます。
Enhertu・Datrowayが切り開いたDXd時代
AstraZenecaとDaiichiの最初の成功例であるEnhertuは、HER2陽性乳がんにおいてRocheのKadcylaを相次いで上回る臨床成績を示し、二次治療以降の標準治療を塗り替えました。近年では、HER2 lowや他腫瘍種への拡大も進み、「HER2=免疫染色3+だけではない」という概念変化も生んでいます。
第二のDXd ADCであるDatroway(dato-DXd)はTROP2を標的とし、TNBCやHR陽性乳がんなど、予後不良で選択肢の限られていたサブタイプに対して新たな治療オプションを提示しました。DXd系ペイロードに共通する課題である間質性肺疾患(ILD)リスクは依然として注意が必要なものの、「強力なバイスタンダー効果と許容可能な安全性のバランス」が臨床的メリットと認識されつつあります。
こうしたDaiichi発DXd ADCの成功は、AstraZenecaにとって「自社でも同様のプラットフォームを構築する」方向性を後押ししました。その延長線上にあるのが、次に取り上げる社内ADC群です。
社内ADCプラットフォームの中核:AZD5335とAZD8205
AstraZenecaは、近年のESMO等の学会で、自社開発のADCとしてFRα標的のAZD5335とB7-H4標的のAZD8205のデータを相次いで公開しました。いずれもTopoisomerase Iペイロードと独自リンカーを用いた設計であり、「Enhertu/Datrowayで学んだ教訓を自社技術に落とし込んだ」第二世代プラットフォームと位置づけられています。
特に注目されたのが、プラチナ製剤抵抗性卵巣がん患者を対象としたAZD5335の成績です。フェーズ1/2a試験では、1.6〜2.4 mg/kgの用量レンジ全体で約50%前後の奏効率と、7〜8か月程度の無増悪生存が示され、「既存のFRα標的ADC(例:Elahere)に対しても競争力のある成績」として高い評価を得ました。また、高FRα発現のみならず、低発現集団でも一定の抗腫瘍効果が見られた点は、適応拡大の余地を示唆しています。
B7-H4標的のAZD8205は、婦人科腫瘍や乳がんなど複数のソリッド腫瘍において開発が進行しています。B7-H4は免疫チェックポイント様の機能を持つ分子であり、腫瘍免疫微小環境との相互作用も含めた「ADC+免疫」の新しい組み合わせの基盤になり得る標的です。AstraZenecaは、これら社内ADC群を「自社リンカー・ペイロード技術の検証の場」と位置づけ、将来的なパイプライン拡張の起点として活用しています。
放射性医薬への拡張:Fusion買収とPSMA/EGRF-cMETラジオコンジュゲート
AstraZenecaは、ADCと並行して放射性医薬(radioconjugates)にも大きく踏み込んでいます。その象徴が、Radiopharma企業Fusion Pharmaceuticalsの買収です。この買収により、PSMA標的の放射線コンジュゲートFPI-2265や、EGFR–cMET二重標的の放射性リガンドなどを含むパイプライン、ならびに放射性同位体化学・製造拠点を手中に収めました。
放射性医薬は、ADCと同様に「抗体/リガンド+ペイロード」の設計論で語ることができますが、ペイロードが化学薬剤ではなく放射線源である点が最大の違いです。AstraZenecaは、ADCで培った標的選択性・リンカー設計の知見を、放射性医薬にも水平展開することで、「分子標的+局所放射線照射」という治療の新しい軸を作ろうとしています。
バイスペシフィック抗体・T細胞エンゲイジャー戦略
AstraZenecaのオンコロジーポートフォリオでは、ADC/放射性医薬だけでなく、バイスペシフィック抗体やT細胞エンゲイジャーも重要な柱です。例えば、PD-1/TIGIT二重阻害抗体であるrilvegostomigや、CTLA-4/PD-L1バイスペシフィックであるvolrustomigなど、免疫チェックポイントを複合的に制御する分子が開発されています。
T細胞エンゲイジャー領域では、CD19/CD3に続いてCD20を標的とするT細胞エンゲイジャーへと展開しており、「conditional activation」や「masking」技術を用いることで、腫瘍局所でのみT細胞を強く活性化させる設計を追求しています。これは、ADCにおけるバイスタンダー効果と同様、「効果を最大化しつつオフターゲット毒性を抑える」という共通の設計哲学の延長線上にあります。
細胞治療ロードマップ:自家から同種・in vivoへ
細胞治療(Cell Therapy)についても、AstraZenecaは自家CAR-Tに加えて、同種(allogeneic)およびin vivo細胞治療へと投資を広げています。Gracell買収によりBCMA×CD19デュアル標的CAR-Tを獲得し、さらにEsoBiotec買収によって「体内で直接細胞を改変する」in vivo細胞治療技術にアクセスしました。
興味深いのは、同じ時期に他の大手企業(Takeda, Pfizer, Rocheなど)が遺伝子・細胞治療パイプラインを縮小・整理しているのに対し、AstraZenecaはむしろコミットメントを強めている点です。これは、「ADC/放射性医薬/バイスペシフィック/細胞治療を、がん治療プラットフォームとして統合する」という長期ビジョンに基づいた動きと解釈できます。
他社戦略との比較:単発アセットか、プラットフォームか
MerckはDaiichiとの大型DXdディールを通じて、Keytruda以降の収益源としてADCを中核に据えています。一方でBMSは免疫チェックポイント+CELMoDなど、Rocheは抗体+細胞治療・再生医療といった枠組みで、それぞれ自社の強みを活かしたポートフォリオを構築しています。
その中でAstraZenecaの特徴は、「特定モダリティに依存せず、標的と生物学に対して最適な『運搬手段(ペイロード+フォーマット)を選ぶ』」という意思決定を、かなり早い段階から打ち出している点です。ADCも放射性医薬も細胞治療も、あくまで「標的と患者に合わせて選ぶツール」であり、それらを束ねるのは、標的のライブラリと独自リンカー・ペイロード技術だという世界観です。
この発想は、単発のM&Aやライセンス取得でアセットを積み上げる戦略とは異なり、「治療体系全体を設計するプレイヤー」としてのポジションを志向しているように見えます。
まとめ:AstraZenecaの“ポストEnhertu時代”が意味するもの
Enhertu/Datrowayの成功を足場に、AstraZenecaは自社ADCプラットフォーム・放射性医薬・バイスペシフィック・細胞治療までを統合したオンコロジー戦略に踏み出しています。その狙いは、個々の薬剤でライバルに勝つことにとどまらず、「化学療法や従来の単剤免疫療法を、複数モダリティを組み合わせた新しい治療体系で置き換えていく」ところにあります。
2028〜2035年の間にKeytrudaや多くのバイオ医薬品が特許切れを迎える中で、各社は「次の10年」を支える収益ピラーを模索しています。AstraZenecaのアプローチは、ADCをその中心に据えつつも、放射性医薬・細胞治療といった周辺モダリティを早い段階から巻き込むことで、治療選択肢の厚みと柔軟性を手に入れようとしている点に特徴があります。
日本の製薬企業やバイオベンチャーにとっては、個々のモダリティの勝敗にこだわるだけでなく、「どの標的・患者集団に、どのフォーマットを組み合わせるか」を俯瞰的に設計できるかどうかが、今後の国際競争力を左右する一つの尺度になっていくと考えられます。
私の考察
AstraZenecaの戦略を俯瞰して感じるのは、「ADC企業」ではなく「オンコロジー・プラットフォーム企業」を目指しているという明確な意思です。EnhertuとDatrowayは確かに強力な成功事例ですが、同社はそこで立ち止まらず、自社リンカー・ペイロード技術、標的ライブラリ、放射性医薬、細胞治療までを含めた長期ポートフォリオに投資しています。これは、単一モダリティのピークを避け、科学技術の進歩に合わせて治療の“組み合わせ”を柔軟に変えていくための布石と解釈できます。一方で、日本のプレイヤーが同じ発想をそのまま真似る必要はありません。むしろ、自前で全モダリティを抱えることは現実的でないからこそ、「標的・疾患・強みのある技術」を明確に絞り込み、AstraZenecaのようなグローバルプレイヤーと補完的な関係を築ける領域を見極めることが重要です。ADCや放射性医薬の一部工程、あるいは特定標的に特化した創薬基盤など、日本発で世界に提供できる“尖ったモジュール”を育てていくことが、結果としてグローバルな治療体系の一部を担う近道になると考えています。
本記事は、Morningglorysciencesチームによって編集されています。
関連記事



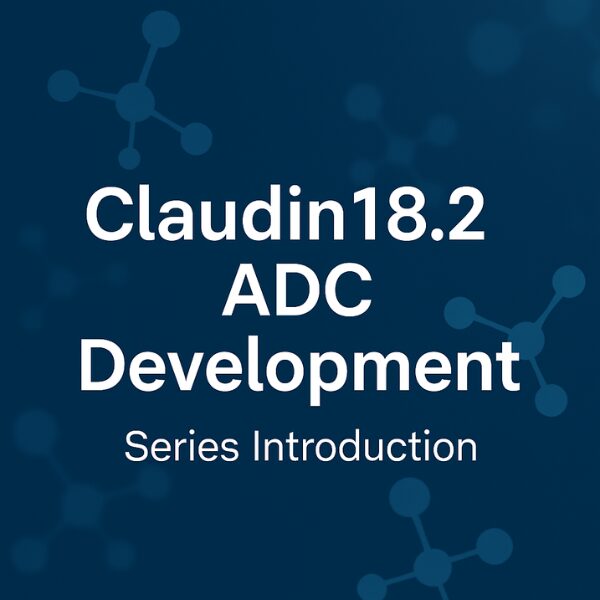







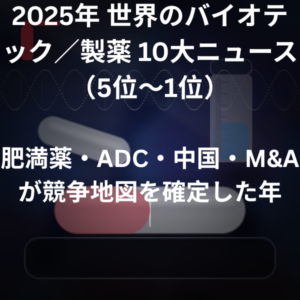
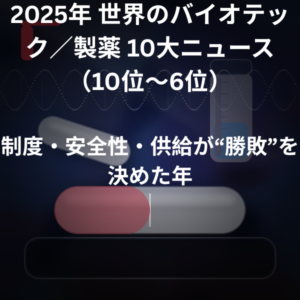

コメント