抗体薬物複合体(ADC)は、がん治療の中でも近年最も注目を集める分野のひとつです。本シリーズでは、ADCの構造から作用機序、細胞内での挙動まで段階的に解説してきましたが、今回は「おまけ」として、近年のブレークスルー事例と最新の開発競争について深堀りしていきます。
エンハーツが切り拓いた新しい地平
2020年代初頭、ADCの中でもひときわ注目された製品が、第一三共とアストラゼネカが共同開発したエンハーツ(Enhertu:trastuzumab deruxtecan)です。HER2陽性乳がんに対する治療薬として、2019年末に米国で承認を受けて以降、その驚異的な治療効果と、さまざまな固形がんへの応用可能性により、ADC市場の成長を牽引してきました。
エンハーツの革新性は、以下の3点に集約されます:
- 高Drug-to-Antibody Ratio(DAR): payload数が平均8と高く、従来よりも強力な殺細胞効果を実現。
- 安定かつ効果的なリンカー設計: 腫瘍内での切断に最適化されたペプチド型リンカーを採用し、正常組織での早期放出を防止。
- バイスタンダー効果: payloadが細胞膜を通過して周囲のHER2低発現細胞にも拡散し、治療範囲を広げる。
この成果により、「HER2低発現がん」など、従来の抗HER2療法では対象とされなかった症例にも適応拡大が進み、ADCの可能性を大きく拡張することとなりました。
激化するADC開発競争(2023〜2025)
エンハーツの成功を受けて、ADC開発の熱は一気に高まり、2023年以降、グローバル各社による開発・買収が加速しています。特に注目すべきは以下の動きです:
1. 大型M&Aとライセンス契約の続出
- ファイザー(Pfizer)によるSeagenの買収(2023年):約430億ドル規模のメガディール。
- アストラゼネカは、中国のHarbour BioMedやDaiichi Sankyoとの提携を拡大中。
- エーザイや武田薬品も、次世代リンカー技術や新規ターゲットを持つバイオテックとの戦略的連携を模索。
2. 次世代Payload・リンカーの研究開発
- Topoisomerase I阻害薬(エンハーツ型)から、微小管阻害薬、免疫刺激性Payloadへの多様化。
- pH感受性・酵素分解型・還元環境対応型など、放出条件を制御するリンカー技術が多層的に展開。
3. 新しいターゲットの探索
- TROP2(DS-1062)、CEACAM5、HER3などの「難しいがん」に対する戦略的ターゲティング。
- がん幹細胞、腫瘍微小環境を標的とした新しい抗体技術との融合。
日本企業のポジショニングと挑戦
第一三共のエンハーツは、日本発のADCがグローバルスタンダードとなった好例です。一方、他の日本企業もこの潮流に乗るべく、以下のような動きを見せています:
- 中外製薬:独自のSMART-ADC技術を進化させ、グローバル開発パートナーを模索。
- エーザイ:アクティブなバイオベンチャーとの連携に加え、自社ADCパイプラインの強化に注力。
- 大日本住友:ADC CMO事業や製造技術への投資を進め、川上・川下の統合戦略を展開中。
今後のADC開発のカギは?
今後、ADC競争における勝敗を分けるポイントは以下の3点と考えられます:
- 適切な患者層の特定とバイオマーカー戦略:Precision medicineとの連携。
- 製造・品質管理の最適化:DARの均一化、スケーラビリティの確保。
- 免疫チェックポイント阻害剤やT細胞療法との併用戦略:シナジー効果の創出。
これらの条件を満たすには、バイオテックと製薬企業の高度なコラボレーションが不可欠であり、今後もアライアンスとM&Aは続くと予想されます。
次回予告:In vivo CAR-T技術の時代へ
本シリーズではADCを取り上げてきましたが、次回からは「In vivo CAR-T細胞療法」の入門シリーズを開始します。これまでのex vivo(体外)型とは異なり、体内でCAR-T細胞を直接生成する技術が注目されています。低コスト化、製造簡素化、患者アクセス改善という観点から、新たなブレークスルーとして世界中のバイオベンチャーが研究を加速しています。
次回はその概要と、どのような企業や技術がこの分野を牽引しているのかを丁寧に解説しますので、ぜひご期待ください。
—
Morningglorysciences公式サイト では、最新のがん治療とバイオテック技術に関する解説を継続更新中です。





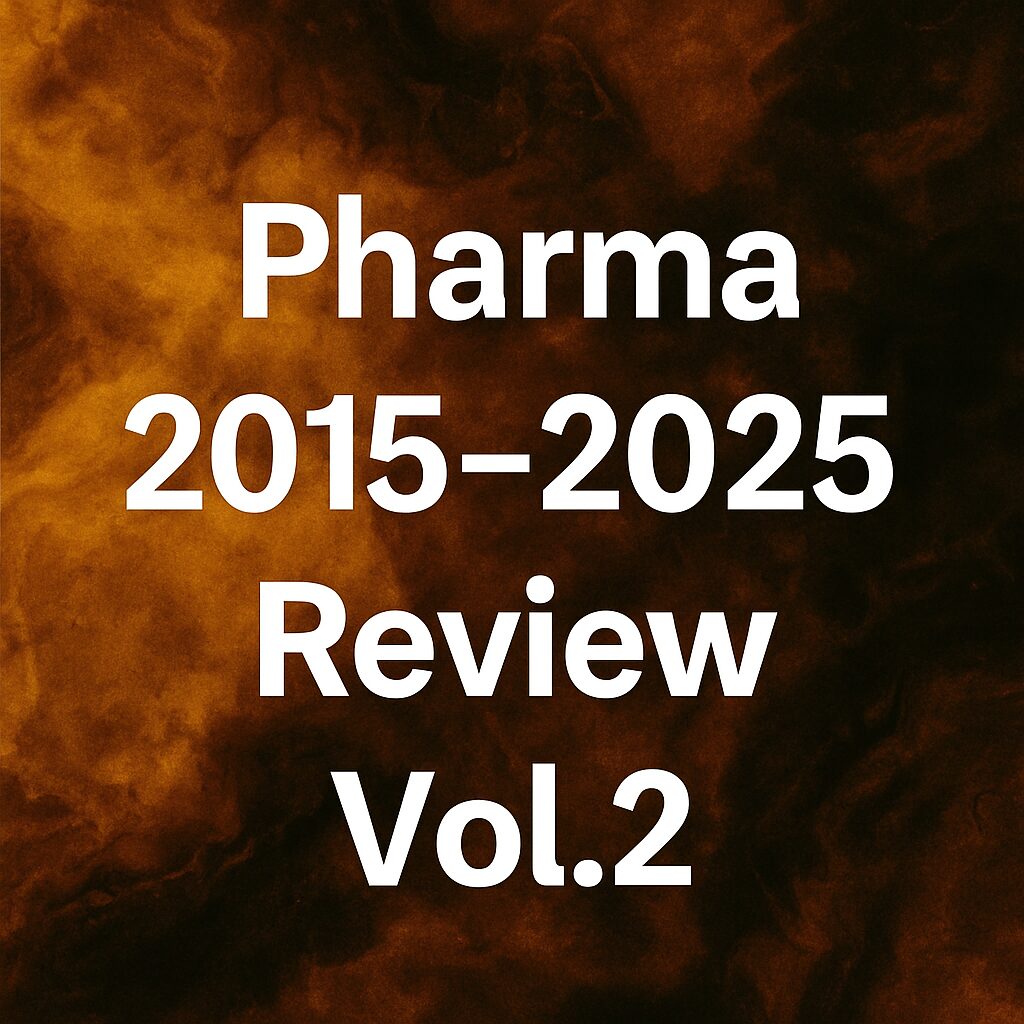


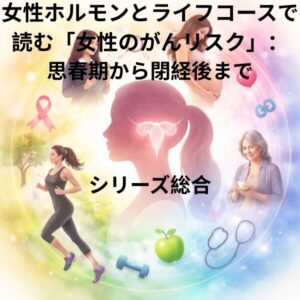
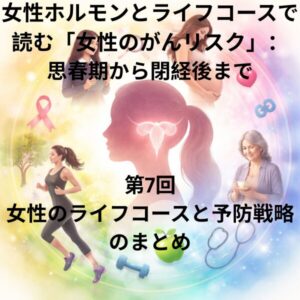
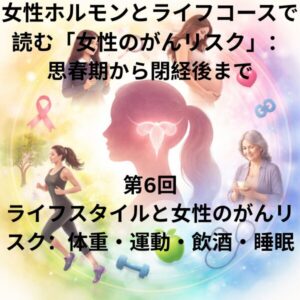
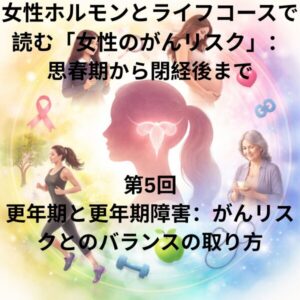
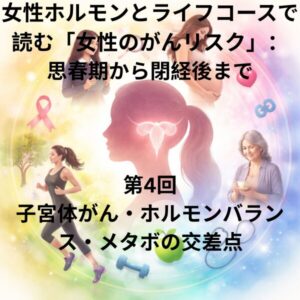
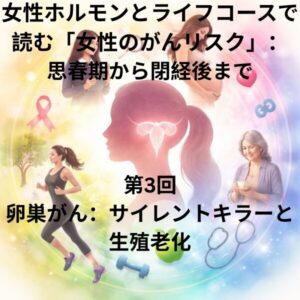
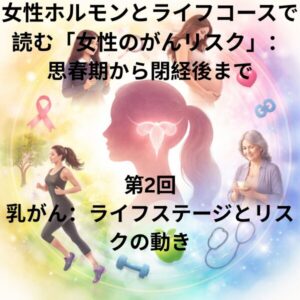
コメント