同じ「二重特異抗体薬」であっても、その構造様式(モダリティ)により、体内での安定性や分布、作用の仕方が大きく異なります。本記事では、IgG型・非IgG型・融合タンパク質型などのモダリティの違いによって生じる薬理特性の違いを、初心者にもわかりやすく解説します。
1. モダリティとは何か?
「モダリティ」とは、抗体医薬の構造的な形式を指す用語であり、抗体そのものの形状や結合部位の設計、さらには補助タンパク質の有無などを含みます。二重特異抗体では、ターゲット結合部位を2種類持つだけでなく、その配置や構造形式がさまざまな薬理特性に影響を与えます。
2. IgG型モダリティの薬理特性
- 安定性: Fc領域を持つことで体内半減期が長くなる
- 分布: 血中滞留性が高く、組織への浸透は比較的遅い
- 機能: ADCCやCDCなど免疫エフェクター機能を保持可能
代表例:GenentechのGlofitamab、RocheのFaricimab など
3. 非IgG型(二量体、断片型など)の薬理特性
- 安定性: 小型構造ゆえに分解・排泄が早く半減期が短い
- 分布: 組織への浸透性が高く、固形がんなどで有利
- 機能: Fc領域がないため免疫活性化機能は基本的に無し
代表例:AmgenのBlinatumomab(BiTE技術)など
4. 融合タンパク質型(IgGベース+他構造融合)
- 安定性: 構造が大きくなるため安定性にバラツキが出やすい
- 分布: 特定部位への指向性を強化する設計が可能
- 機能: Fcを利用した標準的な活性+融合タンパクの機能追加
代表例:JanssenのTeclistamab、ZymeworksのZW49など
5. 各モダリティにおける薬理特性比較まとめ
| モダリティ | 安定性 | 分布性 | 免疫活性 | 代表例 |
|---|---|---|---|---|
| IgG型 | ◎ | ○ | あり | Glofitamab, Faricimab |
| 非IgG型 | △ | ◎ | なし | Blinatumomab |
| 融合タンパク型 | ○ | ○〜◎ | あり(+α) | Teclistamab, ZW49 |
6. モダリティ選択が与える開発戦略への影響
ターゲットとする疾患(血液がん・固形がん)、投与ルート(静脈内、皮下など)、治療環境(外来/入院)によって、適切なモダリティは異なります。たとえば、短時間作用を狙うBiTEは一部で持続注入が必要となり、製剤開発に工夫が求められます。
7. 今後注目される新規モダリティとその応用
近年では、Tri-specificやTandem構造など、さらに進化した構造設計が登場しています。また、抗体以外のモダリティ(例:抗体-ペプチド融合体や抗体-RNA複合体など)も登場しており、モダリティの選択は創薬戦略の重要な鍵となりつつあります。
まとめ
二重特異抗体薬において、モダリティの違いは薬理特性だけでなく、投与方法、製剤設計、開発コストにも影響を及ぼします。今後の開発では、疾患に応じた最適なモダリティの選択が成功の鍵となるでしょう。
🔗 関連記事・シリーズリンク
- 治療薬トレンド2025年:何が注目されているのか?
- 初心者向け入門シリーズ 記事一覧
- やせ薬って何?話題の肥満治療薬をゼロからやさしく解説
- 抗体って何?がんを狙い撃つ夢の治療薬「ADC」の誕生前夜
- In vivo CART シリーズ
- 【第1回】CAR-Tとは何か?エミリーの奇跡
- 【第2回】技術の核心:ナノ粒子・ベクター・mRNA
- 【第3回】がんだけを狙うために:標的抗原の選定と特異性
- 【第4回】CAR構造を深掘り:共刺激とシグナル伝達の最前線計
- 【第5回】臨床試験の最前線と注目企業:開発競争の現在地
- 【第6回】in vivo型CAR-Tの課題を解決する技術と今後の展望
- 【第7回】in vivo CAR-Tの未来を担うキーパーソンたち
- 【第8回】グローバル戦略から読み解く in vivo CAR-T開発の未来
- バイスペシフィック シリーズ
- 【第1回】二重特異抗体薬とは何か?基礎から徹底解説
- 【第2回】構造設計の比較と治療効果への影響
- 【第3回】標的の選び方に関する戦略的考察
この記事はMorningglorysciences編集部によって制作されました。


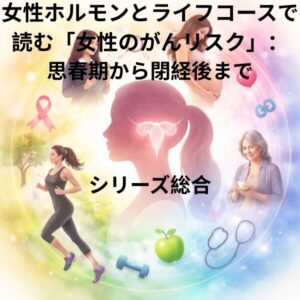
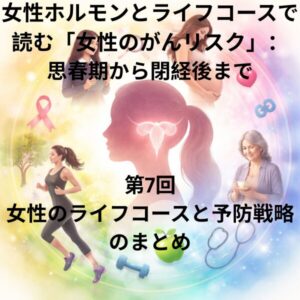
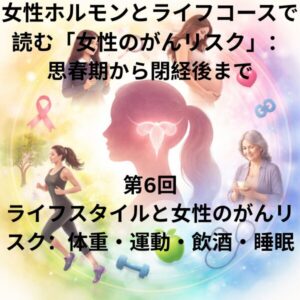
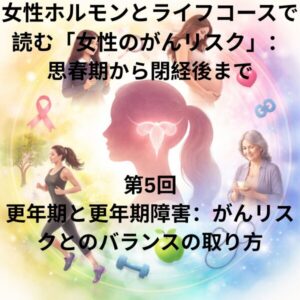
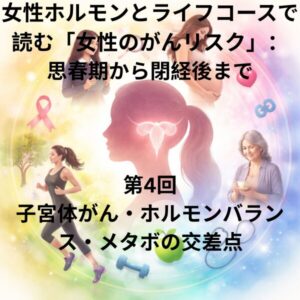
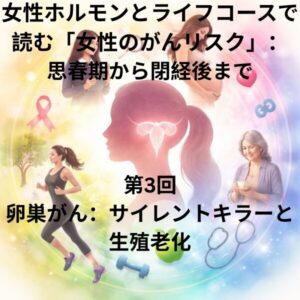
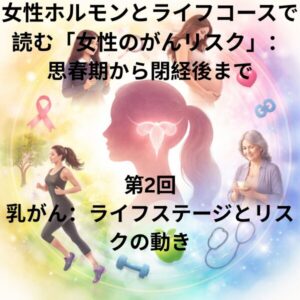
コメント