これまでの特集では、CAR-Tの基本、in vivo型の特徴、遺伝子導入法や標的抗原、そしてシグナル設計について解説してきました。第5回では、実際に現在進行中の臨床試験と、その先頭を走る注目企業たちに焦点を当てます。科学だけでなく、どの企業が次世代医療を実現しようとしているのか——その「今」をわかりやすく紹介します。
目次
- 1. in vivo CAR-Tの臨床試験が始まった
- 2. 主要プレイヤー紹介:Capstan、Intellia、Umojaなど
- 3. 技術アプローチの違いと治療領域
- 4. 今後の課題と未来予測
- 5. まとめと次回予告
1. in vivo CAR-Tの臨床試験が始まった
かつて「夢の治療法」とされたCAR-T細胞療法は、血液がんに対していくつもの承認薬が登場し、実用化の段階に入りました。一方、体外操作を必要とするex vivo型にはコストや時間、施設面での課題が残っており、体内で直接CAR-Tを“つくる”in vivo型への期待が高まっています。
実際、2023年から2024年にかけて、米国を中心に複数のin vivo CAR-Tを使ったヒト臨床試験が始動しました。これは、科学的な原理の証明(proof of concept)から、いよいよ実践的な安全性・有効性の確認段階へ移行したことを意味します。
2. 主要プレイヤー紹介:Capstan、Intellia、Umojaなど
ここでは、現在注目されているin vivo CAR-T開発企業を簡単に紹介します。
● Capstan Therapeutics
カプスタンは、脂質ナノ粒子(LNP)を用いてmRNAを体内のT細胞に導入する技術を武器とし、CAR-Tのin vivo化に取り組んでいます。2023年にFDAからIND(治験開始届出)承認を取得し、世界初のヒト試験に突入しました。ターゲットはCD19陽性のB細胞性白血病・リンパ腫です。
● Intellia Therapeutics
CRISPR技術で知られるIntelliaも、in vivo型の遺伝子編集CAR-Tを開発しています。自社のLNPプラットフォームを用い、体内でT細胞に編集を加えるアプローチを採っています。血液がんだけでなく、将来的には自己免疫疾患への応用も視野に入れています。
● Umoja Biopharma
Umojaは「VivoVec™」というウイルスベクター技術をベースに、体内でのCAR導入を目指しています。同社はまた、CAR-Tの持続性や安全性を高めるために、自己調整型の共刺激設計も開発しており、他社との差別化を図っています。
● その他の注目企業
- Vector BioPharma:組織特異的プロモーターを活用したin vivo導入型CAR-T
- Sana Biotechnology:体内編集によるT細胞再プログラミング技術
- Verve Therapeutics:エピゲノム制御CAR-Tの概念検証
3. 技術アプローチの違いと治療領域
各社のアプローチは大きく分けて次の2つです:
- ① LNPベースのmRNA導入:非ウイルスで比較的安全性が高く、製造が容易。CapstanやIntelliaが代表例。
- ② ウイルスベクター型:組織特異性や効率性に優れるが、免疫応答や挿入変異のリスクもあり。UmojaやVectorがこの方式。
また、対象となる疾患も各社で異なります。B細胞性白血病やリンパ腫が依然として主戦場ですが、骨髄腫、AML(急性骨髄性白血病)、さらに今後は固形がんへの展開も模索されています。
4. 今後の課題と未来予測
in vivo CAR-Tはまだ黎明期にあり、以下のような課題が残されています:
- ● 体内選択性の確保:CAR遺伝子がT細胞以外に導入されない制御が必要
- ● 長期的な安全性:オフターゲット効果や過剰活性化の懸念
- ● 臨床スケールのデータ不足:現在はまだ初期フェーズの症例が中心
とはいえ、すでに「第一世代の臨床試験」は始まっており、2025年以降はP1/2段階の中間データが次々と発表される見込みです。今後2〜3年で実用化の地平が大きく開ける可能性があります。
5. まとめと次回予告
in vivo CAR-Tは、従来の細胞療法の壁を破る次世代のがん治療として、今まさに臨床の現場へ足を踏み入れつつあります。Capstan、Intellia、Umojaといった企業が先陣を切り、技術的なチャレンジとともに新たな未来を切り拓こうとしています。
次回第6回では、「in vivo型CAR-Tの課題を解決する技術と今後の展望」と題し、細胞選択性や制御性、安全性設計などの最前線を解説していきます。
🔗 関連記事・シリーズリンク
- 治療薬トレンド2025年:何が注目されているのか?
- 初心者向け入門シリーズ 記事一覧
- 【第1回】CAR-Tとは何か?エミリーの奇跡
- 【第2回】技術の核心:ナノ粒子・ベクター・mRNA
- 【第3回】がんだけを狙うために:標的抗原の選定と特異性
- 【第4回】CAR構造を深掘り:共刺激とシグナル伝達の最前線計





この記事はMorningglorysciences編集部によって制作されました。


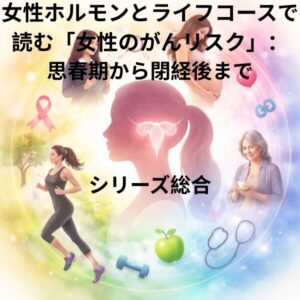
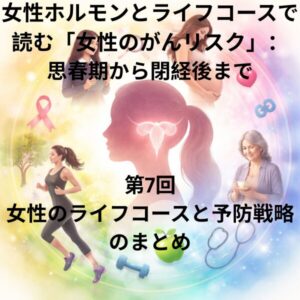
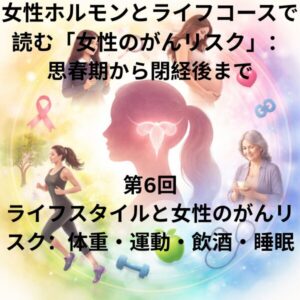
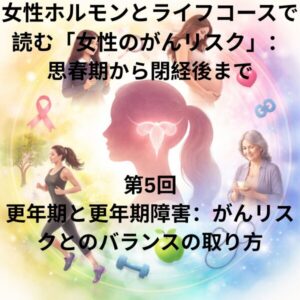
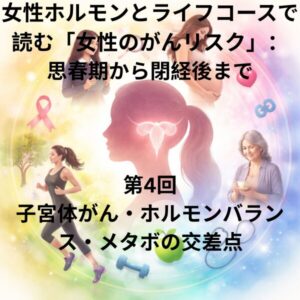
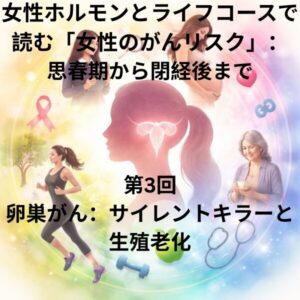
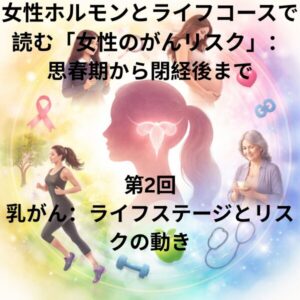
コメント