論文:A fluorescent-protein spin qubit(Nature, 2025年9月4日)
目次
要旨(3行で)
- 遺伝子導入できる蛍光タンパク質(EYFP)が、光で初期化・読み出し・制御できるスピン量子ビットとして実証されました。
- 液体窒素温度で約16 μsのコヒーレンス(CPMG下)と最大20%前後のスピンコントラストを報告。
- 哺乳類細胞でのコヒーレント制御に加え、室温の大腸菌でもODMRを実証(コントラスト最大8%程度)。
なにが新しい?
固体欠陥(NVセンターなど)と異なり、遺伝的にコード化できる蛍光タンパク質を量子ビット化した点が核心です。これにより、標的タンパク質の至近距離(数nm)にセンサーを一対一で配置でき、生体分子スケールの量子センシングが現実味を帯びます。
測定の仕組み(OADFとODMR)
- OADF(励起遅延蛍光)読み出し:近赤外(約912 nm)パルスで三重項サブレベルの占有を整え、続く共鳴マイクロ波で遷移を駆動すると、時間遅延蛍光のコントラストとしてODMRが観測されます。
- 室温ODMR:室温では緩和が速くコントラストが消えやすいものの、912 nmの再励起を組み込むことで再分極させ、室温でもODMRコントラストを取り戻す設計です。
主要結果
- ゼロ磁場分裂:D ≈ (2π)×2.356 GHz、E ≈ (2π)×0.458 GHz。
- コヒーレンス:80 K付近でCPMG下約16 μs。
- 室温センシング:水溶液でODMRを取得し、DC磁場の差分検出を実施。
- 細胞内実証:大腸菌で室温ODMRを観測。時間遅延蛍光によりオートフルオレッセンスの影響を低減。
- 感度の見積り:ACで数 μT·Hz−1/2(80 K)、室温DCで数 mT·Hz−1/2の上限見積り(正規化条件あり)。
どこが効いている?(技術の肝)
- 遺伝子導入で場所指定:融合タンパク質化することで、標的タンパク質の極近傍で直接スピン計測が可能。
- 室温読み出しの工夫:912 nm再励起で再分極—コントラスト消失問題を回避。
- 改良余地:光学取り出し効率・集光・フォトスタビリティの向上で、単一NV級の感度に迫る余地。
応用可能性(著者らの展望)
蛍光タンパク質ベース量子ビットは、EPR的・NMR的測定にも接続可能性があります。酸化還元状態、金属タンパク質の酸化状態、距離制約(DEER)、薬剤結合機構、さらには19F含有薬との相互作用など、生命科学での新しい読み出し軸が期待されます。室温で狭いODMR共鳴を利用した多重化イメージングの可能性も示唆されます。
創薬につながる私の考察(ストーリー)
- 標的近傍の機能計測:EYFP量子ビットを標的タンパク質へ融合し、活性中心の数nm内で酸化状態変化やラジカル中間体、配位状態の違いをODMRコントラストとして読み出す—メカニズムに即したフェノ型評価を実現。
- ドラッグ・ターゲットエンゲージメント(TE)の量子KPI化:19F含有薬やスピンラベル化リガンドと組み合わせ、結合・解離・コンフォメーション変化・滞在時間を周波数/コントラスト/緩和で定量。
- フェノタイプ×量子センシング:ミトコンドリア機能、酸化ストレス、相分離などの細胞現象に、局所Bフィールド・温度・電場の量子指標を重ね、ヒット選別やMoA分解能を向上。
- プロテイン工学で最適化:指向性進化で発光・スピン特性を最適化し、疾患別・指標別の専用量子センサー群を設計。
参考
Feder JS, Soloway BS, Verma S, et al. A fluorescent-protein spin qubit. Nature. 2025;645:73–81.
この記事はMorningglorysciencesチームによって編集されました。

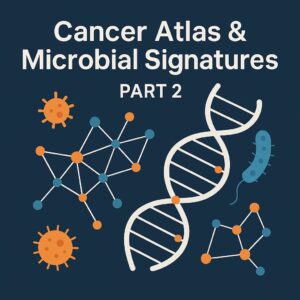
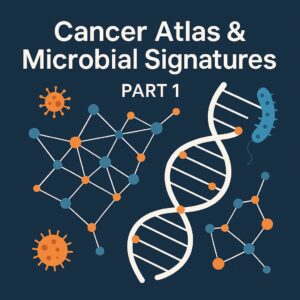
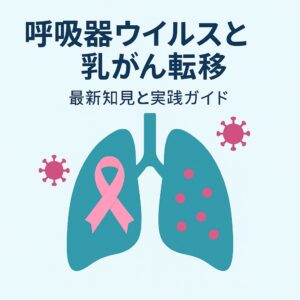
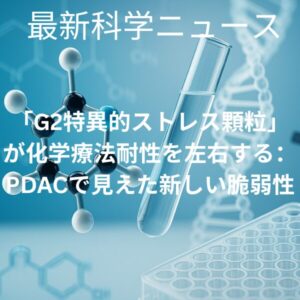

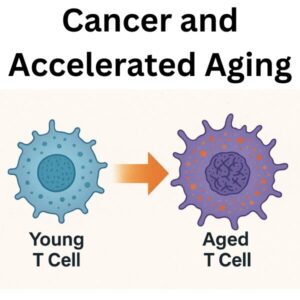


コメント