近年、ベンチャー企業にとって「Exit(資本回収)」は大きな課題です。特にバイオテック業界では、IPO(新規株式公開)やM&A(企業買収)に加えて、SPAC(特別買収目的会社)という仕組みが注目を集めてきました。本記事では、SPACの歴史的経緯、その仕組みと利点・弱点、外部環境の変化による衰退、そして今後のExitの進化について整理します。
SPACの歴史的経緯
SPACは「ブランクチェックカンパニー」とも呼ばれ、1990年代に誕生しました。当初は規模が小さく、主にヘッジファンド投資家の関心に留まっていました。
2010年代には法整備が進み、透明性が改善。シリコンバレーのテック企業やライフサイエンス分野で利用が拡大しました。
そしてパンデミック期の2020〜2021年、コロナ禍による市場過熱でSPACは爆発的に普及。2021年には100社を超えるバイオ関連企業がSPAC経由で上場し、「SPACバブル」と呼ばれる現象が起きました:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
SPACの仕組みと利点・弱点
仕組み
- SPACがまずIPOを行い、信託口座に資金をプール。
- 一定期間内に未公開企業を買収(De-SPAC取引)。
- 対象企業はSPACを通じて実質的に上場し、PIPE投資で追加資金を確保。
利点
- IPOより迅速かつ低コスト。
- PIPEを活用することで大型資金調達が可能。
- バリュエーション交渉に柔軟性がある。
弱点
- 情報開示がIPOより甘く、リスク過小評価につながる。
- スポンサーの「プロモート株」による投資家との利益相反。
- 上場後に事業実績が伴わず株価急落するリスク。
外部環境の変化と衰退
2022年以降、金利上昇と投資家心理の冷え込みにより、成長株中心のSPACは逆風を受けました。SECの規制強化もあり、SPACの「抜け道」的メリットが縮小。さらに、23andMeの破綻やEQRxの吸収合併など失敗事例が多発し、投資家の信頼が揺らぎました。結果としてSPACによる上場件数は激減し、現在は実質的な衰退期に入っています。
成功と失敗の分岐点
SPACで成功した企業と失敗した企業の分岐は鮮明です。
成功例
- Roivant:子会社TelavantをRocheへ7.1Bドルで売却、Dermavantも1.2BドルでM&A成立。
- Cerevel:AbbVieが8.7Bドルで買収し、投資家にリターン。
失敗・縮小例
- 23andMe:2021年には6Bドル評価を得たが、2025年に破産申請。
- EQRx:1.8Bドルを調達も臨床失敗で2023年に吸収合併。
- Immatics/Tango:株価下落で市場評価が大幅縮小。
今後の再復活の兆しとExitの進化
再復活の可能性
- 市場回復期に一部の企業で再利用。
- 業界特化型SPAC(ライフサイエンス、グリーンテックなど)の再評価。
- 米国外(欧州・アジア)での利用拡大。
Exit戦略としての進化
- 「SPAC → 上場 → 短期M&A」という新たなExitモデル。
- IPOの代替というより、M&A前のブリッジファイナンス的役割。
- 流動性確保と早期Exitを重視する資本戦略の一部としての利用。
まとめ:SPACのExit戦略的な位置づけ
SPACは2021年のバブル期に急成長したものの、規制強化や市場環境の悪化により衰退しました。しかし完全に消えるわけではなく、今後は「IPOの代替」から「M&Aを前提とした流動性確保ツール」へと役割を変えて再び利用される可能性があります。
Exitのあり方は進化しており、SPACは新時代のバイオテック資本戦略の一部として再定義されるでしょう。
この記事はMorningglorysciencesチームにより編集されました。
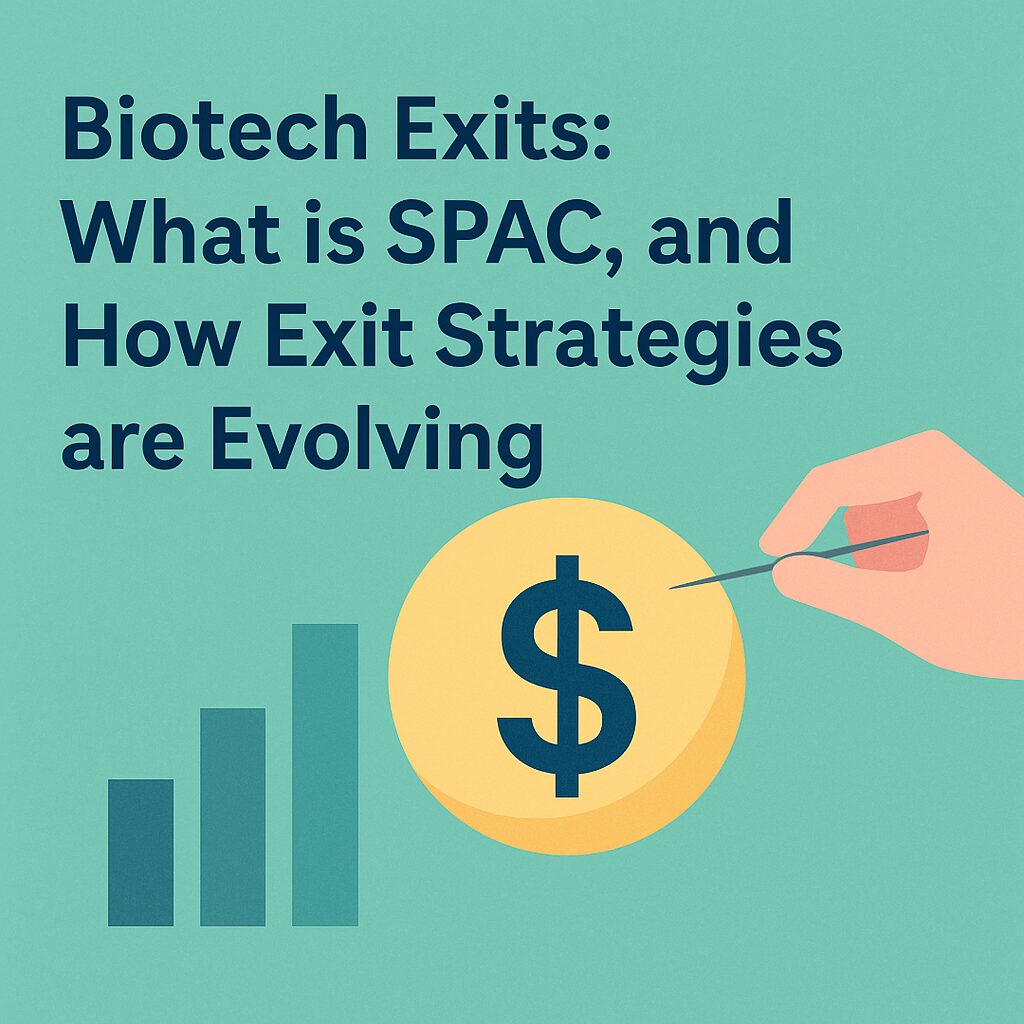
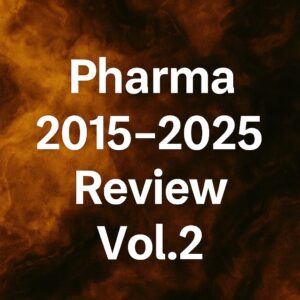
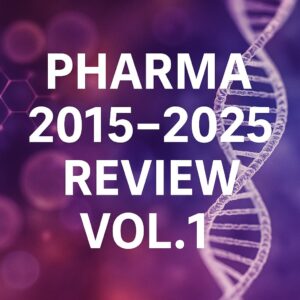

コメント