イントロダクション:老化・がん・免疫という三角関係
第1回では、「がんはなぜ加齢とともに増えるのか?」を歴史的背景とともに俯瞰し、第2回では DNA 損傷、テロメア、エピゲノム、ミトコンドリア、細胞老化(senescence)など、分子・遺伝子レベルのメカニズムから老化とがんのつながりを整理しました。
第3回のテーマは、その上のレイヤーにある「免疫システム」と「腫瘍微小環境(tumor microenvironment, TME)」です。老化は、単にがん細胞側の変異や内的環境を変えるだけでなく、からだ全体の防御ネットワークである免疫システム、そしてがん細胞を取り巻く局所環境にも大きな影響を与えます。
本稿では、
- 免疫監視(immunosurveillance)と免疫編集(immunoediting)
- 免疫老化(immune aging)と炎症性老化(inflammaging)
- 腫瘍微小環境(TME)の構成要素と老化による変化
- 免疫チェックポイント阻害薬と高齢者のがん治療
- 生活習慣(食事・運動・感染症など)が免疫老化に与える影響
といったトピックを、できるだけ平易な言葉で整理していきます。
がんと免疫:免疫監視と免疫編集という考え方
「免疫はがんを監視している」という考え方は、20世紀半ばから提案されてきました。現在では、がんと免疫の関係は大きく「免疫監視」と「免疫編集」という二つの概念で語られます。
免疫監視(immunosurveillance):がんの芽を摘む仕組み
免疫監視とは、免疫システムが日常的に細胞をチェックし、異常な細胞(ウイルス感染細胞や前がん細胞など)を見つけて排除するプロセスです。ここには、
- T細胞(特に CD8 陽性キラー T細胞)
- NK細胞(ナチュラルキラー細胞)
- マクロファージや樹状細胞などの抗原提示細胞
といった多様な免疫細胞が関わっています。がん細胞は、遺伝子変異などにより「非自己(異物)」として認識しうる新しい抗原(ネオアンチゲン)を発現することがあり、本来であればこうした細胞は免疫監視の対象になります。
免疫編集(immunoediting):免疫とがんの“かけ引き”
一方で、がんは免疫の監視を単純に「負けるか勝つか」で終わらせません。現在よく用いられるのが「免疫編集」というフレームワークで、
- 排除期(elimination):免疫が前がん細胞をうまく排除できている段階
- 平衡期(equilibrium):一部のがん細胞が免疫から逃れ、免疫と拮抗しながら共存する段階
- 逃避期(escape):免疫をうまく回避するクローンが選択され、臨床的ながんとして顕在化する段階
という3つのフェーズで説明されます。老化は、この免疫編集のバランスにも強く影響を与えます。免疫側の力が弱ってくると、排除期から平衡期・逃避期への移行が起こりやすくなると考えられます。
免疫老化の基本:造血・リンパ系はどう変わるのか
免疫老化(immune aging / immunosenescence)とは、加齢に伴う免疫システム全体の機能変化を指します。ここでは、骨髄造血、胸腺、末梢リンパ球の変化など、いくつかの代表的なポイントを見ていきます。
造血幹細胞と骨髄の変化
血液細胞は骨髄の造血幹細胞から生まれます。加齢とともに、造血幹細胞の数自体はむしろ増えることがありますが、
- 自己複製能や分化能の質が低下する
- リンパ系よりも骨髄系(ミエロイド系)に偏った分化が起こりやすくなる
- クローン性造血(clonal hematopoiesis)と呼ばれる、一部の遺伝子変異を持つクローンの優占化が起こる
といった変化が見られます。これらは、感染に対する応答性の低下や、白血病・リンパ腫などの血液がんのリスク上昇とも関係していると考えられています。
胸腺退縮と T細胞レパートリーの狭窄
T細胞は胸腺で“教育”を受けて成熟しますが、胸腺は思春期以降急速に縮小(胸腺退縮)していきます。その結果、
- 新生ナイーブ T細胞の産生が低下する
- 代わりに、既に存在しているメモリー T細胞がクローン拡大して数を補う
- 全体として T細胞レパートリーの多様性(多種多様な抗原を認識できる能力)が低下する
といった変化が起こります。これは、新しい病原体や新たながん抗原に対する応答力を弱めるだけでなく、特定のクローンが過剰に増えた偏った免疫状態をつくり出します。
B細胞・抗体応答の変化
加齢に伴い、B細胞の生成や成熟、クラススイッチ、体細胞高頻度変異といったプロセスにも変化が生じます。その結果、
- ワクチンへの応答が若年者に比べて弱くなる
- 新規抗原に対する高親和性抗体の産生が低下する
- 自己抗体の出現頻度が高まる
など、感染症と自己免疫の両面で影響が現れます。がんの文脈では、抗体医薬やCAR-Tなどの免疫療法への応答性や、副作用プロファイルにも関係する可能性があります。
自然免疫(マクロファージ・NK細胞など)の変化
自然免疫系(マクロファージ、好中球、NK細胞など)も老化の影響を受けます。例えば、
- マクロファージの貪食能や遊走能の低下
- NK細胞の細胞傷害活性の変化(数は増えても質が低下する場合がある)
- パターン認識受容体(PRR)シグナルの変化によるサイトカイン産生パターンの変調
などが報告されています。これらの変化は、感染症の重症化リスクを上げるだけでなく、腫瘍細胞の初期排除や腫瘍微小環境の形成にも影響します。
炎症性老化(inflammaging)とは何か
免疫老化と並んで重要な概念が「炎症性老化(inflammaging)」です。これは、加齢に伴って全身で慢性的な軽度炎症状態が維持される現象を指します。
なぜ「静かな炎症」が持続するのか
炎症性老化の背景には、
- 代謝異常(肥満、インスリン抵抗性など)
- 腸内細菌叢の変化(腸内バリア機能の低下や微小なエンドトキシン流出)
- 細胞老化(senescence)に伴う SASP の持続的な分泌
- 慢性的な感染や組織ダメージの蓄積
など、多数の要因が重なっています。血中の IL-6、TNFα、CRP などの炎症マーカーが高めのベースラインを維持するイメージです。
炎症性老化はがんにどう影響するか
慢性的な軽度炎症は、がんの観点から見ると「諸刃の剣」です。
- 炎症サイトカインは、細胞増殖シグナルや血管新生を促進し、腫瘍の成長を助けることがある
- 活性酸素や活性窒素種の産生増加は、DNA損傷やゲノム不安定性を高める
- 一部の炎症シグナルは免疫抑制性細胞(制御性T細胞やMDSCなど)を増やし、腫瘍免疫回避を助長する
一方で、適切に制御された炎症応答はがん細胞の排除にも関与します。この「防御と損傷のバランス」が崩れて、炎症が慢性化・低レベル化した状態が inflammaging であり、多くの加齢関連疾患(心血管疾患、糖尿病、アルツハイマー病など)と同様に、がんリスクの増加にも関わると理解されています。
腫瘍微小環境(TME)における老化の影響
腫瘍は単独で存在しているわけではなく、周囲の血管、線維芽細胞、免疫細胞、細胞外マトリックスなどを含む「腫瘍微小環境(TME)」の中で成長します。老化はこの TME の構成要素にも変化をもたらします。
線維芽細胞・がん随伴線維芽細胞(CAF)の老化
線維芽細胞は、組織の支持構造や細胞外マトリックスの形成に関わる細胞です。加齢とともに線維芽細胞自体が老化し、SASP を含むプロ炎症性・プロ腫瘍性の因子を分泌するようになることがあります。腫瘍内では、がん随伴線維芽細胞(CAF)が、
- 増殖因子やサイトカインを分泌して腫瘍増殖を支援する
- 細胞外マトリックスをリモデリングして浸潤・転移を助ける
- 免疫細胞の浸潤を妨げる物理的・化学的バリアを形成する
といった役割を果たします。老化に伴う CAF の性質変化は、特に高齢者のがんの「硬さ」や「治療抵抗性」と関係する可能性があります。
血管・酸素供給と老化
老化した組織では、血管内皮細胞の機能低下や血管構造の変化により、微小循環が乱れやすくなります。その結果、腫瘍内の酸素・栄養分布が不均一になり、低酸素領域が増えることがあります。低酸素は、
- がん細胞の代謝シフトや幹細胞様性の獲得
- 放射線治療への抵抗性
- 免疫抑制因子の発現増加
などを通じて、がんの悪性度を高める方向に働きます。
腫瘍内免疫細胞の“質”が変わる
老化した免疫系では、腫瘍内に浸潤している免疫細胞の「数」だけでなく「質」も変化します。例えば、
- 疲弊した T細胞(exhausted T cells)が増え、効果的なキラー活性を発揮できない
- 制御性 T細胞(Treg)や MDSC などの免疫抑制細胞が優位になる
- マクロファージが M2 型(組織修復・免疫抑制型)へ偏りやすくなる
といった変化が報告されています。これらは、免疫チェックポイント阻害薬などを用いた免疫療法の効果にも影響する可能性があります。
免疫チェックポイント阻害薬と高齢者がん
近年、PD-1/PD-L1 や CTLA-4 を標的とした免疫チェックポイント阻害薬が数多くのがんで使われるようになりました。老化と免疫療法の関係は、研究・臨床の両面で大きなテーマになりつつあります。
理論的には「高齢者ほど効きにくい」はずだが…?
免疫老化を考えると、「高齢者は T細胞機能が落ちているので、免疫チェックポイント阻害薬も効きにくいのではないか」という直感的な懸念が生じます。しかし実際の臨床試験やリアルワールドデータでは、
- 年齢だけで免疫チェックポイント阻害薬の効果が明らかに低いとは言えない
- 一部のがん種では、高齢者でも若年者に匹敵する、あるいはそれ以上のベネフィットを示すケースもある
といった結果も報告されています。これは、腫瘍側の変異負荷や TME の構成、合併症や併用薬、フレイル(虚弱)状態など、年齢以外の要因が重要であることを示唆しています。
高齢者における安全性と個別化
一方で、高齢者は免疫関連有害事象(irAE)による臓器障害のリスクや、その後の回復力の点で脆弱であることも事実です。したがって、
- 年齢だけで一律に免疫療法を避けるのではなく、機能的な年齢(フレイルの程度、臓器予備能、生活背景)を含めた包括的評価
- 投与スケジュールの調整や、早期の有害事象モニタリングと介入
- 高齢者を十分に含む臨床試験の設計とエビデンス蓄積
が重要になります。老化と免疫療法の関係は、今後の「がん × 老化」研究における大きなフロンティアの一つです。
生活習慣と免疫老化:食事・運動・感染症の影響
免疫老化や炎症性老化は、遺伝や時間経過だけで決まるわけではありません。生活習慣や環境要因も大きな影響を与えます。
食習慣:慢性炎症と代謝の橋渡し
高脂肪・高糖質の食事、過剰なカロリー摂取、アルコールの過飲などは、肥満や脂肪肝、インスリン抵抗性を通じて慢性炎症を促進します。脂肪組織から分泌されるアディポカインや炎症性サイトカインは、inflammaging の一部を構成し、がんのリスクや進行にも影響を与えます。
一方で、地中海食のような野菜・果物・魚・オリーブオイルを多く含む食事パターンは、炎症マーカーの低下や心血管リスクの減少と関連しており、免疫老化やがんリスクにも好ましい影響を持つ可能性が指摘されています。
運動習慣:筋肉・骨・免疫をつなぐハブ
適度な有酸素運動やレジスタンス運動は、
- 体脂肪の減少とインスリン感受性の改善
- 骨格筋からのマイオカイン分泌による抗炎症効果
- 骨髄微小環境やリンパ器官の血流改善
などを通じて、免疫老化や炎症性老化を抑える方向に働くと考えられています。過度のトレーニングは一時的な免疫低下を招くこともありますが、多くの疫学研究で「中等度の継続的な運動」ががん予防や再発抑制と関連していることが示されています。
感染症とワクチン:老化・がんとの三角関係
感染症も、老化とがんの間をつなぐ重要な要素です。例えば、
- ヘリコバクター・ピロリ感染と胃がん
- B型・C型肝炎ウイルスと肝細胞がん
- HPV(ヒトパピローマウイルス)と子宮頸がん・頭頸部がん
などが代表例です。免疫老化が進むと、こうした感染のコントロールが難しくなる一方、ワクチンによる予防や、早期治療による慢性感染の抑制は、がん予防戦略として非常に重要です。高齢者においても、肺炎球菌ワクチンや帯状疱疹ワクチンなどと同様、がん関連感染のワクチン予防が今後さらに重視されていくと考えられます。
まとめ:免疫と微小環境の老化を“見えない背景因子”として意識する
第3回では、老化とがんをつなぐ「免疫」と「腫瘍微小環境」に焦点を当てて整理しました。
- 免疫監視と免疫編集:免疫はがんの芽を摘む一方で、がんは免疫から逃れるクローンを選択し、老化はこのバランスを崩しやすくする。
- 免疫老化:造血幹細胞、胸腺、T・B細胞、自然免疫の機能変化により、新規抗原への応答性が低下し、がんや感染症に対する抵抗性が弱まる。
- 炎症性老化(inflammaging):慢性的な軽度炎症が、DNA損傷、増殖シグナル、免疫抑制などを通じて、がんの発生・進展に有利な環境をつくる。
- 腫瘍微小環境(TME)の老化:線維芽細胞、血管、免疫細胞が老化により変質し、腫瘍の成長・浸潤・免疫回避に影響する。
- 免疫チェックポイント阻害薬と高齢者:年齢だけで効果を一律に判断すべきではなく、機能的な年齢と個別の老化プロファイルを踏まえた治療選択が重要。
- 生活習慣と免疫老化:食事・運動・感染症・ワクチンなどが免疫老化や炎症性老化に影響し、結果としてがんリスクや治療応答性にも関与する。
免疫と腫瘍微小環境の老化は、画像検査や血液検査で直接「見える」ものではありませんが、確実にがんの発生・進行・治療の成否に影響する“見えない背景因子”です。がんゲノムや分子標的だけでなく、「どのような免疫・炎症・微小環境の上でその腫瘍が成り立っているのか」を意識することが、今後ますます重要になっていくと考えられます。
次回(第4回)では、老化とがんの関係を「臓器・組織レベル」で見ていきます。なぜ臓器によって老化のスピードやがんの発生パターンが違うのか、性差や生殖老化(卵巣・精巣機能の低下)ががんにどう影響するのか、といったテーマを取り上げます。
私の考察
免疫老化と腫瘍微小環境の視点を加えると、「老化はがんのリスク要因である」という一文の中に、実は多層的でダイナミックなプロセスが折りたたまれていることが見えてきます。がんは、変異を獲得した細胞だけの問題ではなく、「どのような免疫の網の目をすり抜けたのか」「どのような炎症・線維化・血流の環境に根を下ろしたのか」という、背景との相互作用の結果として立ち現れてきます。
個人的に興味深いのは、免疫老化が単なる「機能低下」ではなく、「再構築」に近い側面を持っている点です。リンパ系から骨髄系へのバイアス、ナイーブ細胞からメモリー細胞へのシフト、慢性的な低レベル炎症などは、長い人生の中で繰り返し遭遇するストレスや感染への「適応」の結果でもあります。その適応が、ある閾値を超えると、今度はがんや動脈硬化、認知症といった加齢関連疾患のリスクを高める方向に働いてしまう。この「適応と破綻の境界線」をどう見極め、どのタイミングで介入するかが、老化医学と腫瘍学の交差点で求められる視点だと感じています。
また、高齢者における免疫チェックポイント阻害薬の使い方は、単に「効く・効かない」ではなく、「誰に」「どのタイミングで」「どの強度で」使うかを考えるフェーズに入っているように思います。時間とともに変化する免疫・炎症・微小環境のプロファイルを、バイオマーカーや画像・デジタル技術でどこまで“見える化”できるかが、今後の重要な研究テーマになるでしょう。
本シリーズ全体を通して、読者の方が「老化」と「がん」、「免疫」と「環境」を切り分けて考えるのではなく、一つの連続したプロセスとして捉え直すための共通基盤を提供できればと思っています。
本記事は、Morningglorysciencesチームによって編集されています。
関連記事 / Related Articles
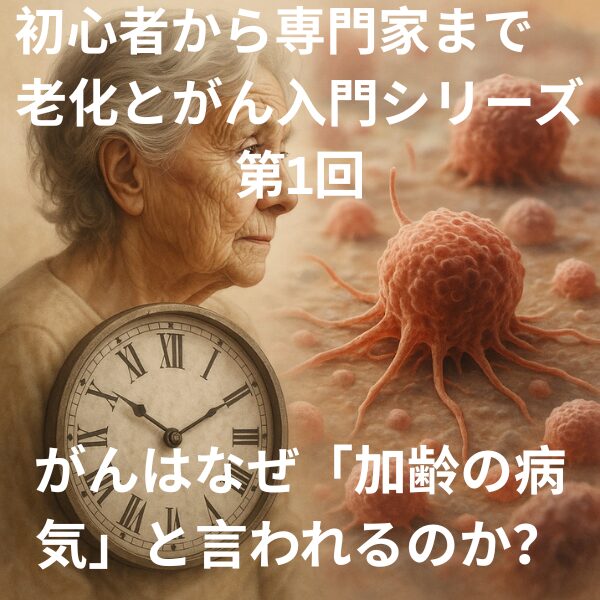

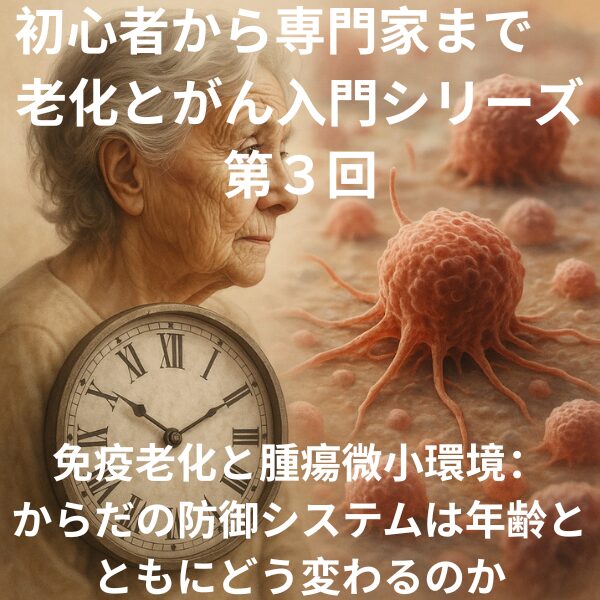
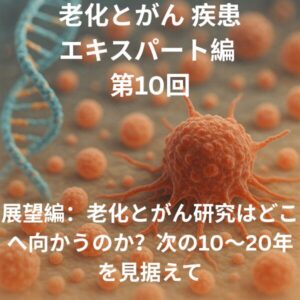
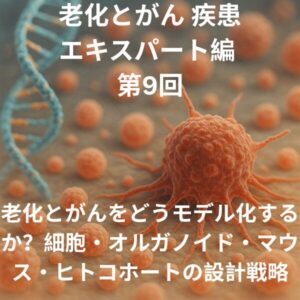

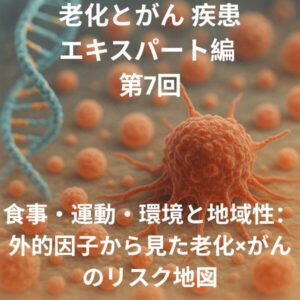


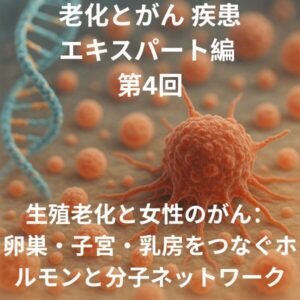

コメント