はじめに
2015〜2025年の10年間、グローバル製薬企業は革新性の高い治療領域への進出と新技術の内製化・導入を進めてきた。本稿では、22社の企業動向をベースに、各社の戦略的買収・提携の動きから、主要テーマ・治療領域・技術トレンドを読み解く。
強化された治療領域とアセットタイプ
■ がん領域(Oncology)
- Merck, BMS, Gilead, AstraZeneca などが主導。
- ADC(抗体薬物複合体)、T細胞エンゲージャー、個別化がん免疫療法に集中。
- 注目Deal:Merck×Seagen(ADC)、BMS×TurningPoint、Gilead×Immunomedics。
■ 免疫・自己免疫疾患(Immunology)
- AbbVie(Allergan買収後の炎症領域強化)、Sanofi、J&Jが主導。
- FcRn、IL-2、腸管免疫、遺伝子制御など新技術の活用。
■ 中枢神経系(CNS)
- Otsuka(CNS特化戦略)、AbbVie(Cerevel買収)、Bayerなど。
- 精神疾患・希少疾患・再生医療・デジタルセラピーへの試みが多い。
■ 代謝・糖尿病・肥満
- Novo Nordisk がGLP-1と肥満領域で圧倒的な成果。
- Eli Lillyも同分野に加えAI創薬活用で参入強化。
mRNAの革新とCOVID-19以降の展開
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的大流行により、2020年から2021年にかけてmRNAワクチンが一躍注目された。
- Pfizer/BioNTech と Moderna が主導し、90%以上の予防効果という予想を超える結果でmRNA技術が実証された。
- 当時の想定では「50%でも有効」とされた中での驚異的な実績が、mRNAを”薬にできる”技術として証明。
- Johnson & Johnson、AstraZenecaなどは非mRNAワクチンを提供したが、最終的にはmRNA型が市場支配。
- この成功により、がんワクチンを含む多くの応用領域でmRNAが製薬戦略の中心に浮上。
Sanofi, GSK, Roche, Bayer, Moderna, Pfizerなどががん免疫、感染症、希少疾患でのmRNA活用を拡大。
免疫チェックポイント阻害薬の進展と限界
- Merck(Keytruda)とBMS(Opdivo + Yervoy)の2強が中心。
- LAG3, TIGIT, TIM3, BTLAなども開発されたが、単剤での効果は限定的。
- 多くの開発がPD-1併用を前提とし、治療軸の最適化が問われている。
第2世代ADCとKRAS阻害薬の進展
- MerckのSeagen買収、Daiichi SankyoのEnhertu、AbbVieのImmunoGen買収などが象徴。
- 第2世代ADCは薬効・安全性でブレイクスルー。
- KRAS標的ではsotorasib(Amgen)、adagrasib(Mirati)に続く進展が期待。
技術トレンド:次世代抗体/CGT/AI創薬/RNA医薬
- 次世代抗体:ADC(Merck, AstraZeneca)、Bispecific(Amgen, Regeneron)
- CGT:Bayer(BlueRock, AskBio)、Novartis(AveXis)
- RNA医薬:siRNA, antisense(Sanofi, Novo)、mRNA(Pfizer, Moderna)
- AI創薬:Sanofi×Exscientia、Lilly×XtalPi など
提携戦略と企業文化の変化
- 大型M&Aの減少、オプション付き共同開発の増加
- スタートアップとの対等なパートナーシップ重視
- プラットフォーム買収から疾患集中型戦略への転換
私のひとこと(所感)
この10年は、がんを中心とした分子標的薬の進化とmRNAの台頭、ADCの再ブームによって、製薬業界に大きな構造転換が起きた時期だったと考えます。今後は、疾患特化型かつモダリティ横断型の設計が企業の差別化要素になると考えています。
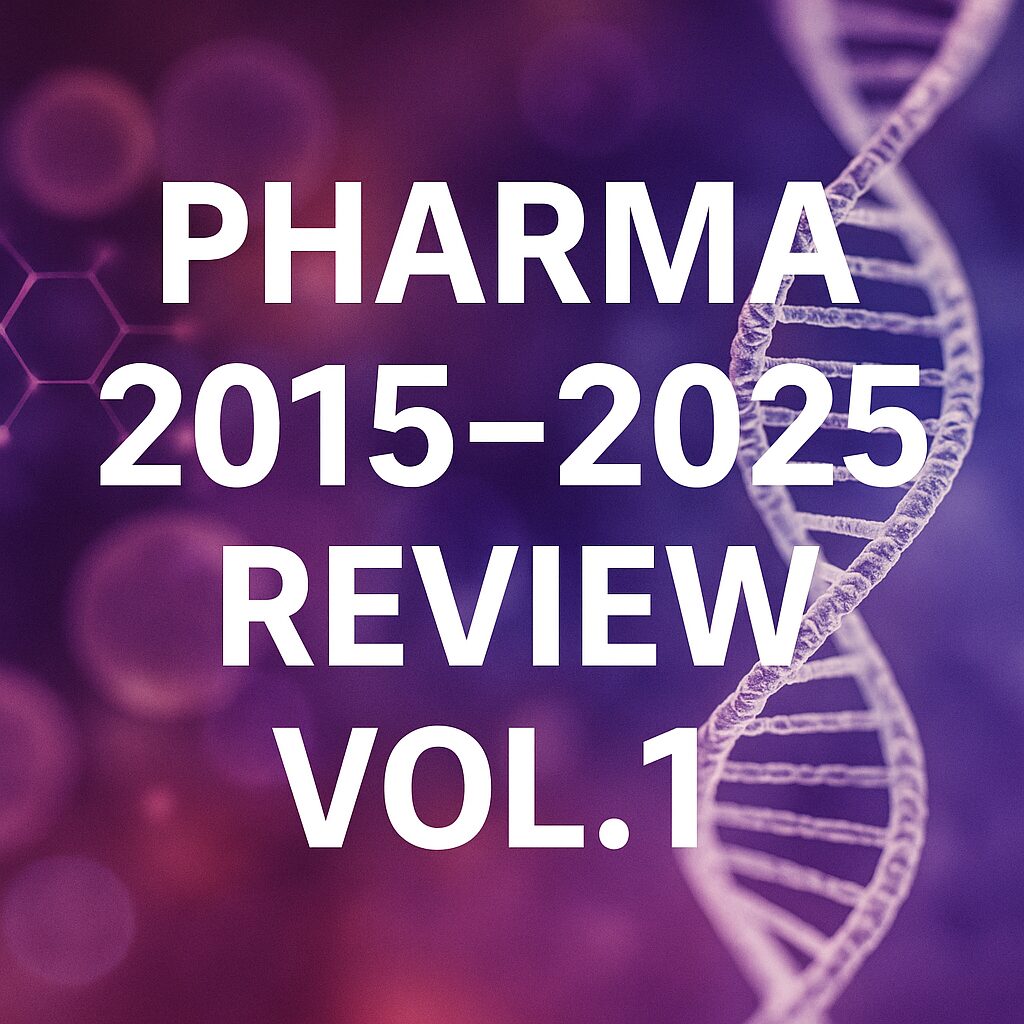

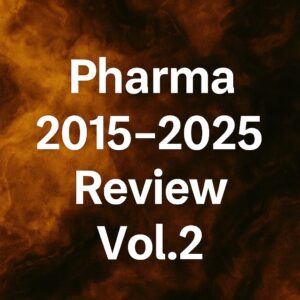

コメント