はじめに
この10年、日本の大手製薬企業もグローバル競争の中で進化を遂げてきた。第一三共、武田薬品、大塚製薬、アステラスといった各社は、それぞれの強みを活かしながら、自社創薬、新規モダリティの導入、海外展開、そしてM&A戦略を通じて競争力の強化を図ってきた。
第一三共:ADCによるグローバル変革
第一三共は、抗体薬物複合体(ADC)「エンハーツ(Enhertu)」の開発・上市を通じて、がん領域におけるゲームチェンジャーとなった。AZ(アストラゼネカ)との提携を皮切りに、Merckとの大型提携も続き、これらは第一三共の技術力をベースとした「共同グローバル展開型ビジネスモデル」の成功例となった。
- エンハーツはHER2低発現乳がんへの適応拡大で“ブロックバスター”化
- 提携スキームにより販路、臨床、薬事を共有しつつ利益を最大化
- ADC分野で後続の複数パイプラインも存在し、長期収益源に
第一三共は「製品売上」ではなく「技術ライセンスと共販型収益」を戦略の軸に据え、製薬ビジネスの新しい道を日本から切り開いた企業といえる。
武田薬品:エンティビオと買収戦略での安定化
武田薬品は2010年代に行ったShireの大型買収により一時的な財務負担が注目されたが、ミレニアム買収により獲得した潰瘍性大腸炎・クローン病薬「エンティビオ(Entyvio)」の成長が同社のグローバル主力製品となり、利益構造を支えた。
- エンティビオは売上100億ドル超の中核製品に成長
- ミレニアムの研究文化が武田のグローバル研究に変化を与えた
- 近年ではNimbusの買収(免疫)など、選択的・戦略的買収も展開中
「疾患集中型」「モダリティ多様化」「グローバル・バイオファーマ化」をバランスよく進めた10年であった。
大塚製薬:神経領域の深化と外部連携の成果
大塚製薬はCNS(中枢神経系)領域における強みを持ちながら、積極的に外部パートナーシップを拡大し、新たな治療法を取り込むことに成功してきた。
- Abilify Maintena(持効性注射剤)など、製品寿命の延長戦略に成功
- 外部提携により希少疾患領域やゲノム編集、幹細胞治療などの新領域にも進出
- CNS偏重のリスクを分散させながら、技術獲得に貪欲な姿勢を継続
今後は既存CNS治療薬の後継パイプラインの育成と、次世代技術導入の両輪が問われる段階にある。
アステラス製薬:戦略的M&Aとその転換点
アステラスはこの10年、積極的にバイオテクノロジー企業の買収に乗り出し、複数の高額案件(IvericBio、Audentesなど)を通じて再生医療・眼科・遺伝子治療に事業展開を広げた。
- Audentes買収による遺伝子治療開発は技術・製造面でのインフラ構築へ貢献
- Iveric買収により眼科領域の強化(地固めと拡張の両立)
- 現在はそれらの買収成果が製品化される「検証フェーズ」に突入
これらの投資の成果が短〜中期的な業績にどこまで結びつくか、投資家の注視が続く。
国際展開と今後の成長市場
日本市場は先進国の中でも人口が限定的で、高薬価政策も逆風となっている。そのため、今後はAPAC(アジア太平洋)、中東・アフリカ、ラテンアメリカといった「グローバルサウス」市場での戦略的展開が鍵となる。
- アステラスはAPAC・ASEAN地域に注力(現地法人強化)
- 第一三共は中南米・中東でも展開強化中
- 武田・大塚は東南アジアでのプレゼンスがすでに高く、今後さらに拡大可能性あり
特に、がん・感染症・免疫などの領域で、グローバルサウスに適応した投与形態・コスト設計・医療体制との親和性が問われる。
私のひとこと(所感)
日本企業はグローバルでの競争に直面しつつも、自社の強みを明確にし、技術と疾患領域を焦点化することで成長の道を切り拓いてきました。第一三共のADC、武田のエンティビオ、大塚のCNS、アステラスの再生医療・遺伝子治療といった象徴的な展開は、もはや「日本発グローバル戦略」と呼べる次元に達しています。今後の課題は、グローバルサウスへの深耕、mRNAやAI創薬といった先端技術への自社展開、そして継続的な価値創出のエコシステムの構築にあると感じています。
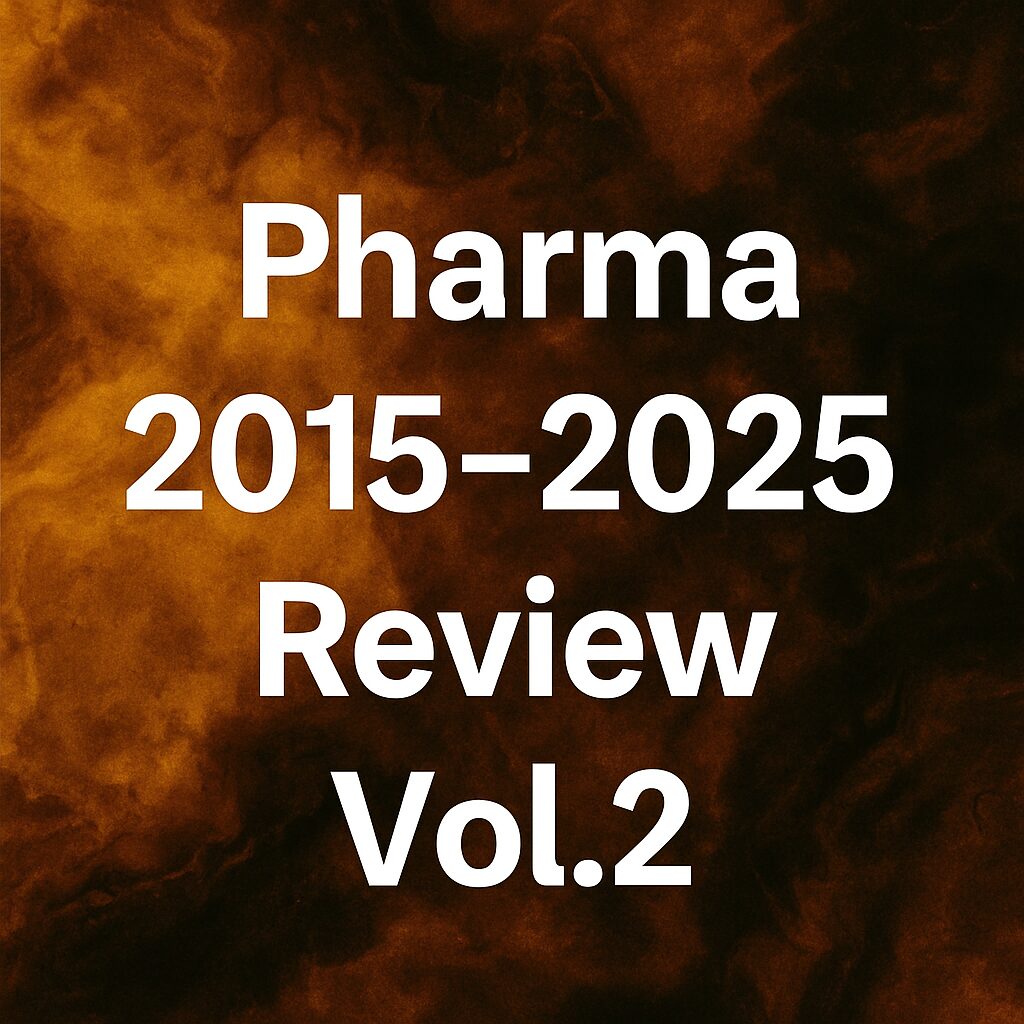

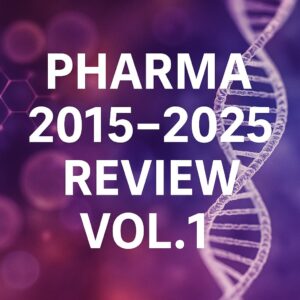

コメント