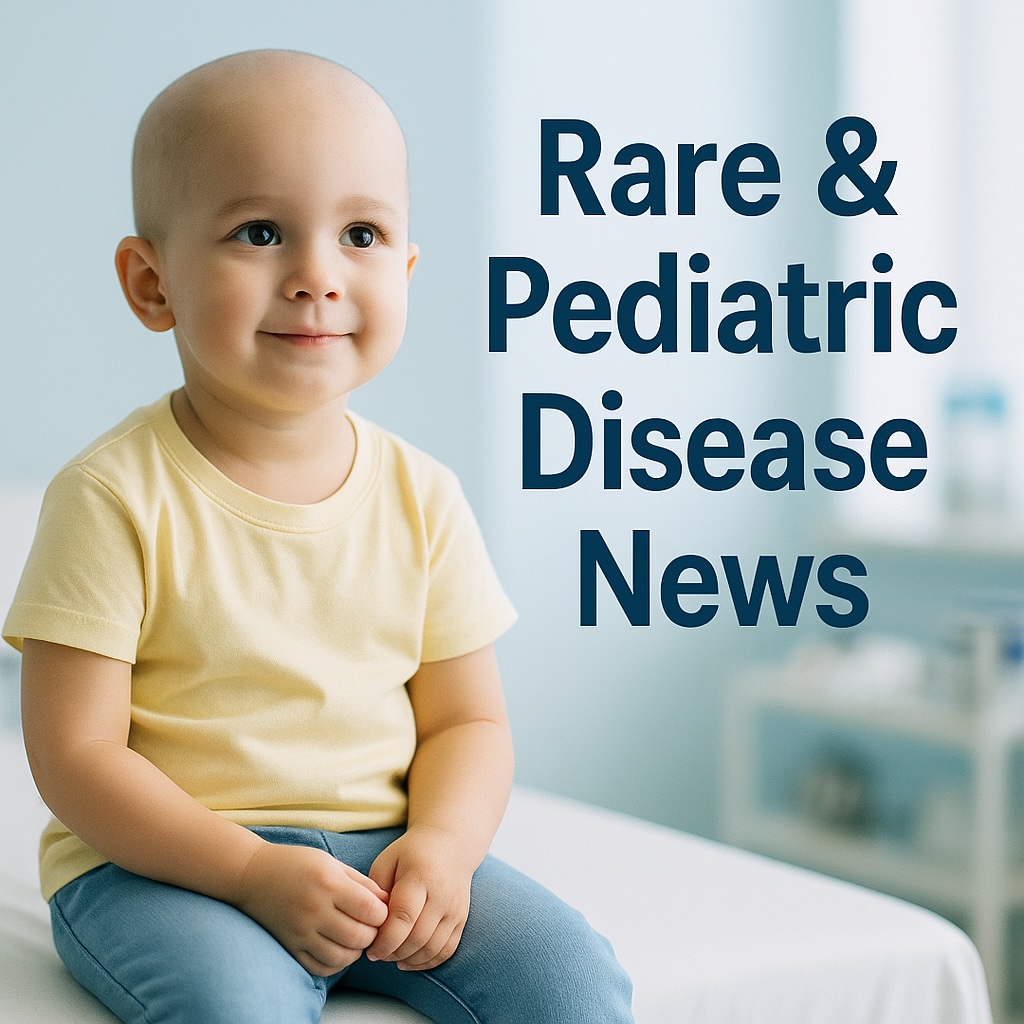– PRV終了後の世界で、グローバルと比較した課題と展望 –
2024年に米国FDAの「小児希少疾患 優先審査バウチャー(PRV)」制度が終了し、世界的に小児希少疾患領域のイノベーションをどう維持するかが議論の的となっています。シリーズ第1回では米国の制度の変化を紹介しましたが、第2回では日本に焦点を当て、国際比較を行いながら今後の戦略的提言をまとめます。
🏛 日本における支援制度
日本では1993年より「希少疾病用医薬品指定制度」が設けられており、対象は患者数が5万人未満の疾患です。指定された医薬品には税制優遇、研究助成、優先審査などのインセンティブがあります。
また、PMDAでは「小児医薬品相談窓口」が設けられており、AMED(日本医療研究開発機構)も小児・希少疾患に関する研究開発を積極的に支援しています。
🇯🇵🇺🇸 日本と米国の比較
- インセンティブの規模: 米国ではPRVが数百億円規模で売買される一方、日本では主に助成金や税制優遇にとどまり、スタートアップの資金調達には限界があります。
- 審査のスピード: 米国の優先審査では承認まで6か月程度に短縮されることもありますが、日本では新しいモダリティに対して審査期間が長期化する傾向があります。
- 治験体制: 米国では国際共同治験が一般的ですが、日本では患者数やネットワーク不足が課題とされています。
🔬 日本でも前向きな動き
こうした課題がある一方で、日本でも着実に進展は見られます。京都大学、慶應義塾大学、国立成育医療研究センターなどのアカデミアが基礎から臨床への橋渡しを担い、JCRファーマやヘリオスといったバイオ企業もグローバル連携を視野に活動を広げています。
🧩 日本に向けた提言
- 日本版PRVの導入など、インセンティブ強化
- 国際共同治験への対応力向上とPMDAのプロセス改善
- 患者団体との協力と、社会的な認知向上
📝 結論
小児希少疾患の治療薬開発は、制度設計以上に「社会的責任」であると言えます。PRVの終了は、次世代に対してどのように責任を果たすかを世界に問いかけています。
日本が世界の流れに追いつき、持続可能な創薬環境を構築するには、制度・資金・共創の3軸での強化が鍵を握っています。