動くGBM――ECM・接着・白質トラクト沿い浸潤を直観で理解
なぜGBMは「取り切っても戻ってくる」のか。“動く”という性質を、ECM(細胞外マトリクス)・接着分子・白質トラクトの観点から入門トーンで解きほぐします。
今回のゴール(3分で把握)
- ECM・接着・細胞骨格が浸潤性を左右する基礎を直観で理解。
- 白質トラクト(神経線維束)に沿った“移動経路”のイメージを持つ。
- 画像(特にDTI)と浸潤の関係をざっくり掴む。
- 抗浸潤×増殖抑制の二面作戦を地図化する。
ECMと接着:細胞が“動ける/動けない”を決める床
ECMは、コラーゲン、ラミニン、テネイシン、プロテオグリカンなどからなる細胞の足場です。細胞はインテグリンなどの受容体を介してECMに“つかまり”、焦点接着やアクチン細胞骨格の再編で前進します。GBMではこの足場の作り替え(リモデリング)が活発で、狭い隙間をすり抜ける形態変化も得意です。
入門キーワード
- インテグリン(接着受容体)
- FAK/ Src(接着シグナル)
- MMP/ADAM(ECM分解)
形を変えて進む
- アメーバ様移動(しなやかに変形)
- メソンジェム様遷移に近い挙動
- 核の変形(核膜の柔軟性)
“動きやすさ”を決める因子
- ECMの硬さ・密度・配向
- 細胞内張力(Rho/ROCK)
- 接着の“つけ外し”の速さ
白質トラクト沿い浸潤:最小抵抗経路を選ぶ
GBMは白質トラクト(神経線維束)の走行に沿って広がりやすい傾向があります。線維束は“行き来の高速道路”のように働き、遠位再発・多発再発の一因になります。
DTI(拡散テンソルMRI)で何が見える?
- 水分子の拡散方向から線維束の推定走行を描く。
- 術前計画で重要線維との距離感を把握。
- 浸潤の“広がりやすい方向”の示唆に役立つことがある。
※DTIは万能ではありません。腫瘍・浮腫で歪むため、ほかの情報と統合して解釈します。
“動き”の仕組みとチェックポイント
① 接着のダイナミクス
- 前方で新規接着を形成、後方で接着解離。
- FAK/Src → Rho/ROCK/MLCの順で牽引力を生む。
② ECMの改変
- MMP/ADAMでECMを部分的に切る。
- テンションや硬さの変化で最小抵抗経路を作る。
③ 形態適応
- 核の“狭窄通過”能力(ラミンなど)。
- アクチン/ミオシンの再編で“絞り出す”。
治療の考え方:抗浸潤 × 増殖抑制の二面作戦
- 足場を変える:接着/ECMシグナル(例:インテグリン、FAK、Rho/ROCK)やECM改変(MMP/ADAM)を抑え、“動き”の経路を狭める。
- 時間を稼ぐ:浸潤速度を落とす間に、増殖抑制(放射線・薬剤)を効かせる。
- 併用前提:可塑性による“逃げ道”を想定し、微小環境(前回)やpre-CC(Part 2)、細胞周期(今後)と組み合わせる。
※具体的な薬剤名はPart 7(開発状況)で俯瞰、バイオマーカーはPart 6で整理します。
図でつかむ(テキスト版:後日SVGに差し替え)
浸潤ルートの地図
- 腫瘍周辺のECMが再構築
- 白質トラクトへ“乗る”
- 遠位へ拡散/多発再発
対策の地図
- 接着/ECMシグナルの抑制
- ECM分解の抑制・足場改変
- 増殖抑制と支持療法の最適化
一旦のまとめ
- GBMはECM・接着・白質トラクトを利用して“動く”。
- DTIは線維束の方向性をつかむヒントになる。
- 抗浸潤 × 増殖抑制を土台に、可塑性を見据えた併用設計が鍵。
私の考え
“取り切れない”原因の多くは、腫瘍が場を選び、形を変え、経路に乗るからです。私は、移動性を鈍らせることと増殖を抑えることを同時に狙い、そこへ微小環境やpre-CC段階の介入を重ねる設計が、少ない手数でも実効性を高める近道だと考えます。次回は可塑性(OPC/AC/MES)を入門トーンで扱います。
Morningglorysciencesチームによって編集されました。
関連記事
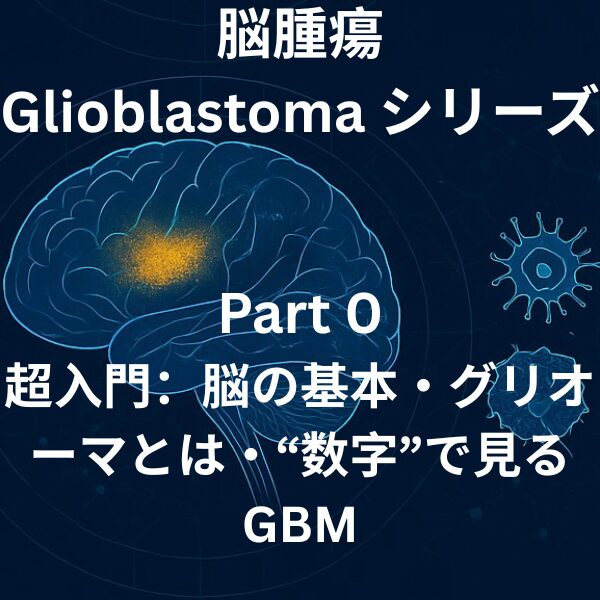
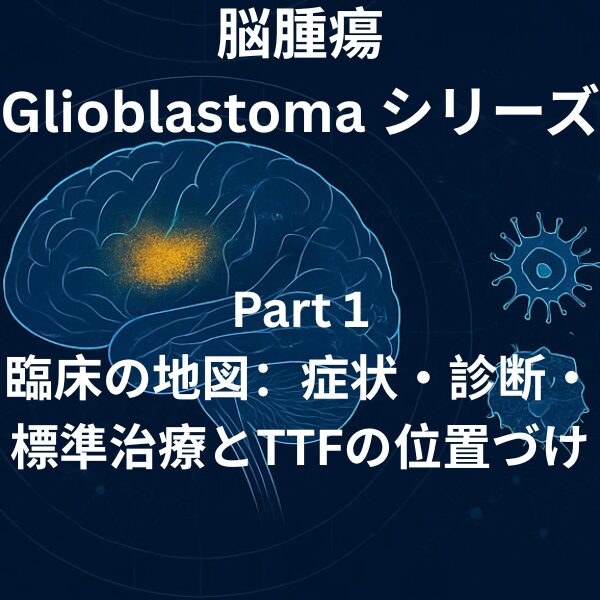
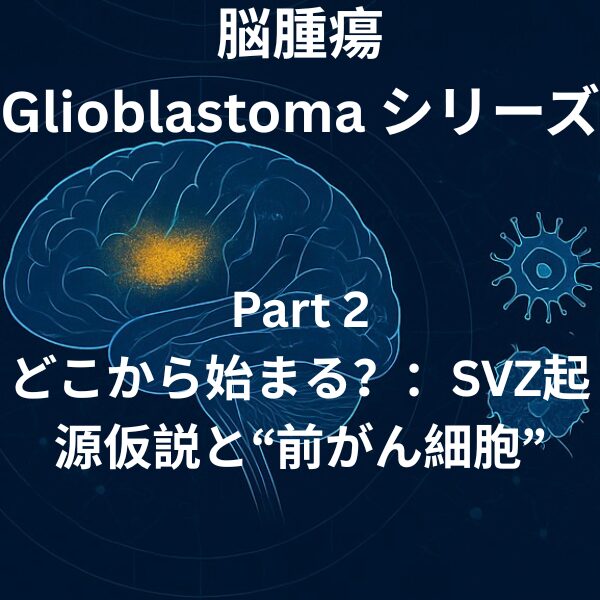
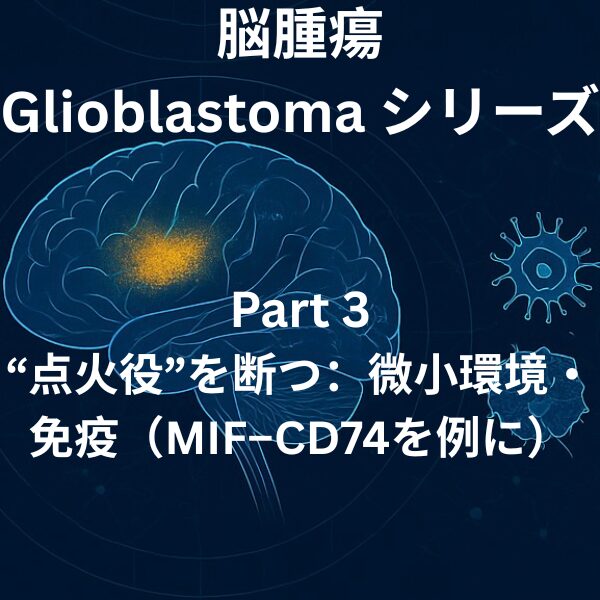
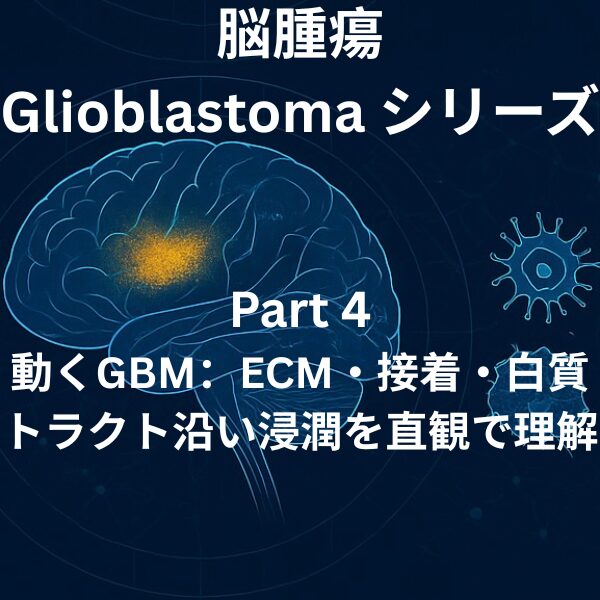
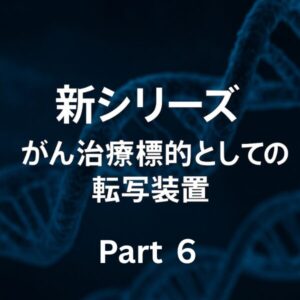
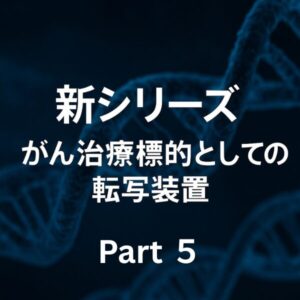
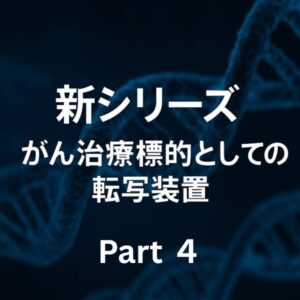
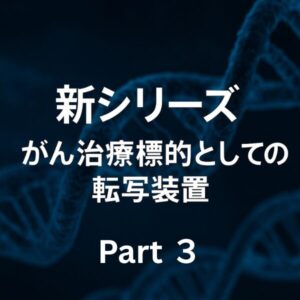
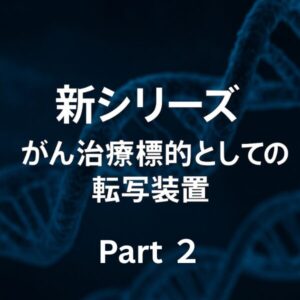
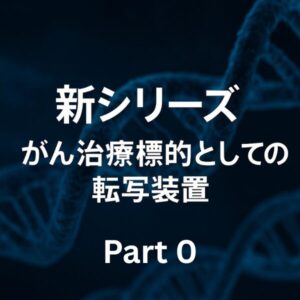
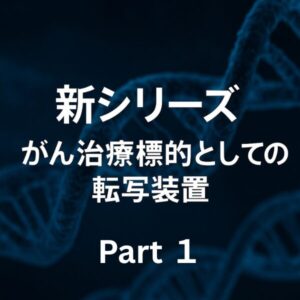

コメント