KRASは「Undruggable」の象徴から、いまや創薬テクノロジーの最前線をけん引する標的へと変貌した。G12C選択的阻害薬の成功を出発点に、2020年代半ばからはRAS(ON)阻害、Pan-KRAS分解、AI/量子コンピューティング創薬が台頭している。本稿では、これら新潮流の原理・強み・限界を整理し、臨床実装に向けた設計論(バイオマーカー、併用、試験デザイン)まで具体化する。
1. 選択的阻害から「ネットワーク制御」へ
アレル特異的阻害(例:G12C、進行中のG12D)は腫瘍縮小というインパクトを示したが、適応集団の狭さと耐性の早期出現(RTK再活性化→WT-RAS駆動)が課題として顕在化した。次の一手は、KRAS単独ではなくRASネットワーク全体(変異型+野生型、上流・下流)を同時に制御することにある。
- 課題A: WT-RASの代償活性化によるMAPK/PI3K再点火
- 課題B: 腫瘍タイプ×アレル差×RTK増幅の多様性
- 課題C: 併用時の毒性シナジーと投与順序の最適化
2. RAS(ON)阻害 ― 「活性状態」を狙う発想
RAS(ON)阻害は、アレルではなくGTP結合の活性状態そのものを標的化する。代表例はRMC-6236、RMC-7977などで、CYPAなど細胞内分子を「足場」に三者複合(tri-complex)を形成し、活性型RASへの選択性と持続的pERK抑制を実現するコンセプトだ。これにより、Mutant+WT-RASを同時に抑制し、RTKリバウンドを起点とする再増殖を抑え込むことが期待される。
- 強み: アレル横断性、WT-RAS由来の耐性回避、持続的pERK抑制
- 懸念: 正常組織への影響(生理的RAS依存臓器)、用量設定
- 適応仮説: PDAC/CRCなどG12C以外の高KRAS依存腫瘍、RTK増幅症例
3. Pan-KRAS分解(Degrader/TTPD) ― 阻害から「除去」へ
Degrader(分解薬)は、KRASをユビキチン化→プロテアソームで分解させる。PROTAC発想を発展させたACBI3のような候補は、複数アレルのKRASを同時に減少させ、阻害よりも広い変異スペクトルで機能的抑制を示しうる。さらにTTPD(Trivalent Targeted Protein Degradation)のような新技術は、標的結合・E3リクルート・協同性を強化し、分解効率と選択性を両立させる。
- 強み: アレル横断・触媒的作用・耐性プロファイル差
- 懸念: E3選択・組織分布・フック効果・中枢移行性
- 臨床設計: PD指標(KRAS量低下、pERK/pS6抑制)、リキッドバイオプシー
4. 上流ノードの同時抑制 ― SHP2/SOS1/RTKをどう組み合わせるか
WT-RASの再点火を断つ縦方向(vertical)併用は、依然として中核戦略である。SHP2阻害(TNO155、RMC-4630)やSOS1阻害(BI-1701963)をKRAS阻害と重ねることで、RTK→RAS活性化ループを鎮める。RAS(ON)阻害や分解薬の時代になっても、上流ノードの適量抑制は毒性を上げずに耐性を遅延させる鍵となる。
5. AI/量子コンピューティングが変える設計・最適化
近年は、拡散モデルや強化学習を用いた分子生成、FEP/誘電応答を組み合わせたバインディング予測、マルチ目的最適化(効力×選択性×ADME/Tox)に加え、量子変分アルゴリズムを活用した難標的ポケットのスクリーニングが報告されている。RAS(ON)や分解薬のような複雑なモードは計算支援の恩恵が大きく、さらに合成可能性予測(retrosynthesis)の併用で実験反復を圧縮できる。
- 生成AI:三者複合に適う立体配置・官能基の自動探索
- 量子計算:スイッチII近傍の遷移状態・水ネットワークの安定性予測
- インフォマティクス連携:タンパク質発現/プロテオーム×薬効応答の統合
6. バイオマーカー戦略 ― 誰に、いつ、何を投与するか
次世代KRAS治療は多層バイオマーカーで最適化する。
- 遺伝子層: アレル(G12D/V/R/C、Q61)、mutant dosage、共変異(TP53、STK11、KEAP1)
- シグナル層: pERK/pAKTのダイナミクス、RTK増幅/過剰活性
- 免疫層: T細胞浸潤、IFNシグネチャー、MDSC/CAF指標
- 動態層: ctDNAクリアランス(早期PDサロゲート)、循環タンパク質
特にmutant dosageは予後と治療反応に直結するため、適用ラインや併用強度の意思決定に組み込むべきである。
7. 併用設計:順序・間隔・強度の最適化
組み合わせの基本原則は「不足する回路を叩く」である。KRAS阻害(MAPK側)に対してPI3K/mTOR側を部分抑制、RTK亢進が強い症例ではSHP2/SOS1を早期から低用量で追加するなど、用量反応曲線の“谷(therapeutic valley)”を狙う。免疫併用では、RAS制御→腫瘍抗原性回復→ICB導入の段階的シーケンスが理にかなう。
8. 試験デザイン:アダプティブに、学習する治験へ
- アンブレラ/バスケット: 腫瘍種横断×アレル層別×RTK増幅層別
- ベイズ的適応: 早期PD指標(ctDNA、pERK)で腕入れ替え
- 実臨床データ連携: RWDで安全性・シーケンス効果を補強
主要評価項目はPFS/ORRに加え、ctDNA陰性化率やDORを早期から採り入れることで、ネットワーク制御の“質”を捉える。
9. 安全性とマネジメント
RAS経路抑制は皮膚毒性、消化器症状、肝機能異常などがボトルネックになる。低用量多剤・段階的導入・間歇投与は有力なマネジメントであり、分解薬は“オン/オフ”制御が効く点が利点になりうる。
10. 産業動向とアライアンス
RMC(RAS(ON)群)、Amgen/BMS(G12C群)、BI/Novartis(SHP2/SOS1群)を核に、分解薬陣営(学術発、専業ベンチャー)、計算創薬(AI/量子)との三位一体の提携が加速している。CDx企業との連携(ctDNA・RTK増幅・dosage評価)も前提化しつつある。
11. 私の考察 ― 「抑える」から「馴致する」へ
次世代KRAS創薬の核心は、生理的RASの役割を壊さず、腫瘍が必要とするネットワーク特性だけを選択的に弱体化する設計にある。分解×RAS(ON)×上流抑制×免疫のコンビネーションは、もはや“力業”ではなく、秩序を取り戻す調律である。臨床はその精密さを測る舞台へ変わる。
この記事はMorningglorysciences編集部によって制作されました。
関連記事






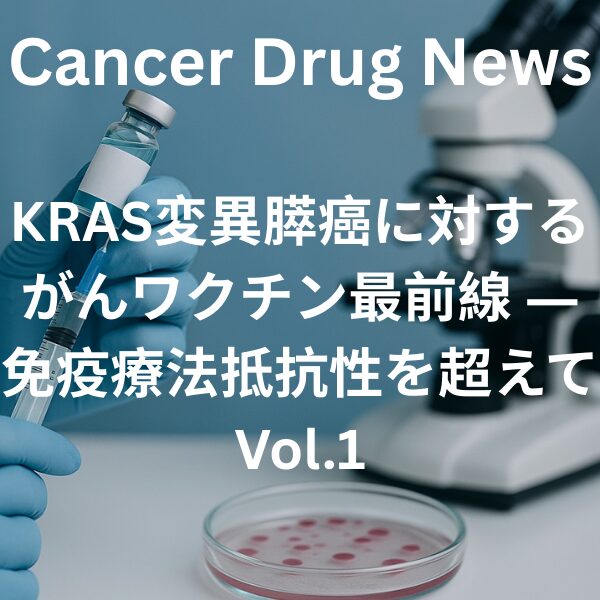
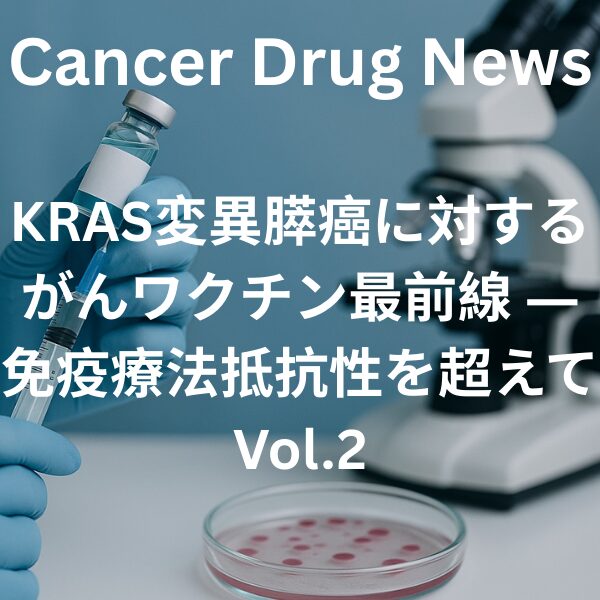
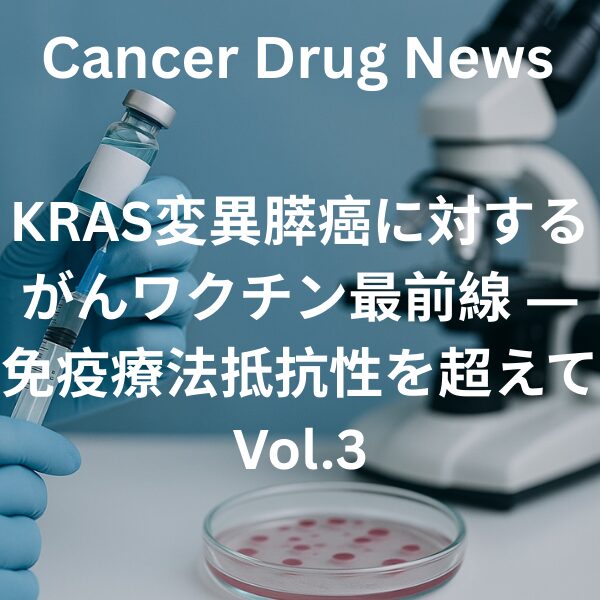



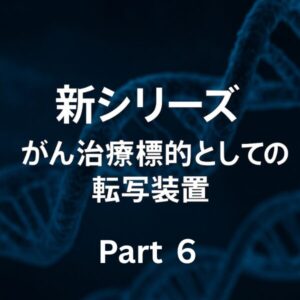
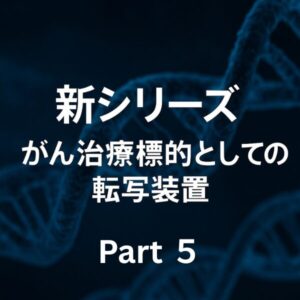
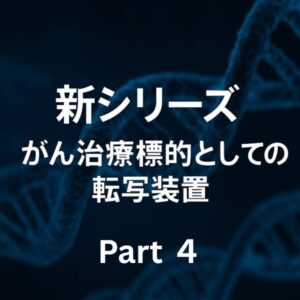
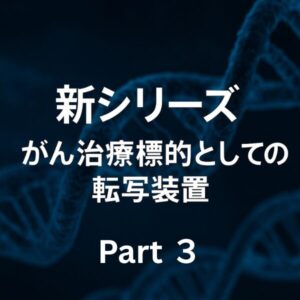
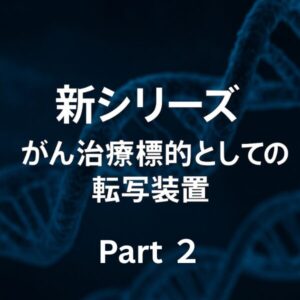
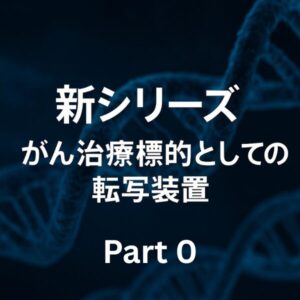
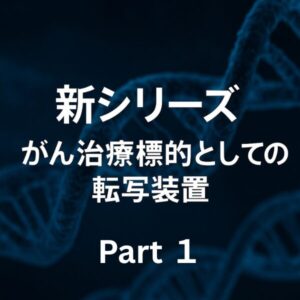

コメント