KRAS創薬の競争は、科学だけでなく産業構造そのものを変えつつある。 「Undruggable(創薬不能)」と呼ばれた標的が治療可能になった背景には、大学発ベンチャーやAI創薬スタートアップなど、新興企業の挑戦があった。 第7回では、Revolution Medicines、Amgen、Boehringer Ingelheim、Roche/Genentech、BridgeBio、Mirati(現BMS)、そしてExscientia(現Recursion)など、主要プレイヤーの動向とその戦略を総覧する。
1. Amgen ― G12C成功の象徴と、その次の一手
最初に難攻不落の壁を破ったのはAmgenのKRAS G12C阻害薬 Sotorasib(Lumakras)である。 非小細胞肺がんでの承認はKRAS創薬の歴史的転換点となった。 しかし市場は限定的であり、主な課題は:
- 適応がG12C変異に限定(KRAS変異全体の約13〜14%)
- WT-RASやRTK再活性化による耐性獲得
- 免疫チェックポイント併用での毒性と有効性の不均一性
Amgenは現在、SHP2阻害薬(RMC-4630)との併用試験を強化しつつ、Pan-KRAS阻害薬および分解薬へのアクセスを模索している。
2. Revolution Medicines ― RAS(ON)時代のアーキテクト
現代のRAS創薬をリードしているのが、米Revolution Medicines(RMC)である。 同社は「活性状態(RAS-GTP)」を標的にする独自技術RAS(ON)を開発し、G12CにとどまらずG12D/V/Rなど広範な変異型を包括している。
- RMC-6236:Pan-RAS(ON)阻害薬(Mutant+WTを同時制御)
- RMC-6291:G12C選択的RAS(ON)阻害薬
- RMC-9805:G12D特異的RAS(ON)阻害薬
さらにRMCは、SHP2阻害薬との併用を中核に据えた「RAS Network Therapy」という概念を提唱し、 RAS経路全体を“系として制御する”アプローチを確立した。 この哲学が後の「システムRAS治療」の基盤となっている。
3. Boehringer Ingelheim ― SOS1を軸とする上流制御戦略
ドイツのBoehringer Ingelheim(BI)は、上流経路のノードであるSOS1阻害薬 BI-1701963を中心に、RAS活性化ループを遮断する戦略を展開している。 この薬剤はRTK依存性の高い腫瘍で有効性を示し、KRAS阻害薬や免疫療法との併用候補として注目されている。
BIは独自のAIプラットフォーム「BI.X」を活用してRASネットワークをモデリングし、創薬化学とデジタル解析の統合を進めている。
4. Roche/Genentech ― ADCとRAS研究のクロスモダリティ戦略
Rocheは中外製薬と連携しながらADC技術で世界的なポジションを確立している。 一方、米国拠点のGenentechでは、RASシグナル伝達と免疫代謝の研究統合を進め、 「RAS阻害 → 免疫応答再活性化 → ADC・T細胞治療との連携」という多層的治療設計を実現しつつある。
この統合的アプローチは、RAS生物学・免疫・薬物デリバリーを組み合わせたクロスモダリティ創薬の最前線といえる。
5. BridgeBio・Mirati(現BMS) ― 精密腫瘍学の継承と拡張
BridgeBioはG12DやQ61Hなど稀少アレル型KRASを標的とする創薬を進めており、Genotype-defined Oncologyの先駆け的存在である。 Mirati Therapeuticsはadagrasib(Krazati)の成功後、2023年にBristol Myers Squibb(BMS)に買収された。 Miratiの研究基盤はBMS内でRAS+免疫併用戦略へと拡張されており、KRAS創薬の臨床インフラを大きく押し広げた。
6. AI創薬・量子創薬 ― Exscientia(現Recursion)を中心とする新潮流
AI創薬企業のExscientia(現Recursion)は、AIによる分子設計と臨床意思決定支援を組み合わせ、RAS標的分子の探索を加速させてきた。 XtalPiやInsilicoとともに、RASの“動的構造”を可視化するAIモデルを構築し、Switch II周辺の難ポケットに対して新規候補を創出している。
近年は量子アルゴリズムによるRAS分子動態シミュレーションが始まり、 AI×量子創薬がRAS(ON)および分解薬開発の「次の知能的フェーズ」を牽引している。
7. 競争軸の変化 ― 「早く」から「正しく」へ
RAS創薬の次の競争はスピードではなく精度と柔軟性である。 単剤のブレイクスルーよりも、AI×分解薬×免疫・代謝の統合設計が成否を分ける。 臨床試験も固定型からアダプティブ/バスケットデザインへと進化し、 データと創薬がリアルタイムに連携する時代に入った。
8. 私の考察 ― 科学と産業の融合が再び始まった
RAS創薬は、科学とビジネスを再び融合させた。 分子設計と経営戦略、AIと臨床、学術と資本がひとつの“創薬エコシステム”として機能している。 RASを軸としたこの流れは、がん治療だけでなく医療全体の構造を再設計する起点となるだろう。
この記事はMorningglorysciences編集部によって制作されました。
関連記事








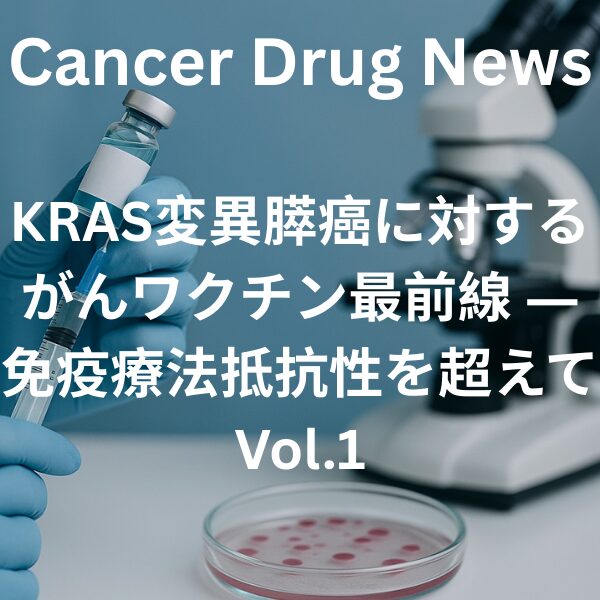
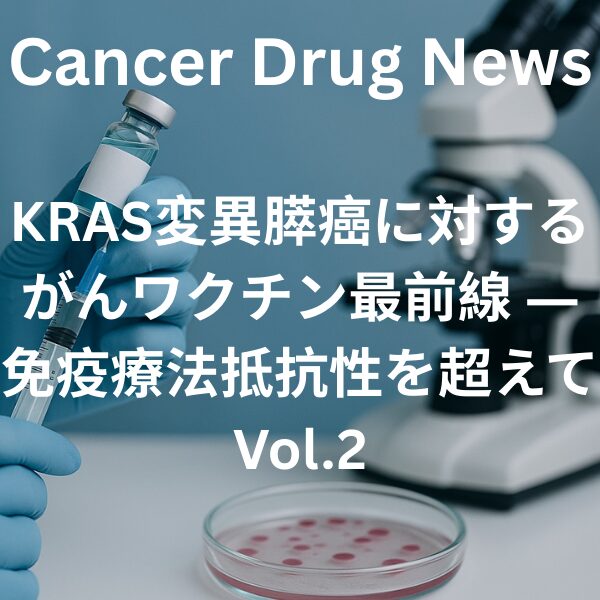
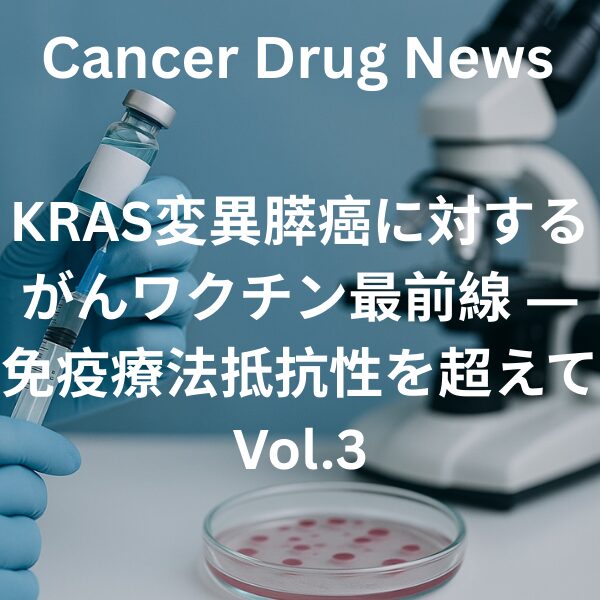



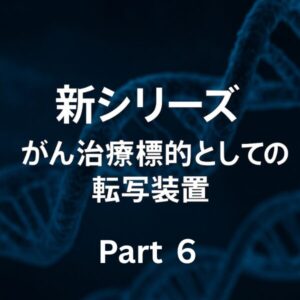
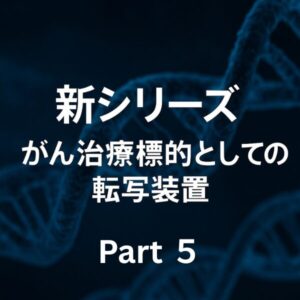
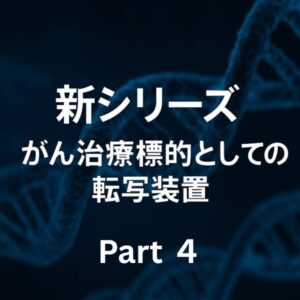
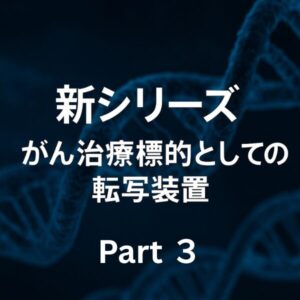
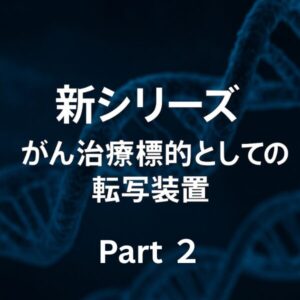
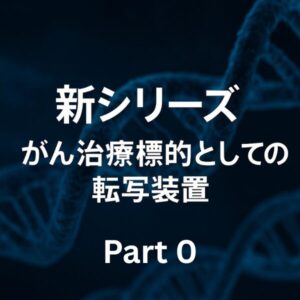
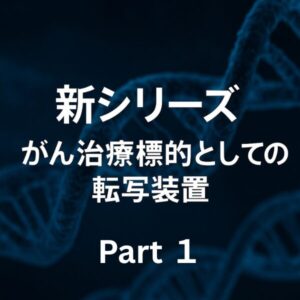

コメント