Claudin18.2(CLDN18.2)を標的としたADC開発は、SHR-A1904とIBI343の二つの第1相試験によって大きく前進しました。本記事では両試験を比較し、薬剤設計・有効性・安全性の違いを整理した上で、Zolbetuximabを含む既存治療との位置づけを議論します。
試験デザインと対象集団の違い
両試験はともに進行胃/GEJがんの既治療患者を対象としていますが、対象数と集団特性に違いがあります。
- SHR-A1904:95例、2ライン以上治療歴のある患者多数、用量漸増0.6〜8.0 mg/kg
- IBI343:127例、広い発現レベルを層別化、高発現群での効果が顕著、RP2Dは6 mg/kg Q3W
IBI343はCLDN18.2発現レベルに基づくサブグループ解析を行い、バイオマーカー主導治療の可能性を示した点が特徴です。
薬剤構造の違い
- SHR-A1904:CLDN18.2抗体+DNAトポイソメラーゼI阻害剤、Fc活性保持
- IBI343:CLDN18.2抗体+Exatecan(トポイソメラーゼI阻害剤)、Fcサイレンス設計
この違いにより、SHR-A1904は免疫依存性細胞障害(ADCC/CDC)も併せ持つ一方、IBI343はFc領域を不活化して消化器毒性の軽減を目指しています。
有効性の比較
両薬剤ともORRは20〜30%台にとどまるものの、治療抵抗性集団においては注目すべき成績です。
- SHR-A1904:ORR 24–25%、PFS中央値 約5.6か月
- IBI343:高発現群でORR 29–47%、PFS中央値 5.5–6.8か月
IBI343の方が高発現群で奏効率がやや高い傾向を示し、発現レベルとの関連性がより明確でした。
安全性の比較
有害事象はいずれも血液毒性が主体ですが、消化器毒性の頻度に違いが見られます。
- SHR-A1904:悪心・低アルブミン血症が多く報告、Grade ≥3は62%
- IBI343:血球減少主体、消化器症状は比較的軽度、Grade ≥3は66%
IBI343はFcサイレンス設計の効果で消化器系副作用が抑制されている可能性があります。
Zolbetuximabとの比較とADCの位置づけ
Zolbetuximabは2024年にFDA承認を得た初のCLDN18.2標的抗体ですが、効果は免疫環境に依存し、PFS・OS延長は限定的でした。これに対しADCは、免疫細胞活性に依存せず腫瘍直接殺傷作用を持つため、Zolbetuximab不応例や免疫抑制性腫瘍環境でも有効性が期待されます。
ADC共通の課題
- 奏効率が30%前後にとどまる点
- 血液毒性を中心とするGrade ≥3 AEの高さ
- 耐性獲得のメカニズム(ADC内在化、薬物排出、DNA修復経路活性化など)
これらを克服するには、発現バイオマーカー精緻化、バイスタンダー効果を持つペイロード選択、免疫療法や化学療法との併用戦略が不可欠です。
私の考察
両ADCはそれぞれ異なる設計思想を体現しており、SHR-A1904は「免疫活性+ADC」、IBI343は「安定PK+毒性軽減」を志向しています。私の見立てでは、今後は以下の戦略が重要になるでしょう。
- 発現レベルに基づく適応最適化:IBI343のように高発現群で強い効果を示す薬剤は精緻な患者選択が必須。
- 併用療法:ADC単独では限界があり、ICIや抗VEGF剤との組み合わせでシナジーを模索すべき。
- 耐性克服:トポイソメラーゼI阻害剤耐性メカニズムの解明と、異なるpayloadを用いた次世代ADC開発が不可欠。
総合的に見て、SHR-A1904とIBI343は相補的な位置づけを持ち、両者の進展が今後のClaudin18.2治療の基盤を形成すると考えます。
Morningglorysciences公式サイト では、最新のがん治療とバイオテック技術に関する解説を継続更新中です。
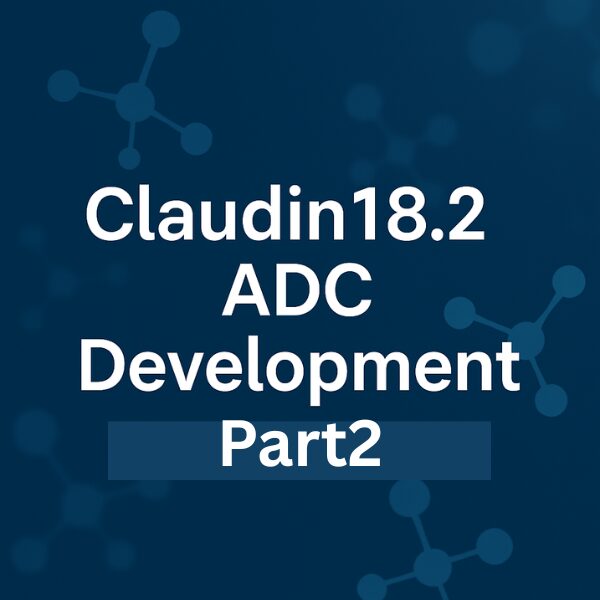

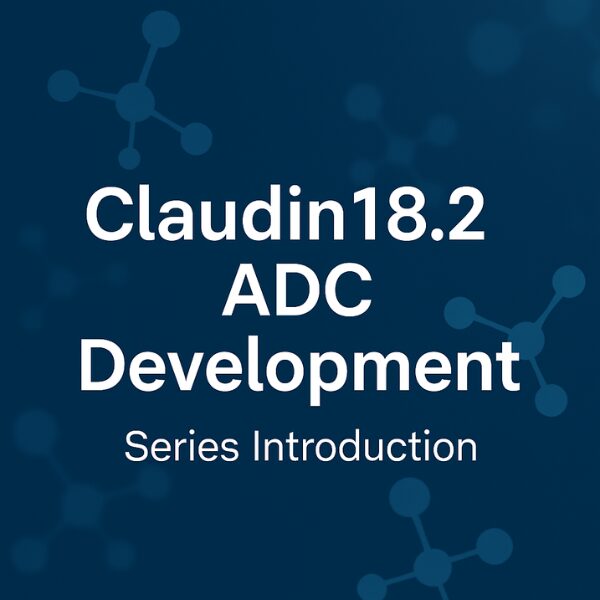






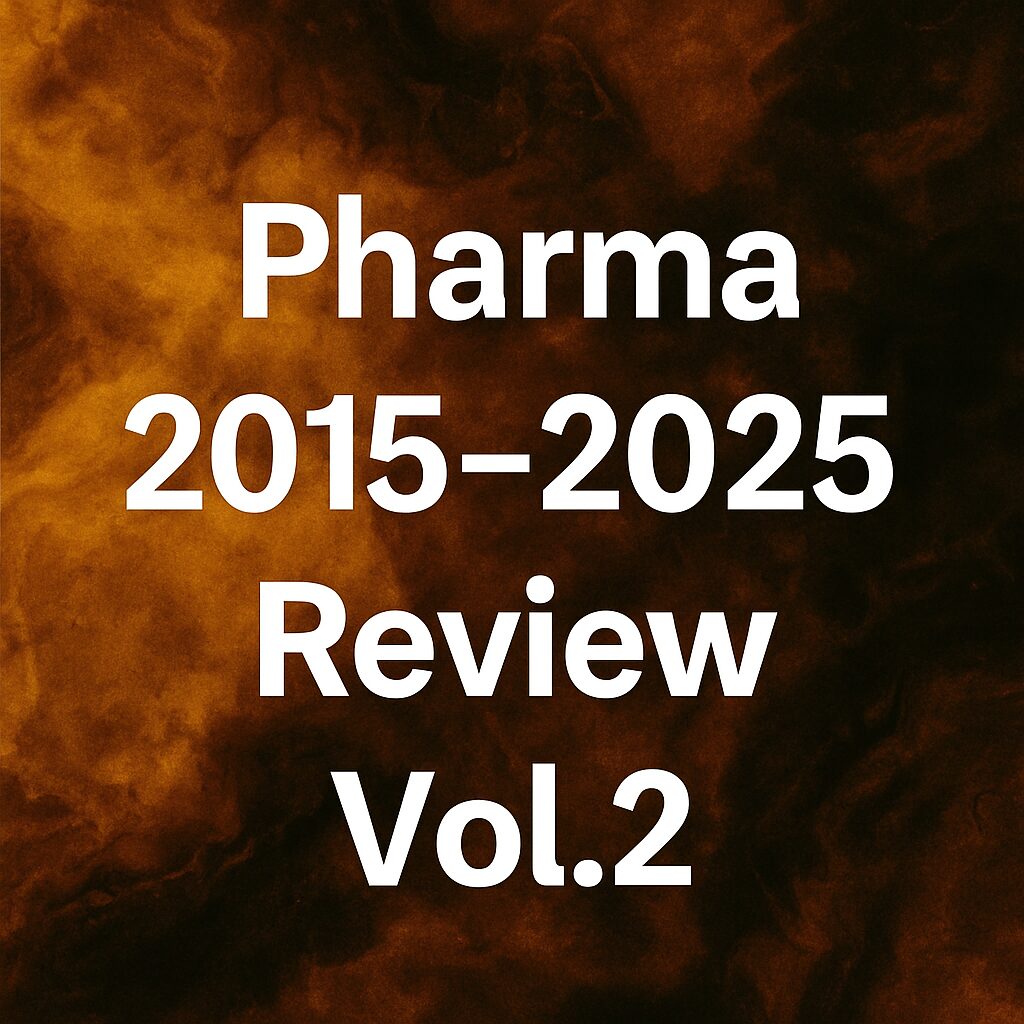

この記事はMorningglorysciencesチームによって編集されました。
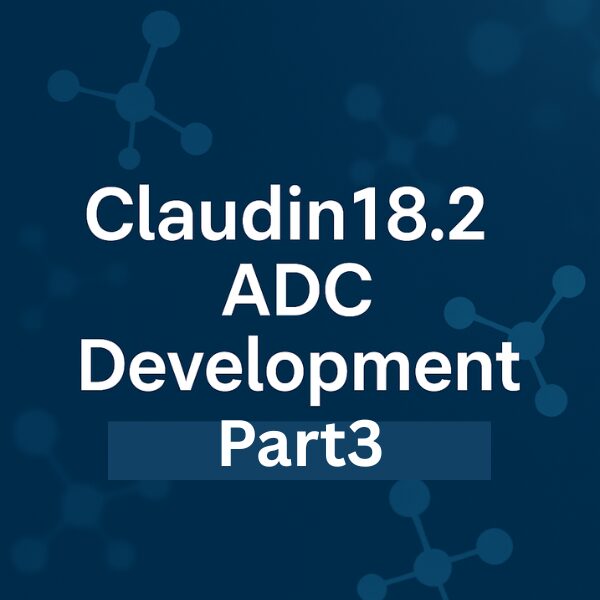
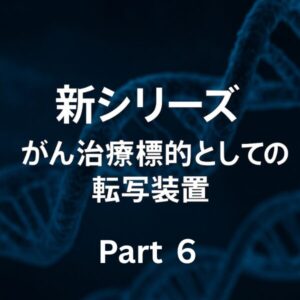
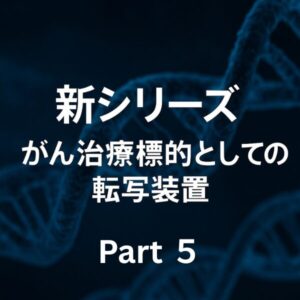
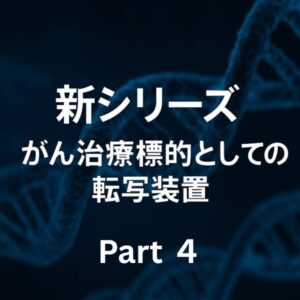
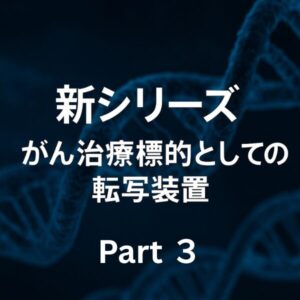
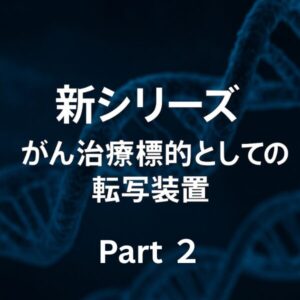
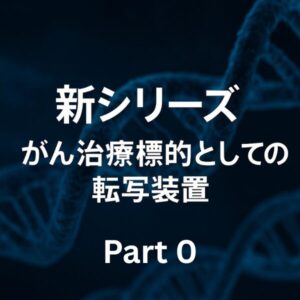
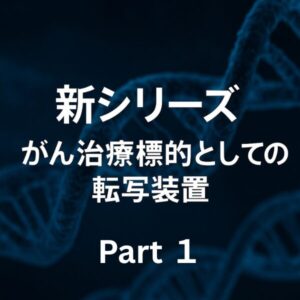

コメント