はじめて読む人でも「診断から初期治療、そして再発まで」の全体像がわかるように、専門用語をしぼって丁寧に解説します。
今回のゴール(3分で把握)
- どんな症状で受診につながるのかをイメージできる。
- 診断の流れ(画像→手術→病理・分子検査)を図としてつかめる。
- 標準治療(手術+放射線+テモゾロミド)とTTFの立ち位置がわかる。
- 再発のときに何を考えるか(治験・選択肢)を「地図」で理解できる。
シリーズ案内
本シリーズは、超入門→最新の治療設計へと段階的に学べる構成です。Part 0(超入門)→本回(臨床の地図)→Part 2(起源と前がん細胞)…と読み進めると理解がシームレスにつながります。
まずは症状:受診のきっかけになるサイン
- 頭痛・吐き気:腫瘍や浮腫で頭蓋内圧が高まると起こりやすい。
- けいれん(発作):てんかん様の発作で発見されることがある。
- 言葉・理解のしづらさ、運動まひ、しびれ:腫瘍の場所に応じた神経症状。
- 性格・行動の変化、集中力や記憶の低下:前頭葉やネットワークの機能低下。
- 視野障害、ふらつき:視路や小脳に関わる症状。
※症状は人によって異なります。上記はあくまで代表例です。
診断の流れ:画像 → 手術 → 病理・分子検査
1) 画像検査(主にMRI)
- MRI(造影):典型像の把握、周囲の浮腫、白質トラクトとの関係を確認。
- 機能画像:拡散テンソル(DTI)で重要な神経線維との距離感をみることがある。
2) 手術(できるだけ安全に、できるだけ多く)
- 最大安全切除:機能温存を最優先しながら腫瘍量を減らす。
- 切除が難しい部位では生検で診断を得ることも。
3) 病理・分子検査
- 組織の見た目(組織学)に加えて、分子情報(例:IDH、TERT、EGFR、MGMT など)を確認。
- MGMTプロモーターのメチル化は、後述のテモゾロミド(TMZ)感受性と関係。
入門ボックス:用語の最小セット
- MGMTメチル化:TMZが効きやすい傾向のバイオマーカー。
- 最大安全切除:機能を守りつつ、できるだけ取り切る戦略。
- DTI:白質線維の走行を可視化し、手術計画に役立つMRI。
標準治療とTTFの位置づけ
基本は「手術」→「放射線+テモゾロミド(TMZ)」
- 手術:腫瘍量を減らすほど、その後の治療が働きやすくなる傾向。
- 放射線療法:局所制御の柱。分割照射で実施。
- テモゾロミド(TMZ):経口のアルキル化剤。放射線と同時併用→維持投与。
TTF(腫瘍治療電場)
- 頭部に装着した電極パッドから、特定の周波数の電場を腫瘍部位へ送る。
- 細胞分裂を妨げることで、TMZと併用して生存延長の報告がある。
- 装着時間のアドヒアランスが治療効果の鍵。
QOLと支持療法もセットで考える
- けいれん管理:抗てんかん薬は個別化。
- 浮腫対策:ステロイド使用は最小限に、離脱も計画的に。
- リハビリ・栄養・心理的サポート:生活の質を守るための土台。
再発時の考え方:次の一手をどう決めるか
再発は珍しくありません。だからこそ、「次の一手」を落ち着いて検討できる準備が大切です。
再手術:症状緩和や組織再評価を目的に。
再照射・定位照射:前回照射量や部位の条件次第で選択。
薬物療法の変更・臨床試験:分子層別・既往治療歴で最適化。
治験(臨床試験):最新の治療へアクセスする重要な導線。
入門ボックス:臨床試験って何?
- Phase 1:安全性の確認(用量を探る)。
- Phase 2:有効性の手がかり(仮説検証)。
- Phase 3:標準治療と比較(最終検証)。
参加条件(適格基準)が定められています。主治医とよく相談しましょう。
図でつかむ「臨床の地図」(テキスト版)
症状 → MRI(+必要に応じ機能画像)
最大安全切除 or 生検 → 病理・分子検査(MGMT ほか)
放射線+TMZ(±TTF) → 維持TMZ(±TTF)
経過観察と支持療法(けいれん・浮腫・リハなど)
再発時:再手術/再照射/薬剤変更/治験の検討
一旦のまとめ
GBMの初期対応は、「最大安全切除」→「放射線+TMZ」→「必要に応じTTF」が基本ライン。
治療は生活の質(QOL)の維持とセットで設計する。
再発時は治験を含めた選択肢を早めに把握しておくと、判断が落ち着く。
私の考え
臨床の地図をもつことは、個々の患者さんにとっての最適な順番を見つけることに直結します。GBMは再発しやすく、単剤での決定打は限られます。だからこそ、標準治療の上に何を重ねるか、再発時に何へアクセスするかを早い段階から想定しておくべきです。次回以降、腫瘍の「出発点」や「微小環境」「可塑性」を学び、より理屈の通った組み合わせへと進めていきます。
Morningglorysciencesチームによって編集されました。
関連記事
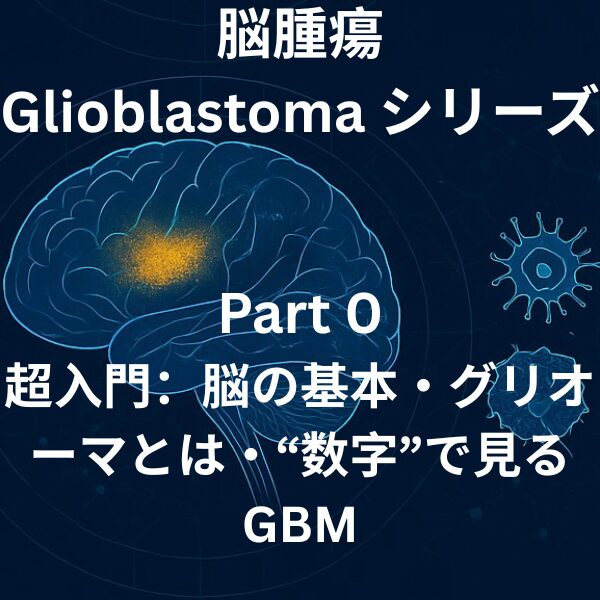
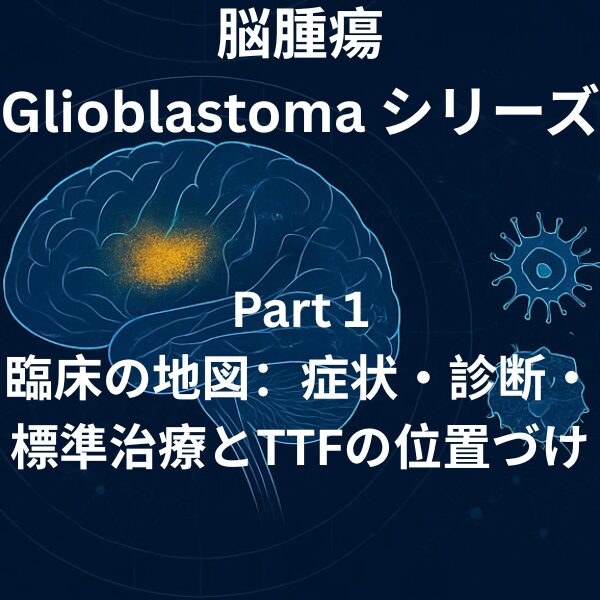
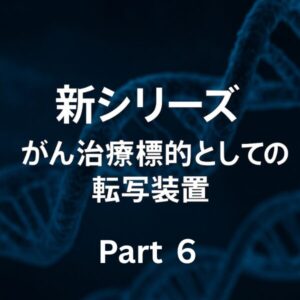
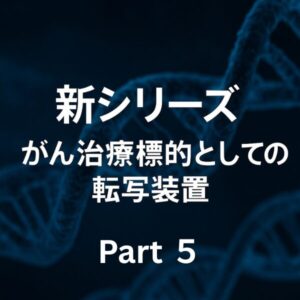
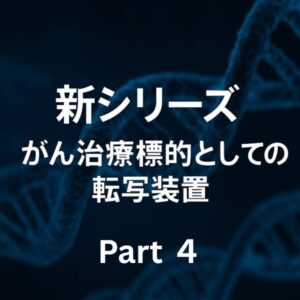
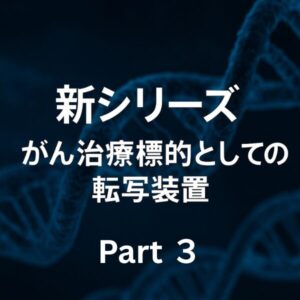
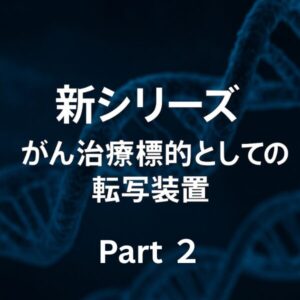
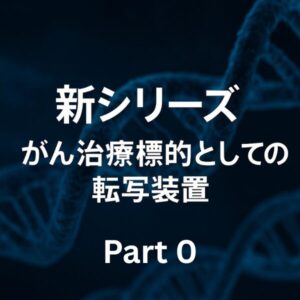
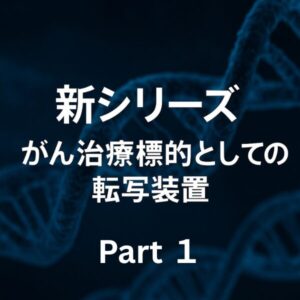

コメント