どこから始まる?――SVZ起源仮説と“前がん細胞(pre-CC)”
「腫瘍そのもの」だけでなく、どのように生まれ、どう成長し、どこで多様化が始まるのかを、入門トーンでやさしく整理します。
今回のゴール(3分で把握)
- SVZ(側脳室下帯)とは何か、なぜ注目されるのかが分かる。
- 前がん細胞(pre-CC)のイメージを、難しい数式なしで理解できる。
- 「腫瘍の芽」と「腫瘍本体」の関係(共有する変化と分岐)を直観でつかむ。
- なぜ治療の設計に役立つのか(早期介入・層別・併用のヒント)。
SVZとは?――脳の“苗床”のような場所
SVZ(Subventricular Zone, 側脳室下帯)は、脳室のそばにある幹/前駆細胞のニッチ。生涯を通じて細胞の供給源になりうるため、変化の起点として注目されます。
入門ボックス:ここだけ押さえる
- 幹/前駆細胞:分裂し、新しい細胞を生む“母体”のような細胞。
- ニッチ:幹細胞が働く“環境(場)”。周囲の細胞・分子シグナルが重要。
- 仮説の要点:一部のGBMは、SVZの細胞に生じた変化が“出発点”になっている可能性。
“前がん細胞(pre-CC)”とは?
pre-CCは、がん化の手前にある細胞集団を指す言葉です。すでに一部の遺伝学的・機能的変化を持ちながら、まだ“腫瘍そのもの”ではない段階。たとえば、染色体7の増加(chr7 gain)や染色体10の欠失(chr10 loss)のような“方向づけ”となる変化を共有している一方で、その後の変化は分岐して腫瘍本体の多様性につながる、と考えられています。
たとえ話:枝分かれする“苗”
同じ苗(pre-CC)から育った枝(腫瘍細胞)が、それぞれ違う葉や実(性質)をもつイメージ。苗の段階での共通点(chr7+/chr10−など)と、育つ過程での分岐(コピーナンバー変化や転写状態の違い)が、最終的な多様性を生みます。
何を“共有”し、どこで“分岐”するか(クローン進化の超入門)
- 共有:pre-CCと腫瘍本体が同じ“初期変化”を持つことがある(例:chr7+/chr10−)。
- 分岐:その後に生じる変化(増幅/欠失や遺伝子発現のクセ)が枝ごとに異なり、OPC-like/AC-like/MES-likeといった“細胞状態”の違いへつながる。
- 結果:腫瘍は可塑性(状態が行き来する力)を持ち、単一標的に逃げやすい。
※専門的には単一細胞解析や系統推定を用いて議論されますが、本記事では概念を重視します。詳細は後続回(可塑性・バイオマーカー)で丁寧に扱います。
“場”の力:微小環境とMIF–CD74(入門)
pre-CCから腫瘍化へ進む局面では、微小環境(免疫・グリア・ECM)のシグナルが強まると考えられます。例として挙げられるのがMIF–CD74という経路。これは“芽”の段階から腫瘍本体、そして免疫細胞とのやり取りに関わる可能性があり、早期介入の標的として注目されています。
ワンポイント:腫瘍“そのもの”だけでなく、周囲の場(Microenvironment)を整える発想が重要です。
なぜ治療設計に効くのか
- 早期介入の糸口:pre-CC段階に特有の脆弱性(例:GAP43/CCND1依存など)が示唆され、芽の段階で“多様化”の前に手を打つ発想へ。
- 層別の指標:SVZ近傍のpre-CC署名や、画像(DTI)との組み合わせで、誰に・いつ・何をの設計がクリアに。
- 併用前提:腫瘍の可塑性に対抗するには、pre-CC+微小環境+細胞周期のように多点で網を張る発想が有効。
図でつかむ(テキスト版:後日図に差し替え)
系統イメージ
- SVZの幹/前駆細胞
- pre-CC(chr7+/chr10−を共有)
- 分岐 → CC(OPC/AC/MES 状態多様化)
治療学イメージ
- pre-CCの脆弱性を狙う
- “場”の点火(MIF–CD74など)を抑える
- 可塑性を想定し多点併用で網を張る
一旦のまとめ
- SVZは“芽”が生まれやすい場で、pre-CCはがん化の前段階の概念。
- pre-CCと腫瘍本体は初期の変化を共有しつつ、その後に分岐して多様化する。
- 治療は、早期介入・層別・多点併用を見据えた設計がカギ。
私の考え
GBMの“難しさ”は、芽の段階から始まる多様化にあります。私は、腫瘍本体に到達する前の「pre-CCの足場」と「微小環境の点火」を同時に抑えることが、将来の治療をシンプルにする近道だと考えています。次回は、微小環境と免疫(MIF–CD74)を入門トーンでさらに深掘りします。
Morningglorysciencesチームによって編集されました。
関連記事
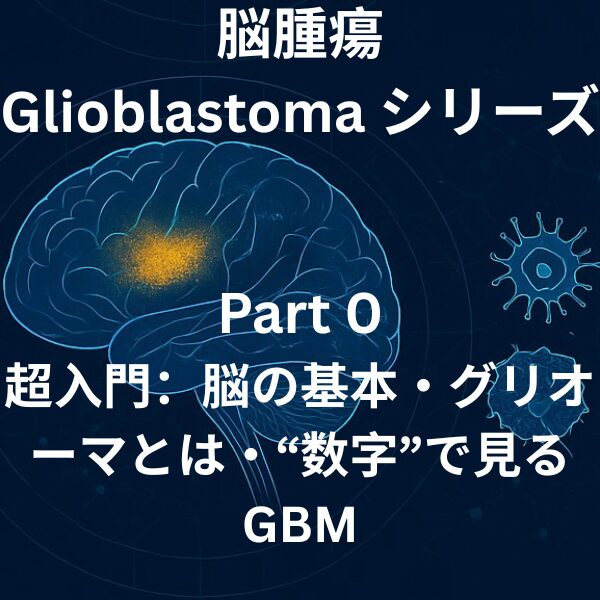
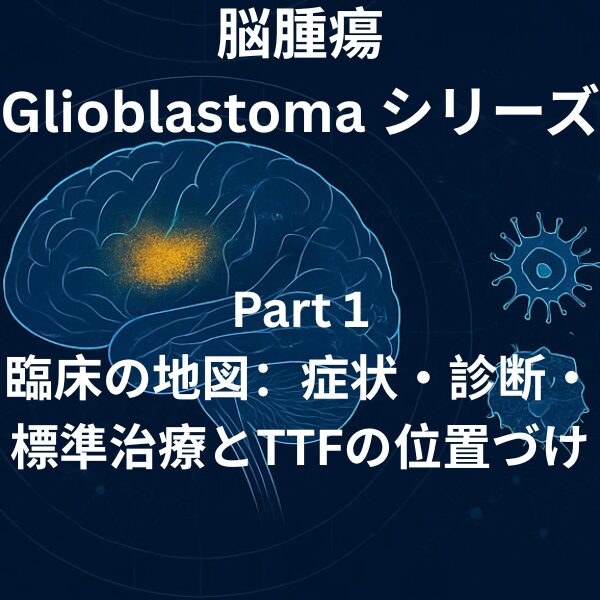
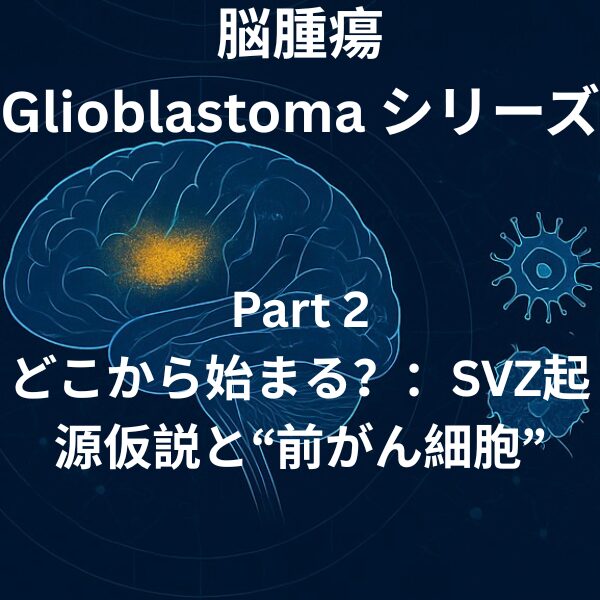
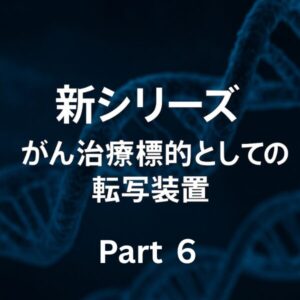
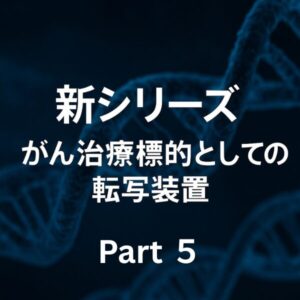
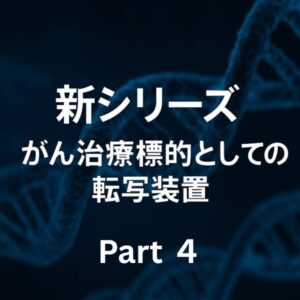
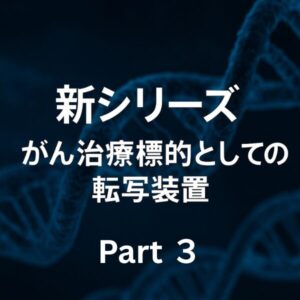
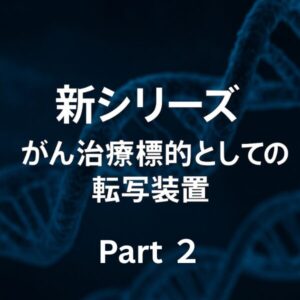
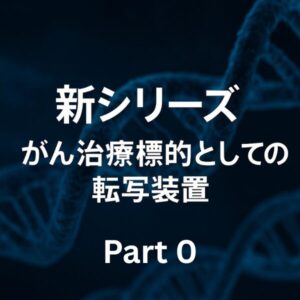
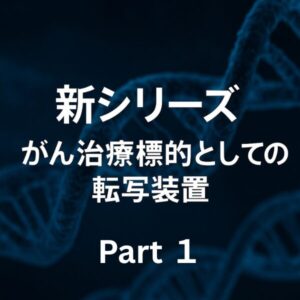

コメント