がん遺伝子の中でも最も長く、最も難解とされてきた標的――それがKRASである。 1982年にヒト膀胱がん細胞から最初のRAS変異が同定されて以来、40年以上にわたり科学者たちはこの分子を「不可能を可能にする」標的として追い続けてきた。 しかし、2020年代に入るまで、RASは“Undruggable(薬にならない)”の代名詞だった。
本シリーズの第1回では、KRAS研究の歴史と基礎生物学、難攻不落とされた理由、そして2020年代に起きた「直接阻害薬」のブレイクスルーまでを整理する。 また、第2回以降で扱う「Wild-type KRASの機能」や「多選択RAS(ON)阻害薬」などの理解を助ける基礎として、KRAS経路の全体像をここで俯瞰しておく。
1. KRASとは何者か ― RASファミリーとがんの起源
RASは、細胞の増殖・分化・生存を制御する小型GTP結合タンパク質群である。 ヒトにはHRAS・NRAS・KRASの3つの主要アイソフォームが存在し、いずれも「分子スイッチ」として機能する。 GDP結合状態では不活性(OFF)、GTP結合状態では活性(ON)となり、上流の受容体チロシンキナーゼ(RTK)からの刺激を受けて、SOS1などのGEFがGDPをGTPに交換することでスイッチが入る。
このRASスイッチがONのまま固定化される変異(特にG12・G13・Q61部位)は、がん細胞の恒常的増殖を引き起こす。 実際、RAS変異は全ヒトがんの約25〜30%に見られ、特にKRAS変異は膵がん・大腸がん・肺がんで高頻度に出現する。
- 膵がん(PDAC):約90〜95%がKRAS変異
- 大腸がん:約40〜50%
- 肺腺がん:約30〜35%
これほどまでにがんの根幹に関与する遺伝子は稀であり、「KRASを制御できれば、がんを制御できる」とまで言われてきた。
2. なぜKRASは“Undruggable”と呼ばれたのか
KRASが「難攻不落」とされた最大の理由は、構造的な“手がかりのなさ”にある。 ATP結合タンパク質やキナーゼとは異なり、RASは平滑で深いポケットを持たず、典型的な低分子阻害剤が結合できる空間が存在しなかった。 さらにRASは細胞内で極めて高濃度(10〜20 µM)で発現しており、GTPとの親和性が強いため、外部から競合的に奪うのはほぼ不可能と考えられていた。
もうひとつの理由は、RASの活性化・不活性化がきわめて短時間で行われる点だ。 GTP-GDP交換やGTP加水分解がミリ秒単位で進行するため、動的な構造変化を安定的に捉えることが難しかった。 これが「RAS阻害は物理的に不可能」とされた所以である。
3. RAS経路の地図 ― MAPKとPI3Kという二本柱
RASが活性化されると、細胞内で2つの主要経路が作動する:
- RAF–MEK–ERK経路:細胞増殖・分化・サバイバルを制御。
- PI3K–AKT–mTOR経路:代謝・タンパク質合成・抗アポトーシスに関与。
これら2経路はしばしば「RASの双翼」と呼ばれ、腫瘍の性質を決定づける。 興味深いことに、KRAS変異のアレル(G12D, G12V, G12Rなど)によって、どちらの経路が優勢かが異なることも知られている(第2回で詳述)。
また、RASはRAFやPI3Kのみならず、RAL-GDS、Tiam1など多様なエフェクターと結合する。 したがって、KRAS変異が単に「一つのスイッチ」ではなく、細胞全体のシグナル・ネットワークの重心を変える存在であることが理解できる。
4. “Undruggable”を覆した発見 ― KRAS G12C阻害薬の登場
転機が訪れたのは2013年。 カリフォルニア大学サンフランシスコ校のKevan Shokatらは、KRAS G12C変異のCys残基が新たな「アロステリック・ポケット(Switch II pocket)」を形成することを発見した。 このポケットに共有結合的に結合する化合物が、GTP結合を阻止し、KRASを「不活性のまま固定化」できることが示された。
この発見は瞬く間に業界を揺るがし、AmgenのSotorasib(Lumakras)、MiratiのAdagrasib(Krazati)という2つのKRAS G12C阻害薬が臨床開発に進んだ。 2021年、Sotorasibは非小細胞肺がん(NSCLC)を対象にFDA承認を取得し、史上初の「直接KRAS阻害薬」となった。
これにより、「RASは薬にならない」という固定観念はついに崩壊した。
5. それでも克服すべき壁 ― 限定的な適応と耐性
G12C阻害薬の成功は象徴的だったが、課題も残る。 まず、KRAS G12C変異は主に肺がん(約13%)に集中しており、膵がんや大腸がんでは頻度が極めて低い。 一方で、膵がんの大多数を占めるG12DやG12V変異には共有結合部位が存在せず、同様の手法が通用しない。
さらに臨床では、KRAS G12C阻害薬を投与しても耐性化がほぼ不可避であることが明らかになっている。 RTK(EGFR、METなど)の再活性化を介して、**Wild-type RAS(WT-RAS)** が代償的にシグナルを再起動するためだ。 つまり、KRAS阻害が一部成功しても、WT-RASが“バックアップ”として動き出す。
このメカニズムこそ、今後の創薬戦略で最も重要な「WT-RAS制御」の入り口である(第3回で詳述)。
6. RAS研究の新潮流 ― 多選択阻害・分解・免疫再構築へ
現在のRAS研究は、単なるG12C選択的阻害から次の3つの方向へ進化している。
- Mutant+Wild-typeを同時に抑制:例:Revolution MedicinesのRMC-7977(Mutant/WT-RAS(ON)阻害)
- Pan-KRAS分解:ACBI3など、複数アレルをまとめて分解するPROTAC/TTPD
- 免疫再プログラミング:KRAS阻害がTME(腫瘍微小環境)や抗腫瘍免疫に与える影響を活用する新戦略
これらはいずれも、「WT-RASが抵抗性を作る」という課題を逆手に取った設計思想であり、 “KRASだけ”ではなく“RASネットワーク全体”を抑える方向に舵が切られている。
7. Wild-type KRASへの注目 ― “静かな支配者”
近年の研究により、変異型KRASの隣で機能するWild-type KRAS(WT-KRAS)が腫瘍生物学に深く関与していることが判明した。 これまでWT-KRASは「何もしていない残存分子」と見なされていたが、実際には腫瘍増殖・免疫回避・耐性機構において積極的な役割を果たす。
特に、変異KRASによって活性化された下流経路が遮断されると、WT-KRASがPI3K–AKT経路などを介して補完的にシグナルを維持する。 この「バックアップ回路」はKRAS阻害の最大の難関であり、逆に言えばWT-KRASを同時に抑えることが次世代治療の鍵である。
WT-KRASはもはや“沈黙のパートナー”ではない――第3回では、このWT-KRASの役割と創薬への応用可能性を中心に掘り下げていく。
8. KRAS創薬を牽引する主要プレイヤー(2025年現在)
- Amgen:初のKRAS G12C阻害薬 Sotorasib(Lumakras)を上市。
- Mirati Therapeutics:Adagrasib(Krazati)を開発。後にBMSが買収。
- Revolution Medicines:RMC-6236(pan-RAS(ON)阻害薬)、RMC-7977(Mutant+WT-RAS阻害)で先行。
- Verastem / Black Diamond:RAF/MEK併用やアロステリック阻害薬を展開。
- Novartis / Boehringer Ingelheim:SHP2・SOS1阻害薬でWT-RAS上流制御を狙う。
- Quantum-based biotech:量子計算を活用したKRAS阻害薬スクリーニングも登場(Nature 2025報告)。
KRAS創薬の競争は、単なる「阻害」から「制御」「分解」「免疫連携」へと拡大しており、 今後3〜5年はオンコロジー領域で最も動きの激しい分野になると予想される。
9. 今後の展望と第2回への布石
KRAS研究の進歩は、がん治療の概念そのものを変えつつある。 「遺伝子変異=標的」という直線的な図式ではなく、ネットワーク動態を制御する治療へ――それが次の時代の方向性だ。
第2回では、KRAS変異の種類(G12D, G12V, G12R, Q61など)によって腫瘍の生物学的性質がどのように異なるか、 そしてそれが治療反応性・免疫環境・臨床転帰にどのような影響を及ぼすのかを解説する。
この記事はMorningglorysciences編集部によって制作されました。
関連記事


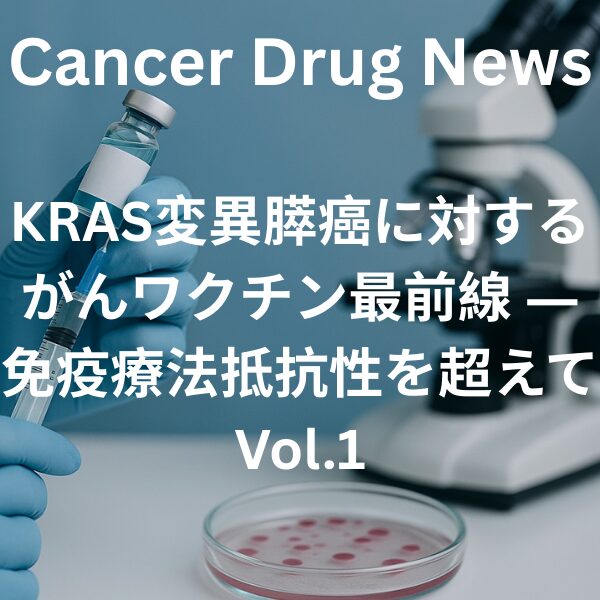
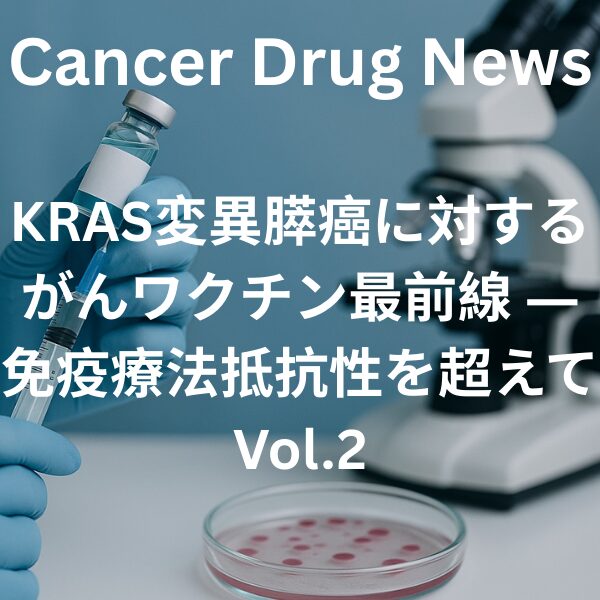
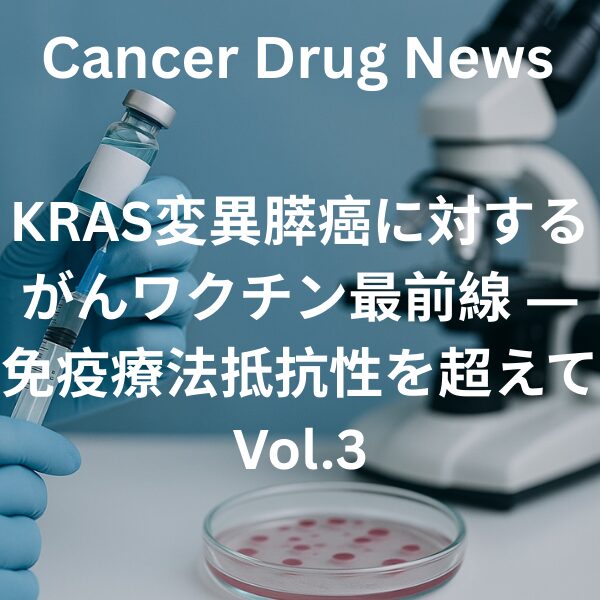



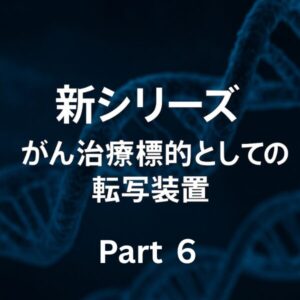
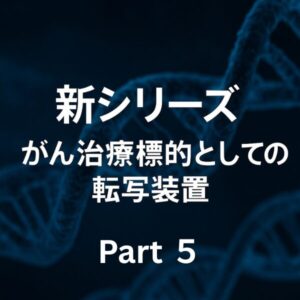
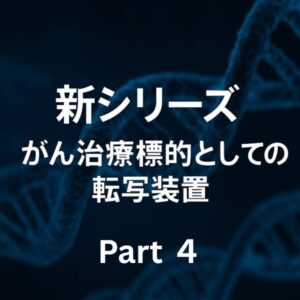
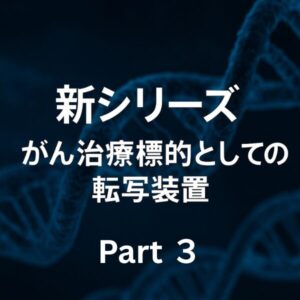
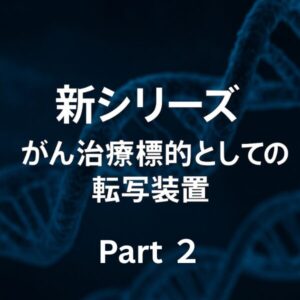
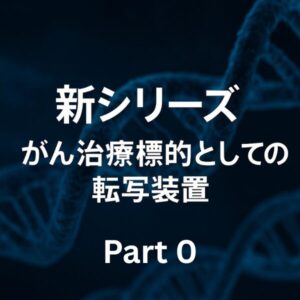
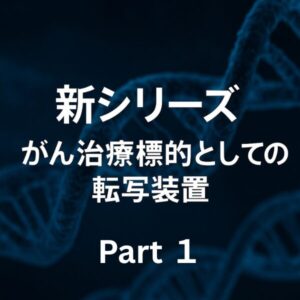

コメント