悪液質の“見える化” — CT体組成・機能・PROでタイプを掴む
第3部は、外来で実践できる「フェノタイピング(表現型の見極め)」の回。CT体組成・身体機能・患者報告アウトカム(PRO)を束ねて、脂肪優位喪失型/筋優位喪失型/混合型などの臨床タイプを素早く判断するコツをまとめます。
やさしい要約(3点)
- CTでの体組成定量(L3単切片)は筋・皮下脂肪・内臓脂肪を“数値化”できる。
- 機能とPRO(椅子立ち上がり・階段・握力相当/食欲・倦怠・悪心)は、治療の意思決定に直結。
- 縦断で見る(治療前→中間→評価時)。“どのコンパートメントが先に落ちるか”で支援策を変える。
1) CT体組成:L3単切片で「量」と「質」を定量する
腹部造影CTの第3腰椎(L3)レベルの単切片を用いると、骨格筋(SKM)・皮下脂肪(SAT)・内臓脂肪(VAT)の面積(cm²)や指数(cm²/m²)が算出できます。さらに、筋放射減弱(筋内脂肪化などの質低下の指標)も推定可能です。
実務メモ:スライス厚・造影相・HUしきい値を施設内で統一。
同一個人の縦断比較では、同条件のCTで解析すること(機器差・造影差に注意)。
- 筋の“量”低下:機能低下や有害事象リスク上昇と連動しやすい。
- 脂肪の“量”低下:早期のエネルギー枯渇シグナル。食欲低下や炎症の強さを反映。
- 筋の“質”低下:筋力効率の悪化。運動処方や蛋白戦略を早める根拠。
2) DXA/BIAとの使い分け、AI自動セグメンテーション
- DXA/BIA:全身の脂肪量・除脂肪量を低被曝/簡便に把握。治療サイクル間の追跡に向く。
- CT:局所の精密定量と“質”評価が強み。もともと撮像しているCTを二次活用するのが効率的。
- AI自動セグメンテーション:解析の再現性・スピードが向上。院内でアルゴリズムを固定し、縦断比較を標準化する。
3) 身体機能:外来3分でできる「強さ」と「持久」の見取り図
- 椅子立ち上がり(30秒 or 10回):日常生活の核心動作。回数/主観的きつさ(0–10)を記録。
- 階段2フロアの息切れ:循環・呼吸・筋の統合評価。主観スコアで縦断フォロー。
- 握力相当:ハンドグリップがなければ、親指と人差し指のつまみ力テストで代替。
- 歩行計測:5m歩行や6分間歩行(可能な範囲で)。在宅は歩数でも可。
4) PRO(患者報告):食欲・倦怠・悪心を“数”にする
食欲低下、倦怠感、悪心・味覚嗅覚変化などを、同じスケールで繰り返し測ることで、介入タイミングを逃しにくくなります。簡便な0–10の数直線でもかまいません(例:食欲 7→4)。
小技:在宅では1日1行の「食欲・活動・気分」の自己スコア。外来では2週間の平均を聞き取り。
5) フェノタイピング:タイプ別に手を打つ
同じ「体重減少」でも、落ちているのが脂肪か筋か、あるいは両方かで、優先すべき支援が変わります。
脂肪優位喪失型
- CTでSAT/VATの先行減少
- 食欲低下・悪心が目立つ
- 対応:食欲・悪心対策の強化、エネルギー補充、早期の栄養介入
筋優位喪失型
- CTでSKM低下・筋放射減弱
- 椅子立ち上がり・階段の悪化
- 対応:レジスタンス運動+蛋白戦略、機能リハを優先
混合型
- 脂肪・筋ともに低下
- PROで倦怠・食欲低下が強い
- 対応:マルチモーダル介入を早期・強度高めに
6) 縦断で見る:治療と連動させるチェックポイント
- 治療開始前(ベースライン):CT体組成+機能+PROを取得。
- 中間評価:レジメン変更点・有害事象と体組成の“動き”を突き合わせ。
- 治療評価時:タイプの変化(脂肪→筋へ、など)を確認し、支援策を調整。
同じ患者でも、時間とともにタイプが移行します。固定観念ではなく“いまの型”を見る運用が肝心。
7) よくある落とし穴と回避策
- CT条件の不統一:同条件の画像で比較。施設プロトコルを固定する。
- 単回測定の過信:縦断比較を前提に。最低でも2点、可能なら3点。
- 体重のみ評価:必ず機能・PROを併記。“体重安定でも機能悪化”に注意。
- データが多すぎる:ダッシュボードは3軸(体組成・機能・PRO)に絞る。
8) 外来で使えるミニ・ダッシュボード(雛形)
【体組成】L3:SKM xx cm²(→△x%)/SAT xx cm²(→△x%)/VAT xx cm²(→△x%)/筋放射減弱(±) 【機 能】椅子立ち上がり 10回・主観◯/10 → ◯/10/階段2F息切れ(±) 【PRO】食欲 ◯→◯/倦怠 ◯→◯/悪心 ◯→◯(0–10) 【総 合】タイプ:脂肪優位/筋優位/混合(該当を○) 【介 入】栄養/運動/症状ケア/投薬の変更点
私の考察
「体重」から「体組成・機能・PRO」に主眼を移すだけで、外来の意思決定は大きく変わります。とくに、脂肪が先に落ちる患者と筋が先に落ちる患者では、第一選択の支援策が異なります。CTは“答え”ではなく“方向づけ”の道具。最小限のダッシュボードで、いまの型に合わせた介入を素早く回す体制づくりが鍵です。
次回予告
第4部は「何が壊れている?— ヒト研究で読む食欲・代謝・脂肪・筋」。中枢ドライバー(GDF15 など)や代謝・炎症経路を、臨床所見と結びつけて解説します。
編集:Morningglorysciences
関連記事


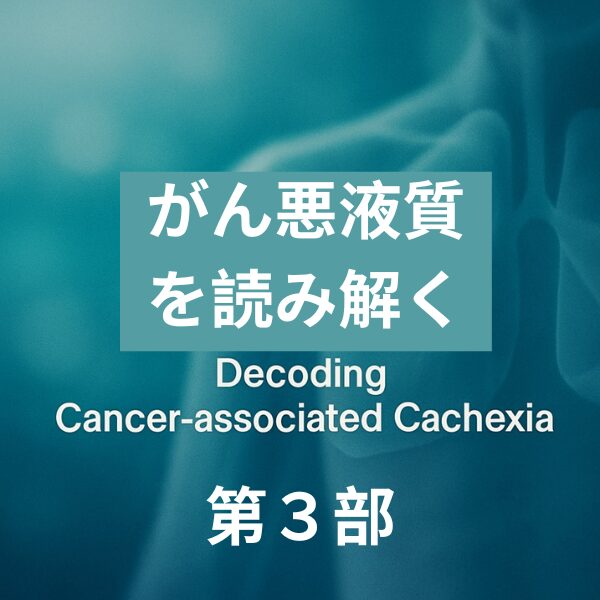
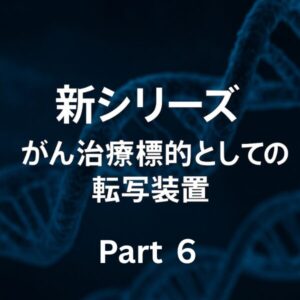
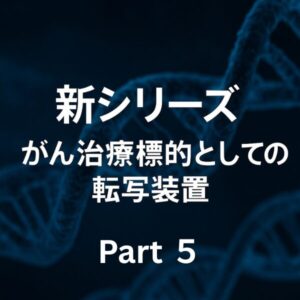
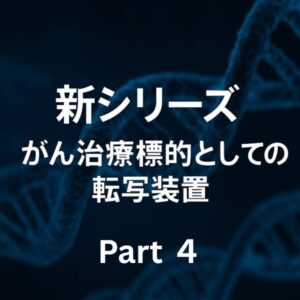
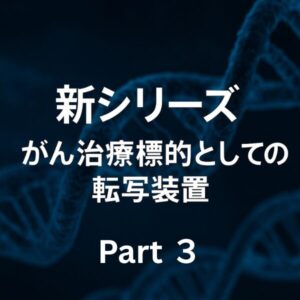
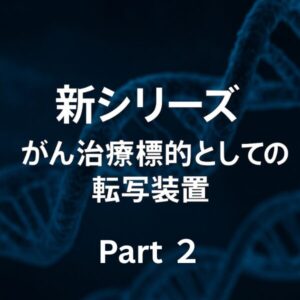
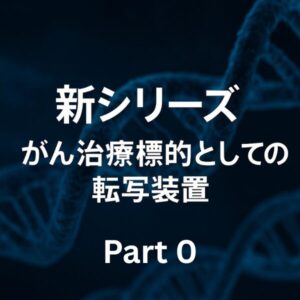
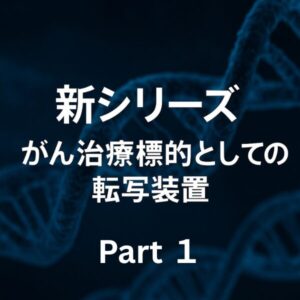

コメント