今日からできる対処 — 栄養×運動×抗炎症+既存薬のリアル
第5部は実装ガイド。家庭と外来の導線をそろえ、栄養・運動・炎症コントロール・症状緩和をセットで回す方法を、ワークフローとテンプレで示します。薬はあくまで補助輪。主治医と相談したうえで安全第一で運用してください。
目次
やさしい要約
- 多職種・多要素を同時に:栄養+運動+炎症・症状ケアを一括で開始し、2週間で見直す。
- “型”に合わせて優先度を変更:脂肪先行型なら食欲・悪心対策+エネルギー補充、筋先行型ならレジスタンス+蛋白強化。
- 薬は短期・目的限定で:低用量オランザピン、メゲストロール、短期ステロイド、(日本)アナモレリン等は効果とリスクを見極めて使う。
1) 外来ワークフロー(所要:初回15–20分、以後10分)
- 事前準備(家庭):第2部の2週間ログ(体重・食事量・活動・機能・症状)+1日1枚の食事写真。
- クイック評価(外来):第3部のミニ・ダッシュボード(体組成/機能/PRO)に反映。
- “型”判定:脂肪先行/筋先行/混合。
- 同日スタート:栄養計画+在宅レジスタンス指示+症状/炎症対策+(必要に応じ)薬の短期トライアル。
- 2週間後レビュー:体組成傾向・機能・PROの変化で調整(増減・中止・切替)。
2) 栄養:エネルギーと蛋白を“現実的に”確保する
- 目標の目安:蛋白1.2–1.5 g/kg/日、総エネルギー25–30 kcal/kg/日(高齢・低活動は個別化)。
- 配分:3食+間食2回。毎食に主菜(卵/魚/肉/大豆)を1品。
- メニュー例(1日):朝=卵+ヨーグルト、昼=鮭/鶏+ごはん/パン、間食=チーズ・プリン、夕=豆腐/肉、寝る前=牛乳/豆乳。
- 食べにくい時:冷製・酸味・香り(レモン・ハーブ)、少量頻回、飲むタイプの補助食品を短期間活用。
- 脂肪先行型のコツ:エネルギー密度↑(オイル/バター/ナッツ/アボカド)+悪心対策の同時実施。
- 筋先行型のコツ:ロイシン/EAAを意識、運動直後の蛋白摂取をセットに。
3) 在宅レジスタンス:痛みゼロ・息切れ軽度で
基本セット(週3日目安)
- 椅子からの立ち座り:10回×2
- かかと上げ:20回×2
- ゴムバンドで肘曲げ/伸ばし:10回×2
- 軽い階段昇降:1–2フロア
強さ目安=RPE 3–4/10(やや楽〜ややきつい)。悪化日(発熱/強い吐き気/疼痛増悪)は休む。
安全フラグ(中止→主治医へ)
- 胸痛・強い息切れ・めまい、転倒未遂
- 発熱、脈拍異常、SpO₂低下を感じる
- 新規/増悪の骨痛・重い筋痛
4) 炎症・症状コントロール:食べられる環境を作る
- 悪心・嘔吐:オランザピン低用量(就寝前)、5-HT3拮抗薬などをレジメンに合わせて調整。
- 疼痛・睡眠:痛みの鎮静と睡眠の質改善は活動度を解放する第一歩。
- 便秘/下痢・口内炎:食べにくさのバリアをすぐ下げる(緩下薬/整腸薬/含嗽など)。
- 抗炎症:NSAIDs等は適応とリスクを確認し、短期・最低有効量で(腎/消化管に注意)。
5) 既存薬の“使いどころ”(要:主治医判断)
(日本)アナモレリン
- 対象:特定がんの悪液質。食欲・体重・除脂肪量の改善が狙い。
- 向いている型:脂肪先行~混合で食欲低下が前景のケース。
- 注意:血糖・浮腫、心血管既往。治療目標と期間を明確化。
オランザピン(低用量)
- 対象:悪心・食欲不振の症状緩和。
- 使い方:就寝前の少量から。眠気や錐体外路症状/QTcに注意。
メゲストロール酢酸
- 期待:食欲↑・体重↑。
- 注意:浮腫・静脈血栓のリスク。高齢者やリスク高群では慎重に。
ステロイド(短期)
- 期待:倦怠・食欲の短期改善。
- 注意:長期は有害(感染・筋萎縮・高血糖)。期間と減量計画を必ず設定。
※いずれも“効いたら理由づけて継続/効かなければ速やかに停止”の方針で。単剤長期固定は避け、2週間ごとに再評価。
6) 型別の第一手(クイック表)
脂肪先行型
- 悪心・食欲対策を最優先
- 高エネルギー密度の献立
- (適応時)アナモレリン
筋先行型
- レジスタンス+蛋白強化
- 疼痛・睡眠の最適化
- 炎症/代謝軸の是正
混合型
- 多要素を同時に開始
- 症状緩和を強める
- 短期的な薬の併用を検討
7) 2週間レビューで見る指標
- 食欲/悪心スコア(0–10)
- 機能(椅子立ち上がり回数と主観、階段の息切れ)
- 体重/むくみ(±)、便通
- 行動(外出回数・歩数・昼寝の増減)
- 安全(転倒・高血糖・浮腫・不整脈など)
8) よくある落とし穴
- 体重だけ追う → 機能/PROを併記して判断。
- “食べられない”の放置 → まず悪心/口内炎/便秘を叩く。
- 運動ゼロ or やり過ぎ → RPE 3–4で継続可能に。
- 薬を漫然と継続 → 2週間で効果判定・中止基準を明記。
私の考察
“食べる・動く・整える”を同時にスタートすることが、単発の介入より強い効果を生みます。第一手は“型”に寄せて素早く、次の2週間で効いた要素を増やし、効かない要素を切る。この反復が、治療継続性とQOLを底上げします。薬は路面をならす道具に過ぎません。患者さんが活動できる時間帯を作る——そこに医療資源を集中的に投下する設計が、現場では合理的です。
次回予告
第6部は「次の一手はここだ — GDF15阻害と精密表現型の時代へ」。バイオマーカー駆動の患者選択、複合エンドポイント、在宅計測を組み込んだ次世代試験設計を展望します。
編集:Morningglorysciences
関連記事
世界最先端の治療薬を創る〜製薬会…


シリーズ:がん悪液質を読み解く — 超入門から最前線まで|第1部 – 世界最先端の治療薬を創る〜製薬会社、…
がん悪液質(Cancer-Associated Cachexia,
世界最先端の治療薬を創る〜製薬会…


シリーズ:がん悪液質を読み解く — 超入門から最前線まで|第2部 – 世界最先端の治療薬を創る〜製薬会社、…
第2部は“実践テンプレ集”。家庭での2週間観察と、受診時に役立つ外来チェックを、コピペで使える形にまとめました。家族・患者さん・医療者が同じフォーマットで記録できる…
世界最先端の治療薬を創る〜製薬会…

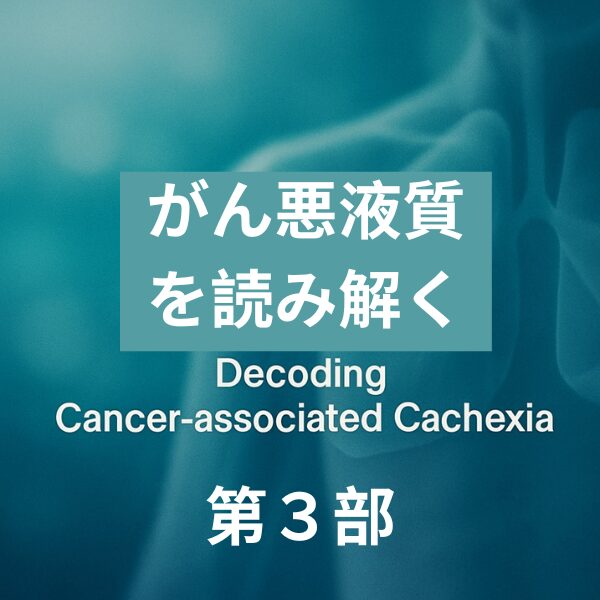
シリーズ:がん悪液質を読み解く — 超入門から最前線まで|第3部 – 世界最先端の治療薬を創る〜製薬会社、…
第3部は、外来で実践できる「フェノタイピング(表現型の見極め)」の回。CT体組成・身体機能・患者報告アウトカム(PRO)を束ねて、脂肪優位喪失型/筋優位喪失型/混合型…
世界最先端の治療薬を創る〜製薬会…

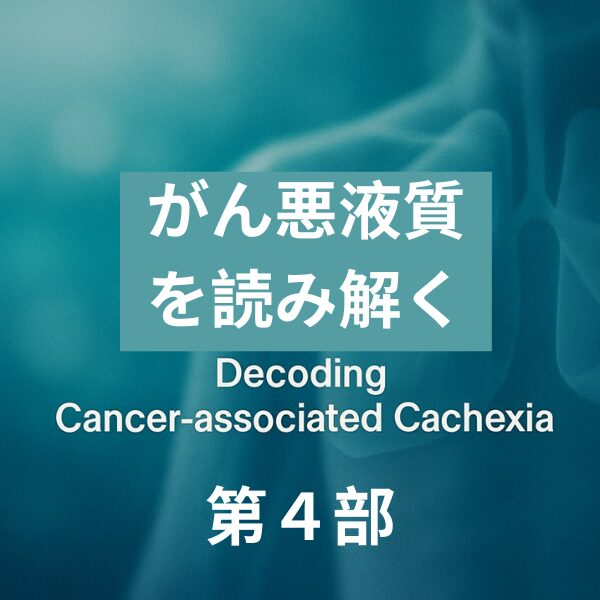
シリーズ:がん悪液質を読み解く — 超入門から最前線まで|第4部 – 世界最先端の治療薬を創る〜製薬会社、…
第4部は「舞台裏」。マウスだけでなくヒトのデータを手がかりに、食欲中枢・全身代謝・脂肪・骨格筋で何が起きているのかを、臨床像とつなげて解説します。第3部のフェノタ…
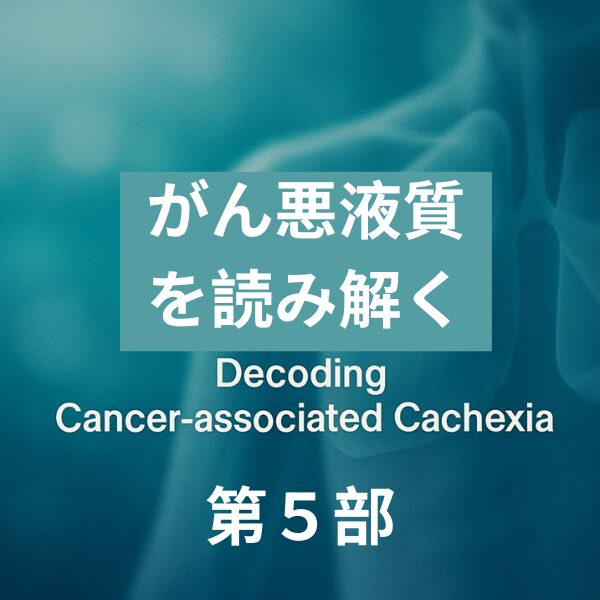
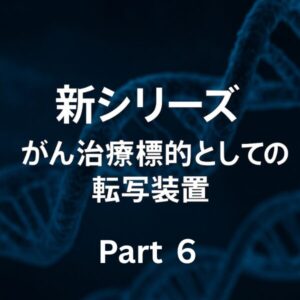
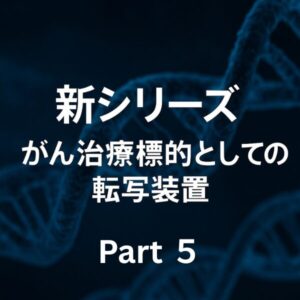
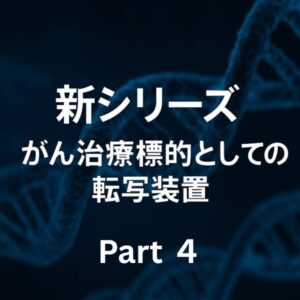
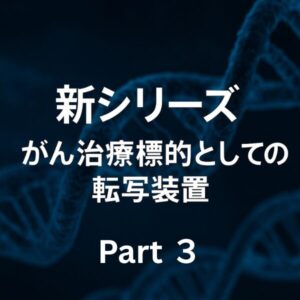
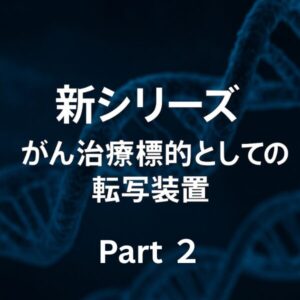
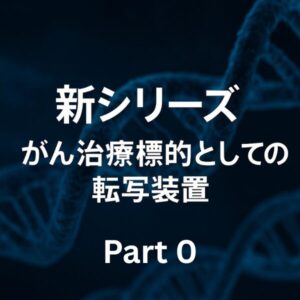
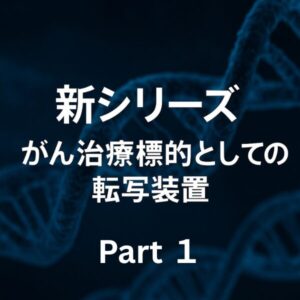

コメント